- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
- 参考文献
1 はじめに
脂肪の過剰摂取など食事の欧米化・晩婚化・出産回数の低下などライフスタイルの変化に伴い,本邦における子宮体癌発生頻度は年々増加している.日産婦婦人科腫瘍委員会の子宮体癌I~IV期の登録数は,1994年の2,115例から2005年の4,267例に増加している.また40歳未満の症例の占める割合も,それぞれ5.2%(109例)から7%(298例)と上昇しており,妊孕性温存が必要な年齢での子宮体癌数が増加傾向にある1).
子宮体癌は,エストロゲン依存性のtype1と,非依存性のtype2とに分けることができる.Type1は,組織学的にG1・G2の類内膜腺癌で子宮内膜増殖症の共存を認めるものであり,体癌全体の80%を占める.近年このtype1が増加しており,早期に診断され,予後の良好な例が多い.一方,type2は,組織学的に漿液性腺癌・明細胞性腺癌・G3の類内膜腺癌などであり,高齢者に多く,一般に予後が悪い.
子宮体癌の多くがホルモン依存性であることから,従来プロゲスチンを用いたホルモン療法が再発・進行時の補助治療として行われてきた.欧米では,プロゲスチン療法が性ステロイドホルモンレセプター陽性再発子宮体癌の治療の中心となっている.さらにプロゲスチン療法は,若年者に対して子宮温存を目的とする治療に応用されている.
プロゲスチン以外に,GnRHアナログ,アロマターゼ阻害剤,選択的エストロゲン受容体作用調節薬(selective estrogen receptor modulator : SERM)なども,再発症例に試みられてきているが,その効果は満足できるものではない.本稿では,ホルモン療法をその治療目標別に,(1)進行・再発子宮体癌に対するホルモン治療と,(2)若年性体癌に対する妊孕性温存療法とに分けて,おのおのの治療法の限界を中心に解説する.
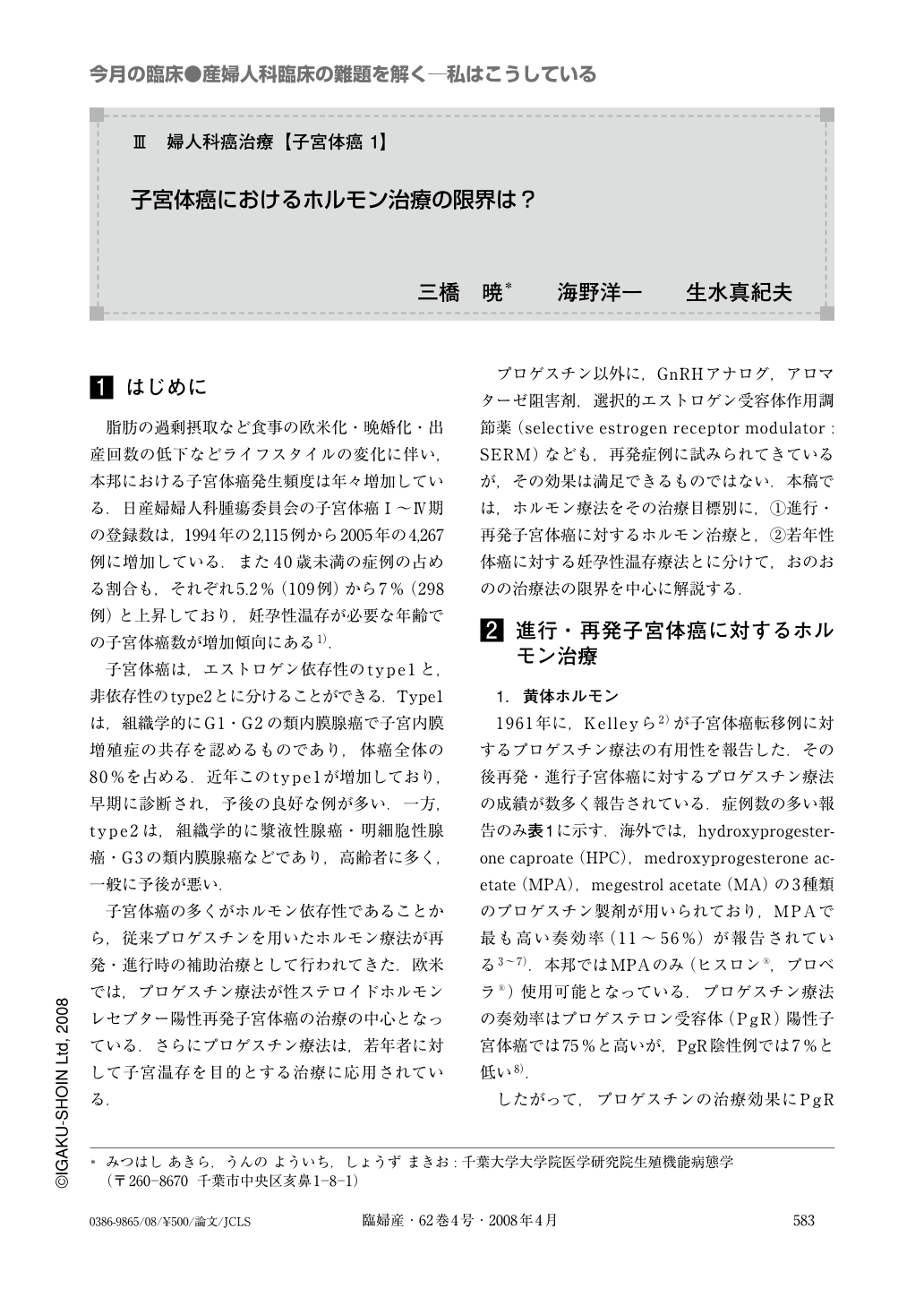
Copyright © 2008, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.


