Japanese
English
- 有料閲覧
- Abstract 文献概要
- 1ページ目 Look Inside
1980年にFurchgottはacetylcholineによって血管の内皮細胞から弛緩因子が遊離することを示したが1),その後bradykinin,substance P2)をはじめ多くの物質によって内皮細胞より拡張因子の遊離の起ることが明らかとなった。又,血管の内膜側を低酸素にすると拡張が生じ内腔灌流液中の6-keto PGF1αの増加がみられること,この現象には内皮細胞が関与すること3),血管の流量を増加させた時に見られる血管拡張は内皮細胞依存性であることなどが報告された4,5)。更に,norepinephrine,serotonin,angiotensin IIやthrombinのような血管収縮性の物質も内皮細胞から拡張因子を遊離させることが知られるようになった6〜8)。以上の実験事実は,ある種の血管作動薬は平滑筋細胞に作用するのみでなく同時に血管壁の内皮細胞にも作用することを示している。しかしながらこれまでに得られた結果の多くはリング状又はラセン状の摘出血管を使い,内皮細胞破壊の前後で用量反応曲線がどのように変化するかをみる形の実験で得られたものであるが,この方法では,内皮細胞を破壊することによって同時に内膜下組織を破壊してしまうという欠点があった。
今回私達は血管の内膜側と平滑筋側を夫々独立に灌流するシステムを犬の大腿動脈分枝とラットの尾動脈に適用し,血管の拡張を直接観察する方法を採用することによって上のような欠点を可及的に回避しながら,α1agonist又はα2 agonistによって内皮細胞依存性の拡張が起るか否かにつき観察したので,その結果につき報告する。この2つの血管についてはシナプス後にα1受容体とともにα2受容体も存在することが薬理学的に証明されている9〜12)。
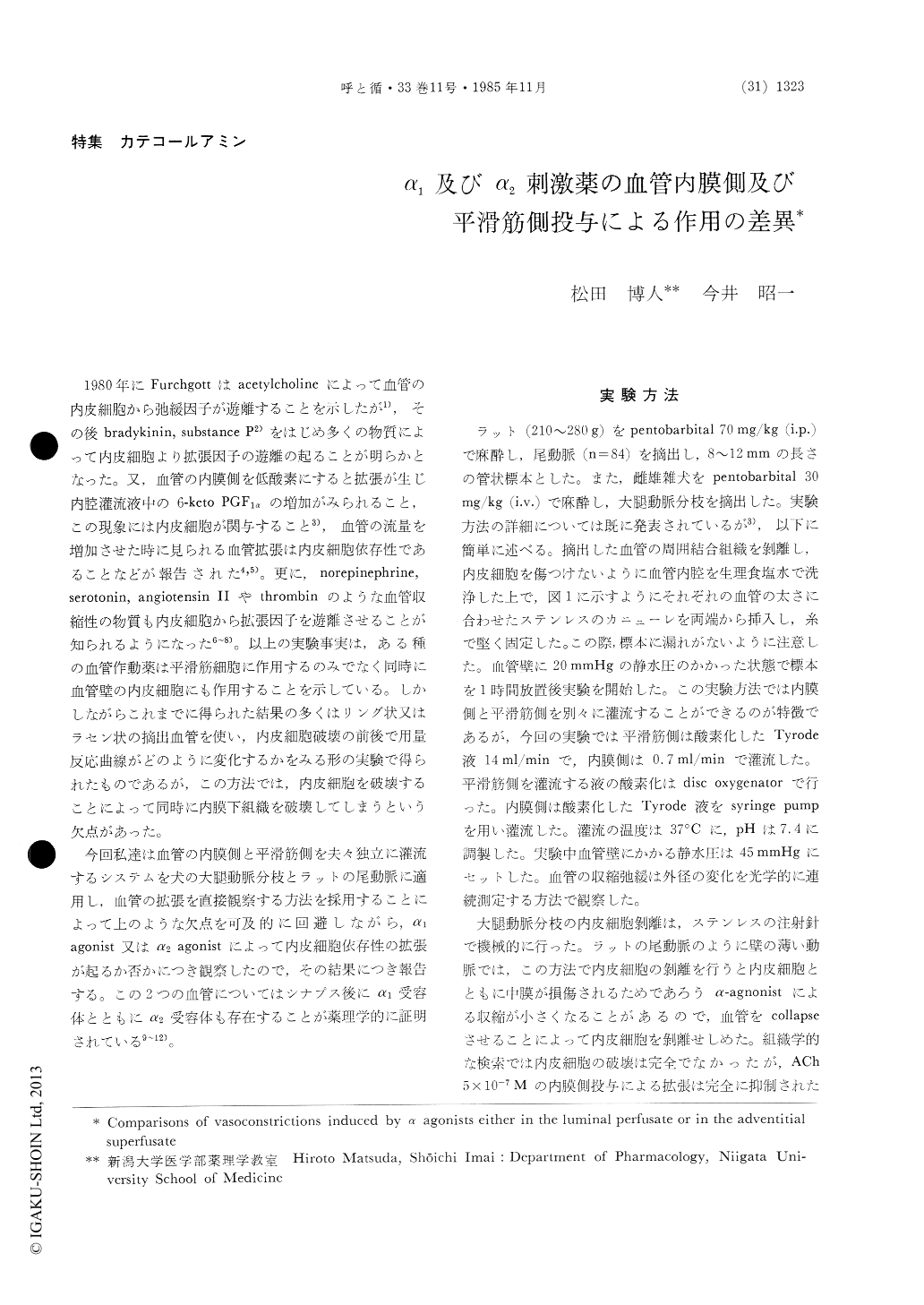
Copyright © 1985, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.


