Japanese
English
- 有料閲覧
- Abstract 文献概要
- 1ページ目 Look Inside
- 参考文献 Reference
Key Questions
Q1:高齢者の活躍のためにウェブアプリができることとは?
Q2:超高齢社会の新しい目標「貢献寿命」の延伸とは?
Q3:高齢者の活躍の促進に活用できるリビングラボとは?
はじめに
ウェブアプリGBER(Gathering Brisk Elderly in the Region)はジーバーと読み,地域の活発な高齢者を集めるという意味の英語の頭文字が名前の由来となっている.東京大学大学院情報理工学系研究科における研究プロジェクト「高齢者クラウドの研究開発」において,高齢期の柔軟な働き方として一人がフルタイムで働くのではなく,複数人の働ける時間や場所,スキルを組み合わせてグループで一人分の仕事を達成するモザイク型就労を実現するジョブマッチングのツールとして誕生した1).
GBERの社会実装は,2016年(平成28年)の千葉県柏市にある一般社団法人セカンドライフファクトリー(以下,SLF)での運用から始まった.SLFは,東京大学高齢社会総合研究機構による研究プロジェクト「セカンドライフの就労モデル開発研究」を通じて設立された,柏市の退職を迎えた市民コミュニティである2).SLFの設立メンバーは,東京大学が開催してきた一連の就労セミナーで,退職後の社会参加の重要性,退職後のセカンドライフの働き方としての生きがい就労,現役世代と働くことの心構え,地域企業の人手のニーズ,ICT活用の意義等,これからの高齢期の就労において必要な視点や考え方を学んできた200名ほどの参加者である.
SLFは,農家の補助,福祉施設での介護助手,住宅のガーデニング,学童保育等の仕事を請け負い,会員がそれぞれの都合に合わせて無理なく働くことに取り組んでいる.GBERはそのSLFの中で,ガーデニングを得意とする職能集団であるSLFガーデンサポートのグループの2015年(平成27年)の発足と合わせて研究開発がスタートした.SLFガーデンサポートの業務フローがどのようになるか,そこでICTはどのように役立てられるか,SLFガーデンサポートのメンバーと議論を重ね,試作システムの評価を繰り返していく中でGBERの運用がスタートした.システム研究開発の初期段階から,当事者であるSLFガーデンサポートのメンバーが利用する当事者としてデザインにかかわっているところは,インクルーシブデザインの形式をとっていたといえる.SLFガーデンサポートでは,グループリーダーが受注してきた仕事に対して,GBERを活用して各メンバーの就労可能なスケジュールに合わせてモザイク型のチームを形成して現場で作業を展開する.多人数で短時間で仕事を仕上げるのが売りとなっていて,依頼のリピーターも多い.
SLFガーデンサポートでのGBERの運用は,2025年(令和7年)で9年目を迎える.50名くらいの小さいコミュニティであるものの,出動人数単位で延べ就労人数をカウントすると1万人を優に超えている.1回の出動で5〜10名ほどのモザイク型のチームが形成されることから,百数十件を超える依頼が毎年寄せられていることになる.SLFガーデンサポートのメンバーからは,GBERは欠かすことのできないツールと言っていただけている.高齢者を対象にしてこれだけの長期にわたって活発に運用されているプラットフォームは,関連するクラウドソーシング業界でも多くはないだろう.高齢者就労を対象にしたビジネスの難しさを物語っているといえる.
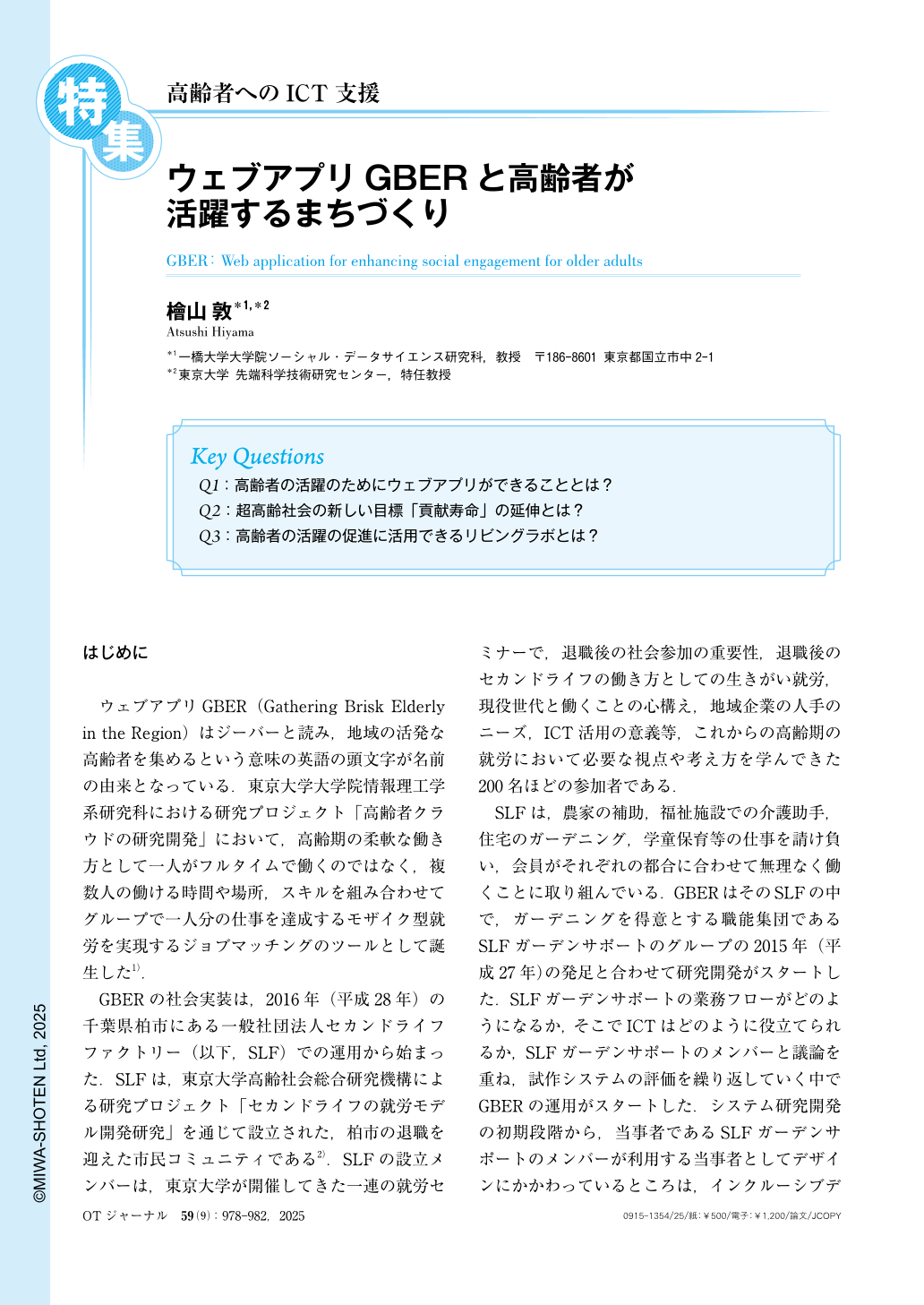
Copyright © 2025, MIWA-SHOTEN Ltd., All rights reserved.


