Japanese
English
特集 若者の自殺対策—精神保健の専門家としてリスクをどう捉えて対応するか
虐待と自殺
Abuse and Suicide
上野 千穂
1
Chiho Ueno
1
1京都市児童福祉センター診療所
1Clinic of Kyoto City Child Well-being Center, Kyoto, Japan
キーワード:
不適切養育
,
child maltreatment
,
自己組織化障害
,
disturbance of self-organization
,
寄り添う
,
stay close to
,
トラウマインフォームドケア
,
trauma informed care
,
小児期逆境体験
,
adverse childhood experiences
Keyword:
不適切養育
,
child maltreatment
,
自己組織化障害
,
disturbance of self-organization
,
寄り添う
,
stay close to
,
トラウマインフォームドケア
,
trauma informed care
,
小児期逆境体験
,
adverse childhood experiences
pp.201-207
発行日 2025年2月15日
Published Date 2025/2/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.048812810670020201
- 有料閲覧
- Abstract 文献概要
- 1ページ目 Look Inside
- 参考文献 Reference
抄録
子どもたちの心は柔らかい。育ってきた家庭環境になじむよう,無意識に大人の思いを吸収し取り入れる。虐待というトラウマとなる出来事ですら「自分の言動に問題があったのではないか」と考えようとする。しかし,不適切養育という土壌で長く育つと,思春期の頃には物事の捉え方や考え方において柔軟性を失い,一定の考えに収束され,非機能的認知に陥りやすくなる。もしも子どもにとってストレスフルな出来事が重なるとする。そのときフラッシュバックなどのトラウマ症状,先が見えないという絶望感に加え,手元にある薬や道具,危険な場所,ふとしたきっかけなどいくつかの条件が重なったとき,そして薬の影響や解離などでその一歩を踏み出すことに不安がなくなったときに自殺企図につながることがある。自殺予防のためにと,自傷や自殺企図を止めるよう伝え,養育者の関わりを正そうとすることが親子をさらに追い詰める場合もある。不適切養育とならざるを得ない家庭に何が起こり,何を必要としているのかを考え,親子のどちらにも寄り添いながら,それぞれ生き延びる道を粘り強く模索する支援が必要となる。
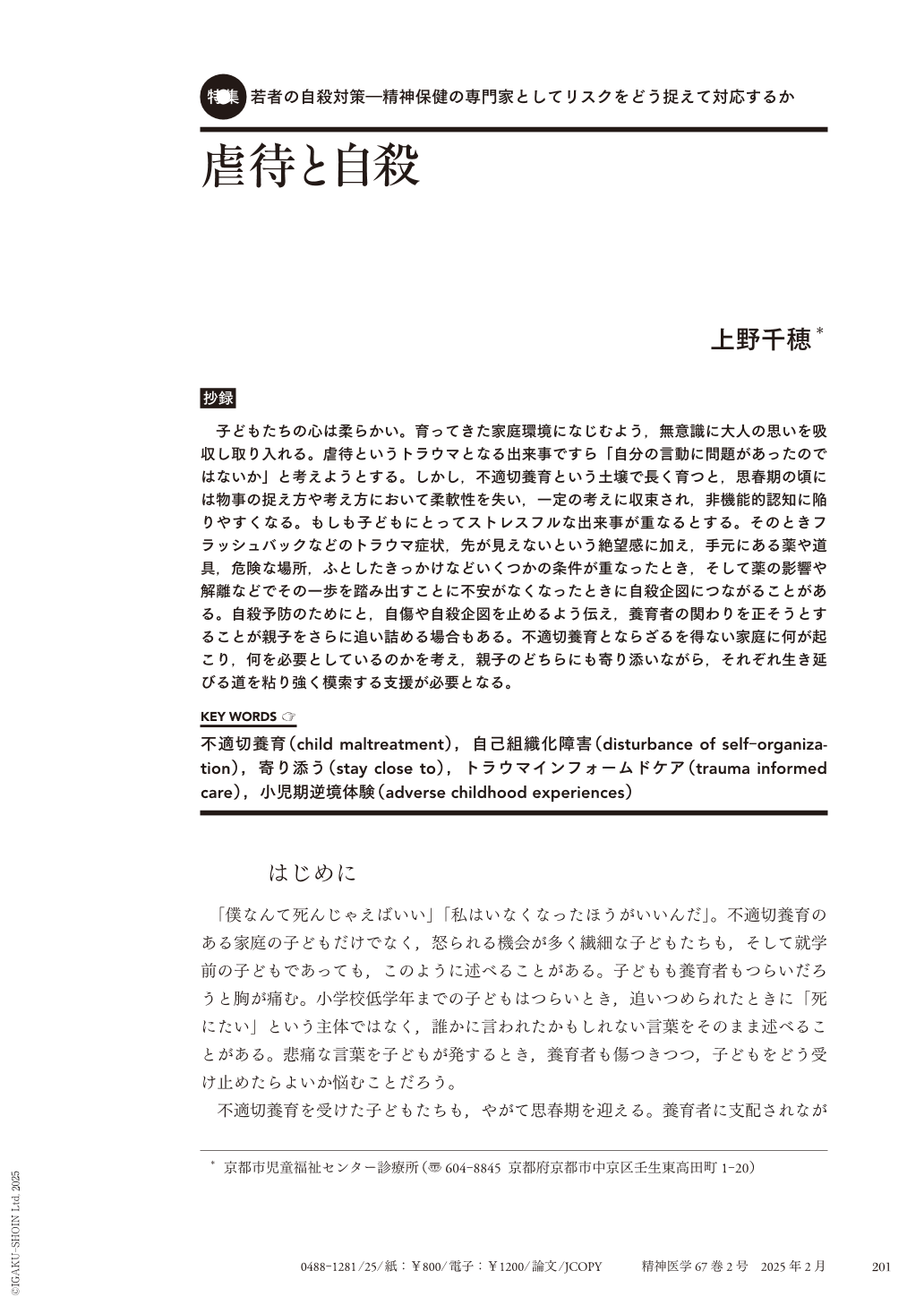
Copyright © 2025, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.


