- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
- 参考文献
Ⅰ 静かなノイズとしての思春期
思春期は,常に時代の文化や制度,社会の空気を最先端で感じとる存在である。それゆえに時代によってそのありようは社会を反映し,彼らへの対応や理解の方向性もそれに沿って変化してきている。大人になる重要な過渡期として「通過儀礼」で制御していた時代もあれば,繊細で脆く傷つきやすい感情を,大人への反抗として社会にも強く表出して「疾風怒濤の時期」をそのまま体現して荒れまくっていた時代もあった。
だがヒトという種である限り,時代の様相に関係なく第二次性徴に関わるホルモンの影響での情緒の揺れや感受性が鋭くなる時期であることなどの本質的な部分はまったく変わらない。しかし,このところ「いわゆる反抗期がなくなってきている」「中二病とか最近,きかなくなった」と耳にすることがある。そして「今の子は,大人びている」「逆らってまで自分を主張することがない」と凪のような印象が語られる一方で,「常識を知らなさすぎる」「あまりに幼稚で子どもっぽい」「善悪の区別がついていない」という声も同時によくきく。
それは子どもによっていろいろ違うということでは……?「大人びてみえる子」が「幼稚で子どもっぽい」一面を見せることもあるのでは……? とも思うが,確かに今の思春期は一見,「大人びた子ども」か「子どもの意識のまま大きくなった子ども」の二極化が進んでいるような印象もある。もちろん,今まで通りの典型的な思春期像―理想を語り,反抗し,親や教師とぶつかりながらも自分を見出そうとするような子どもたち―も当然,いるのだが……。
江戸300年の変化がたった20年で起こっているとも言われるような社会の急激な変化のなかで,今の思春期は何を感じとっているのだろうか。生まれたときからネットが存在しているデジタルネイティブの子どもたちは,それまでの「いわゆる思春期」とは現れ方がどこか違っている部分もあるように思う。
今の思春期は,あからさまな反抗や反発といった分かりやすい形をとらないことが多い。ただただ静かなノイズとして息苦しさとともに存在しているように思う。それは,LINEの既読スピードに反応する感度や,SNSの中でしか語れない孤独,そして言葉にならず,何となく身体に現れる違和感といったようなものとして堆積している。それは目に見えない感情のかたまりとして存在しているのだ。
分かりやすい反抗や反発ではないからこそ,私たちは彼らが意識せずに発しているその静かなノイズを,大人に向けてのシグナルとして捉えて,それをどう感知できるのかを問うていかねばならない。
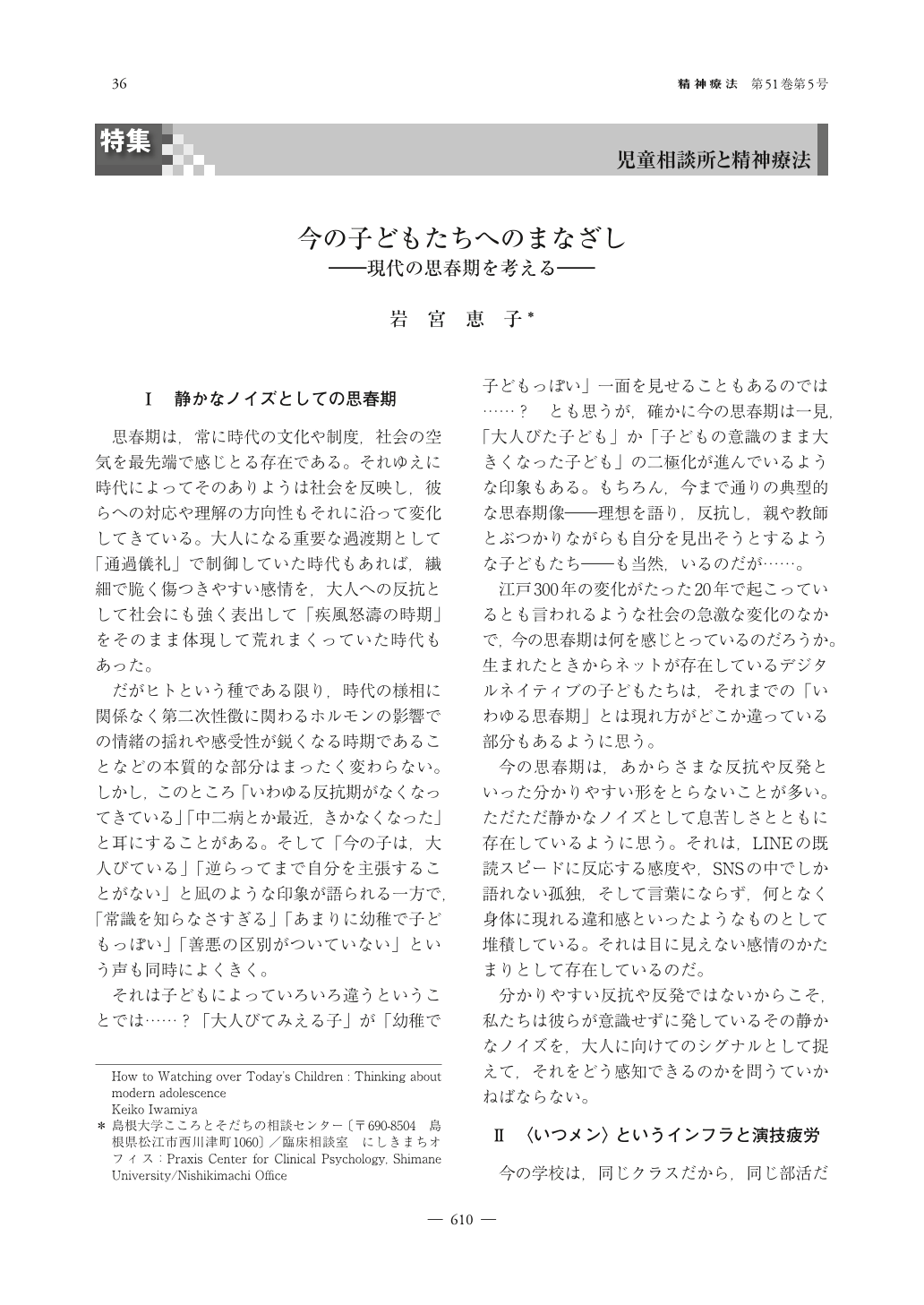
Copyright© 2025 Kongo Shuppan All rights reserved.


