- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
- 参考文献
はじめに
児童虐待が社会問題として取り上げられるようになって30年近く経つ。児童虐待防止法では児童虐待を発見したものは通告しなければならない,とされている。しかしよく耳にするのは「せっかく通報したのに児童相談所はすぐに家に帰してしまった。何かあったらどうするのだ」というお叱りである。通報する側はとても今の生活を続けさせるわけにはいかない,と思って通報する。「お父さんが殴って子どもがよろけて柱に頭をぶつけてたんこぶができた。打ち所が悪かったら大ごとだから保護してほしい」「母親が家事をしないのでこの子の食事は給食だけです。学校が休みの間に餓死してしまいますよ」保育園の先生,学校の担任や家庭訪問をした保健師さんが必死に訴える。保護しないのは児童相談所の怠慢だと怒っている。
地域で気にかかる子どもについて情報を共有する要保護児童対策地域協議会が置かれることで状況が改善している部分もあるがまだ十分ではない。こども家庭庁の統計によれば令和5年の児童虐待相談対応件数は225,509件。うち一時保護して年度中に解除になった件数が30,814件,施設入所等の措置が4,524件となっている。家庭内DVの目撃を含む心理的虐待が約6割を占めるとはいえ,ほとんどが一時保護すらされていない。児童相談所(以下児相と略記)は本来「児童について相談をする所」であり,親の急な入院など一時保護所は虐待以外にも対応している。首都圏や大都市の一時保護所の平均入所率が100%を超えている一方,一時保護所が設置されてない児童相談所も多い。
虐待を見つけて通報すれば今よりもっといい生活が送れるようになってその子どもは幸せだろうと考える人は多い。だからこそ通報してくれるのだと思う。でも生活が変わることがすぐにその子どもの幸せにつながるとは限らない。今まで過ごしてきた生活がその子どもにとっては普通であり,周りが思うほど不幸だと思っていないかもしれない。たとえば,昔おもらしの多い子がいた。保育士さんがとても丁寧にお世話をしてパンツが濡れていることはほとんどなくなった。でもその子は濡れていないパンツが快適だとは言わなかった。乳児の時から濡れたおむつのまま放置されてきた子だった。
最近児童福祉法が改正されて子どもの意見表明権が認められるようになった。以前は一時保護所に入るのも施設に行くのも周りの大人が判断し,良かれと思って説得していた。自分から一時保護を求めて児相にきた子もいたし,一時保護所で温かい食事が出てお風呂に入れることを喜んだ子もいた。でもその子どもたちもいずれは家に帰りたい,と思っていた。子どもは家庭だけで生きているわけではない。家庭から離すことはその子なりに学校や地域で張り巡らせていた根を無造作に引っこ抜いてしまうことでもある。今の生活が傍から見てあまり望ましいものでなくても子どもなりに手放したくない友だちや関わってくれる大人たちとのつながりや居場所がある。子どもに意見を求めれば家に帰ることを選ぶ子どもが圧倒的に多いだろう。児相もあえて家庭が壊れることを望んでいるわけではない。それでも家庭ではなく社会的養護にゆだねようと判断された子どもはそれだけ児相がいろいろな点で「重症」と判断したケースである。
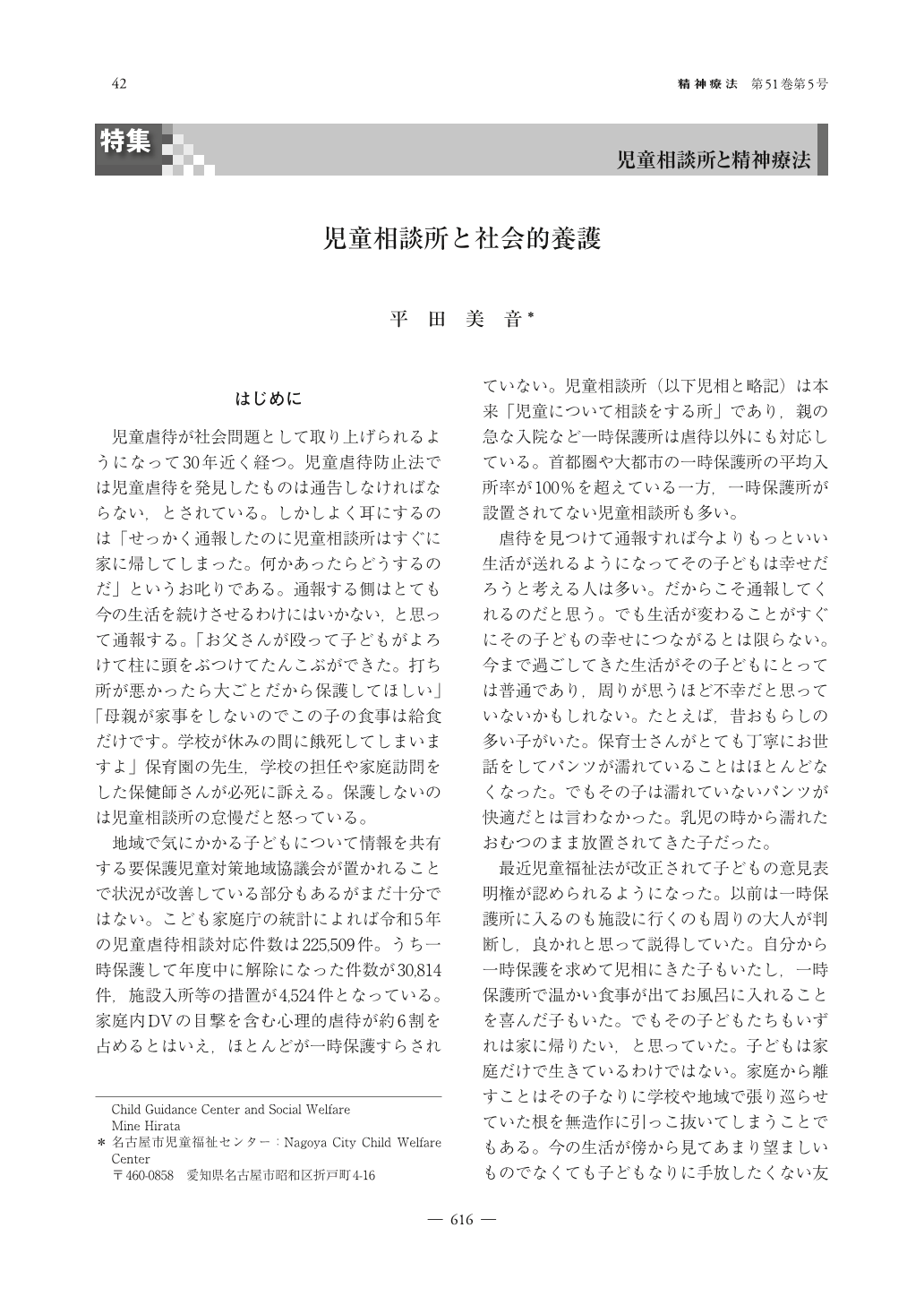
Copyright© 2025 Kongo Shuppan All rights reserved.


