- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
- 参考文献
はじめに
筆者の勤務先に設置された成人発達障害の専門外来を受診する人はひきも切らない。成人してからも発達由来の多様性によって悩まされている人はかくも多いのかと認識を日々新たにしている。しかし,今となっては信じられないことだが,一昔前までは精神科に成人の発達障害という考え方自体がなかったのだ。このことからもわかるように,発達障害の概念,解釈は時代を追うごとに大きく変わってきている。それはたとえば自閉スペクトラム症(ASD)の有病率がどんどん増えているのを見ても明らかだろう。1940年代には自閉症は1万人に2~4人程度と推定されていた(Wing & Potter, 2002)のだが,今日ではASDの有病率は1%程度と言われているのである(WHOのFact sheets 2023)。とりわけスペクトラムという概念が導入されたことによる影響が大きい。Wingは,それをパンドラの箱を開けた,と表現した(Wing, 2005)。DSMに自閉症やアスペルガー症候群,そしてその後ASDが収載された影響も大きい。診断基準は明確に示され,操作的診断がおこなわれるようになった。しかし,抽象化,概念化された診断基準だけを読んでも,発達障害の理念型について理解するのは難しい。いったん源流に立ち返り,理念型が成立した過程を知れば,少しは本質が理解しやすくなるのではないか。
そのような動機から,本稿では自閉症の第一症例といわれるドナルドについて,そしてそれにまつわる時代背景について調べてみた。それにあたって,2015年にSilbermanによって書かれた『Neurotribes』,そして2016年にDonvanとZuckerによって書かれた『In a Different Key』という2冊の書籍に盛り込まれた豊富な歴史的事実が大変参考になった。本稿では,これらの書籍からの引用に加え,原著を含む関連論文,およびドナルドが2023年に死去したことを機になされた報道などから,ドナルドという症例や自閉症という概念が成立した過程を振り返ってみたい。
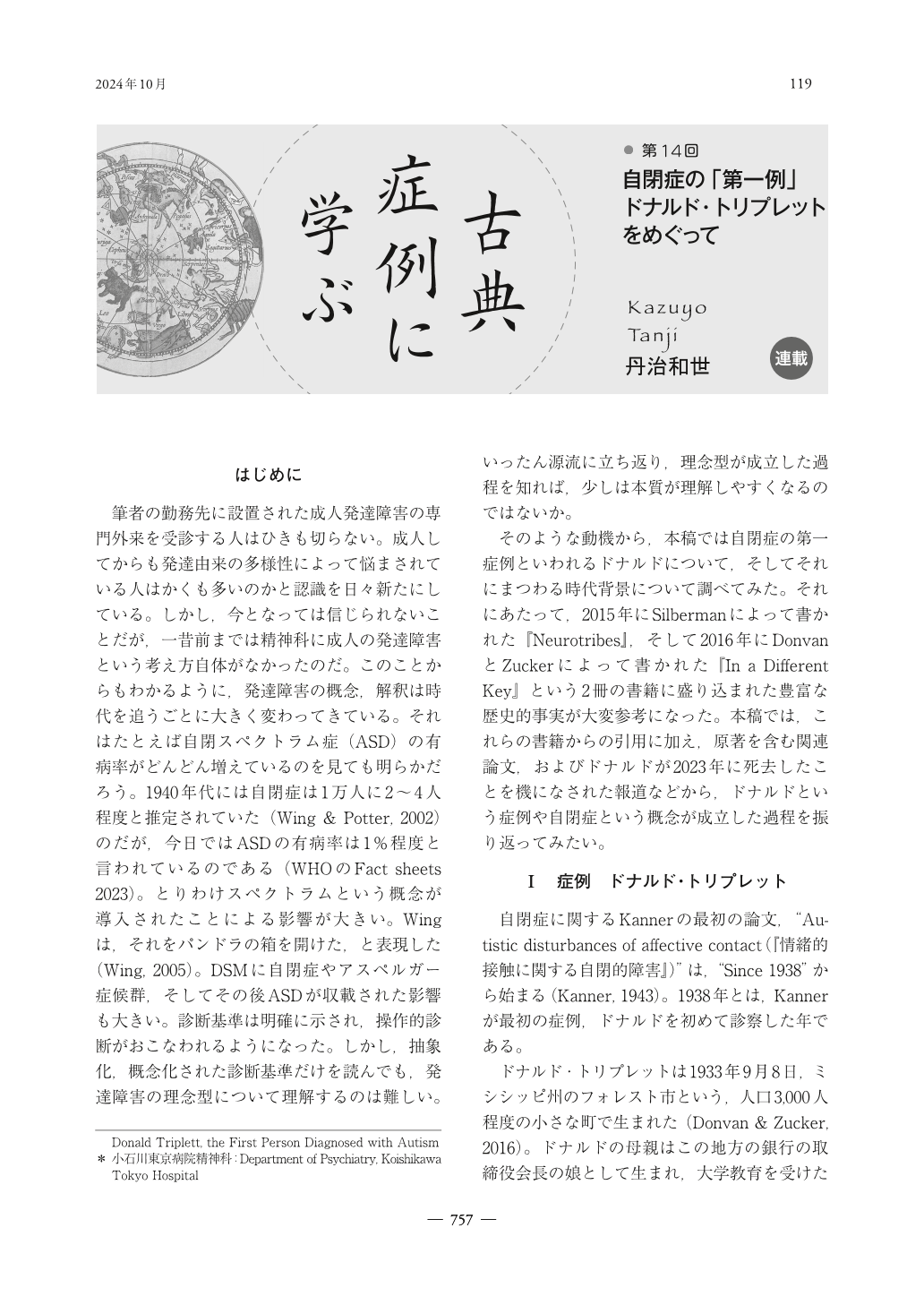
Copyright© 2024 Kongo Shuppan All rights reserved.


