連載 精神科診療の見立てと精神療法を,改めて考えてみよう
19世紀末における外傷性ヒステリー概念の展開―ジャネとフロイト④
原田 誠一
1
,
神田橋 條治
2
,
中尾 智博
3
,
高木 俊介
4
,
岸本 寛史
5
,
滝上 紘之
6
,
八木 剛平
7
1原田メンタルクリニック・東京認知行動療法研究所
2伊敷病院
3九州大学大学院医学研究院 精神病態医学
4たかぎクリニック
5静岡県立総合病院
6應義塾大学医学部精神・神経科
7翠星ヒーリングセンター
pp.763-775
発行日 2024年10月5日
Published Date 2024/10/5
DOI https://doi.org/10.69291/pt50050763
- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
- 参考文献
Ⅰ 臨床場面におけるフロイトの特徴
前回の後半で『ヒステリー研究』の「エミー・フォン・N夫人」を例に挙げて,臨床場面におけるフロイトの接し方の問題点に具体的に触れた。こうしたフロイトの特徴の一部は,その後も生涯にわたって一貫してみられたようである。このテーマと重なるところが多い内容を,北村(2021)は「フロイトが共感の治療的意義を認められなかった理由と,それが彼の治療に与えた影響」という視点を元にして,次のように述べている。
幼少期のフロイトは,ユダヤ人の母からは十分に包容されず,その代わりチェコ人の乳母から大切にされて育った。ところがこの乳母が突然いなくなったために,彼の精神病的不安が喚起され,この不安を乗り越えるために彼はチェコ人の乳母と,彼女の記憶と結びつく故郷の地,そして非ユダヤ的世界への憧憬を抱くようになった。
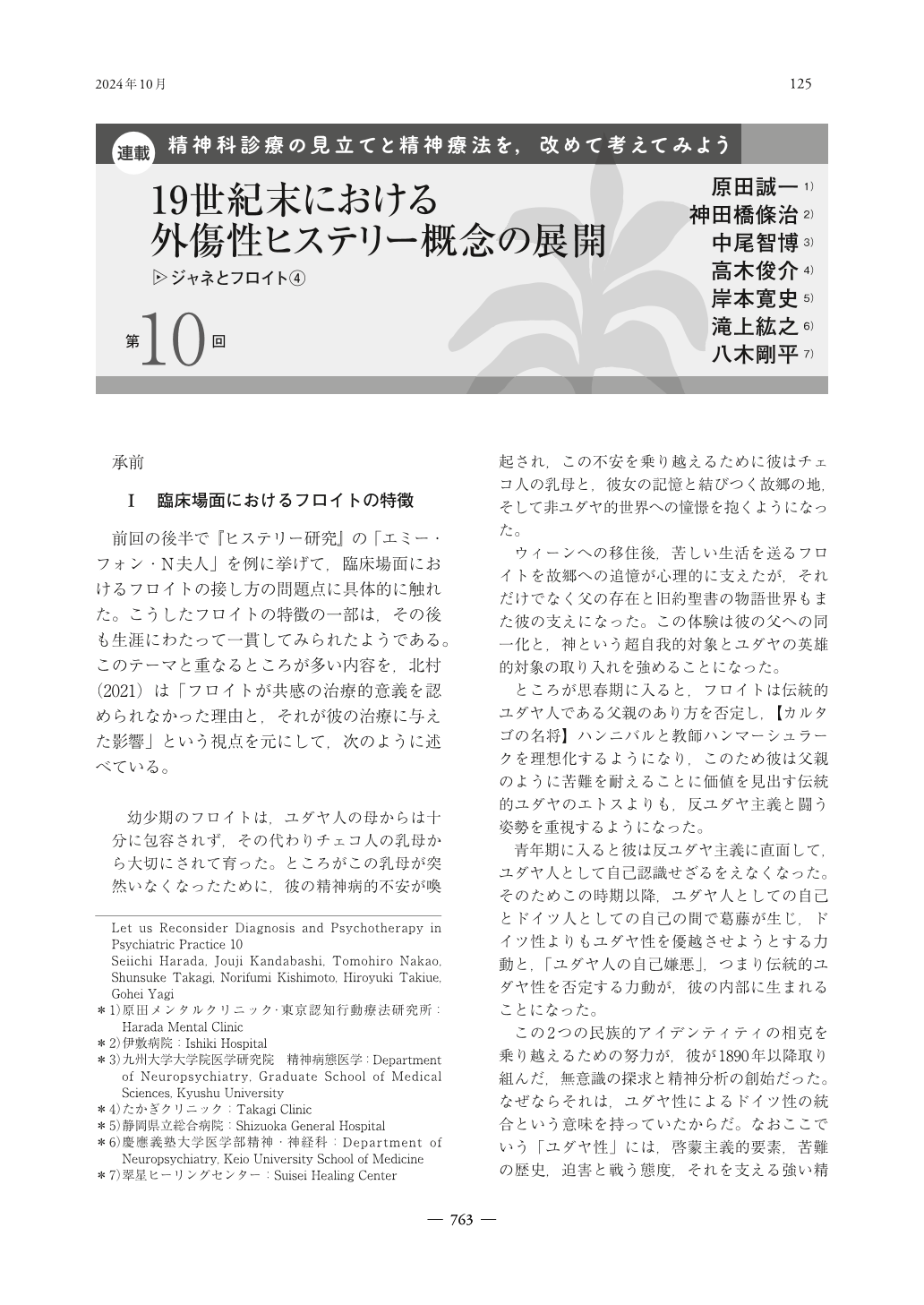
Copyright© 2024 Kongo Shuppan All rights reserved.


