- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
- 参考文献
I 心理臨床行為は日常か,非日常か
一昔前は,カウンセリングというものは非日常性があるからよいのであり,現実から切り離された時間や空間でクライエントが考えたり語ったりすることこそ利点があるとされた。また,そのなかで何をどのように考えてもよいというクライエントの主体性に重きを置き,その人なりに抱く主観こそが大切であるという臨床姿勢が重視された。もちろん今でもそれが大切なのだと考える心理臨床家も少なくない。筆者もそれを否定するつもりはなく,それこそ自分が依拠する学派によっても違いがあるし,どの現場で心理臨床の実践がされるかによってもスタンスが違うと考えている。必ずしもこうでなければならないというわけではない。
ただ,筆者がこれまで携わってきた臨床は,非行や罪を犯す少年,犯罪者へのかかわりであったり,家庭の紛争の最中で身動きが取れなくなっている親や子どもへの対応が中心であった。なかには適応が極めて悪くなり,何をするにもうまくいかない発達障害を抱える人もいたり,虐待やいじめを受け心が深く傷付いている被害者もいたりした。そんな彼らにとっては筆者との面接が仮に一時の安らぎの場となり,日常とは離れた時空間になったとしても,面接が終わるとまた厳しい現実に戻っていかねばならない。そんな空気を醸し出して面接室から帰って行くクライエントの後ろ姿を何度も見せつけられてきた。そして,筆者は自分の臨床がこの一時の面接にとどまらず,彼らの日々の生活に少しでもよい効果として反映されなければ意味がないのではないかとさえ感じるようになった。しかしながら,彼らの抱える問題はあまりにも深刻であったり,障害の程度が重篤であったりして,短時間の筆者との面接の効果はそれほど見込めなかった。筆者は自分の臨床行為が果たして役に立つものであろうかと途方に暮れていた。かといって目の前のクライエントを見放すこともできず,かかわりこそ続けてはいるものの,筆者の心のなかでは「本当にこれでいいのだろうか?」とモヤモヤ感が常に渦巻いていた。
そんな時期に,以下のような村瀬嘉代子の言葉に出会った。「クライエントと週に1時間のセラピーをしていたとするならば,セラピストはその1時間が残りの6日と23時間とどう結びついているかを考えなくてはならない」。この言葉は筆者にはとても衝撃で,心理臨床家がしているセラピーが現実と離れた非日常性を大切にするか否かはともかくとして,それがクライエントの日常といかにつながっているかを考えなくてはならないと主張していたからである。
筆者はそんな臨床姿勢を持つ村瀬にその後ずいぶん影響を受けてきた。例えば,カウンセリングやさまざまな心理的支援やプログラムを実施する場合,それがクライエントに効果をもたらすものでなければならないと村瀬は強調する。また,それをエビデンスをもって言えることが必要と指摘する。そのことを意識せず,あるいは治療効果もないのに漫然とそれを続けていくことは,セラピストの自己満足でしかないとまで村瀬は言うのである。
以前ならともかく,今はクライエント側の権利意識も強い時代であって,無自覚で漫然とした臨床活動をすること自体がもはや職業的な倫理に抵触しかねない。仮に,クライエントの主訴を改善させるセラピスト側の臨床能力が不足していたとするならば,心理臨床家はそのことを率直に認め,それをクライエントに開示して,他の適切なセラピストにリファーするなり,クライエントともう一度主訴について話し合い,治療目標を新たに設定してセラピーを継続していくかどうかをしっかり話し合わねばならないであろう。村瀬(2009)はこの点について,「相手の生が少しでも生きやすいものになるために,現実的な目標を定め,その目標実現のためにふさわしい技法を用い,かつ治療者は自分の行為に責任を負って,かかわる過程が『治療としての関係』なのです」(p.17)と語っている。
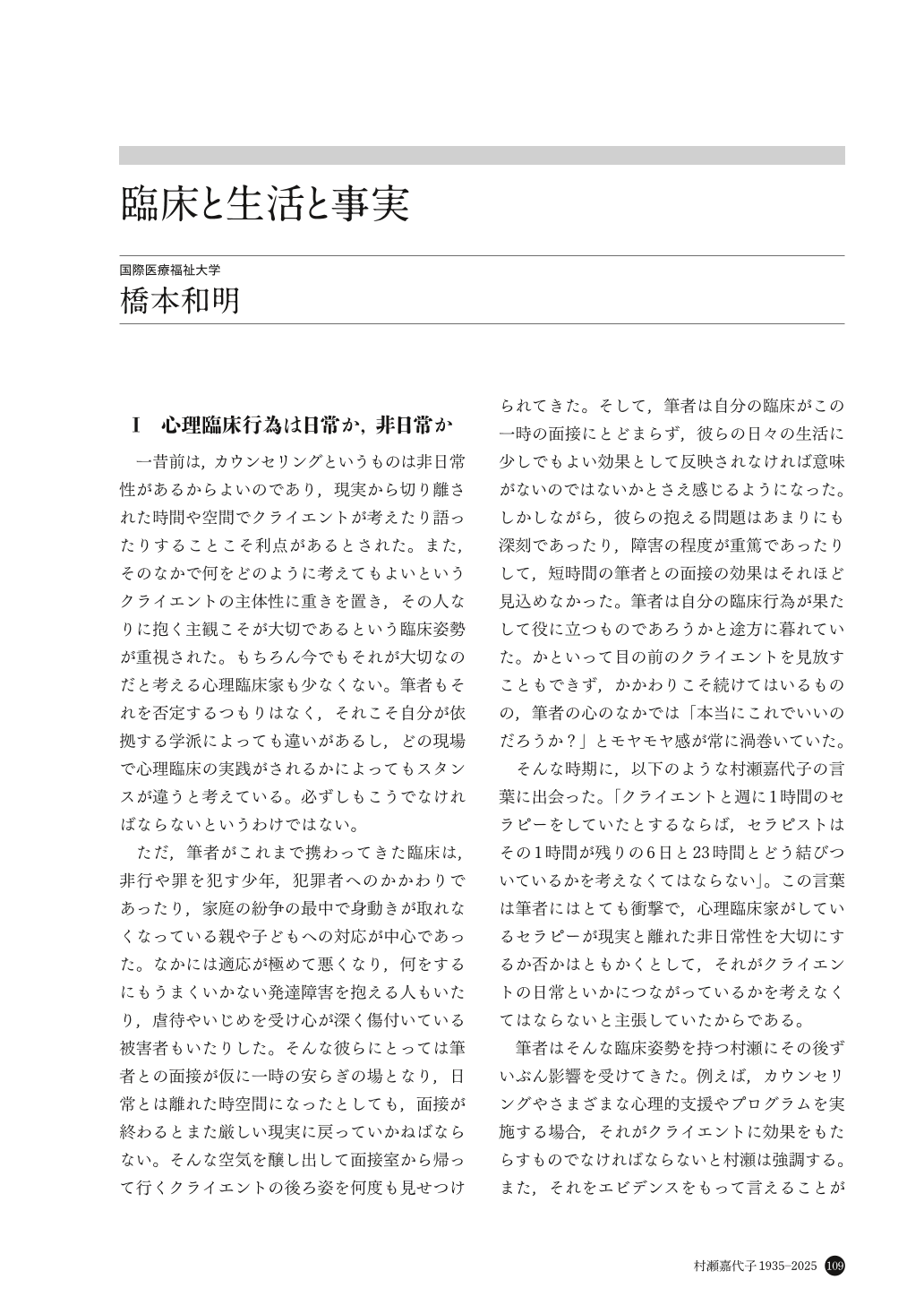
Copyright© 2025 Kongo Shuppan All rights reserved.


