- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
I はじめに
村瀬嘉代子先生の論文に初めて接したのは,1978年に『季刊精神療法』(金剛出版)に掲載された「さまざまな身体症状を訴えた一少女のメタモルフォーゼ」という事例論文である。この年に私は家裁調査官補として勤務を始め,読んだのは翌年のことだったと記憶している。大学院では実験社会心理学専攻で,Freudの著作や実存主義哲学,当時脚光を浴び始めていた行動理論の書籍は読んでいたものの,実践的な著作にはほとんど触れていなかった。実務上の必要に迫られ,さまざまな心理療法,カウンセリングの実践報告を読みあさっていた時期のことだった。
これは少々差し支えのある感想かもしれないし,多分に当時の私の理解力不足があったのだと思うが,多くの心理療法事例を読んで,なるほどとは感じつつも,そこで描かれる心理プロセスがどこか中空に浮かんでいるもののように思え,裁判所という極めて現実的でありながら人々の強烈な感情が交差する場でのヒントになるとはなかなか思えなかった。
そんななかで出会った村瀬先生の論文は,まさに強烈な印象を残した。
「花束を持って家庭にお見舞いに行く」「一緒にお菓子作りをする」「本人の希望を入れて自宅のおせち作りを任せる」等々,学んでいた治療原則からは著しく逸脱する方法だったし,それを同じように意味ある形で実践できるとは到底思えなかったけれども,このような子どもや家族(ひいては治療者にも)触知可能で存在感を残す働きかけが,深く広範な心理的波及力を持って事態を動かしていくありように衝撃を受けた。論文を読みながら,地上の一点から高い中空と広範な地表に光が広がるようなイメージが浮かび,本人,家族の心の振動が見て取れるように思えたのである。後に中井久夫先生がこの論文へのコメントのなかで,囲碁の布石になぞらえ「盤面に石を打つ」と表現し,「治療者が去っても石は残る」と書かれているが,まさに急所への一手が効いて,確固とした存在感を残してその後の動きを促していくのである。
家庭裁判所という一つひとつの判断を「事実」「行為」の形で示すことが求められる場にあって,子どもや家族の健康的な成長を促すためには,その心理的意味を十分に吟味しつつ,確かな臨床的根拠をもった具体的働きかけこそが肝要なのだと痛感した。また,何度も読み返すなかで,そうした一つひとつの働きかけのなかに「退行」と「進展」,あるいは「母性性」と「父性性」が絶妙に組み込まれており,それが悪性の退行や嫉妬心などを防ぎ,一見危ない橋を渡っているようでいながら,周到に見通された道を進むことを可能にしていることも見えてきた。家裁調査官の仕事の道標を得たと感じたときであった。
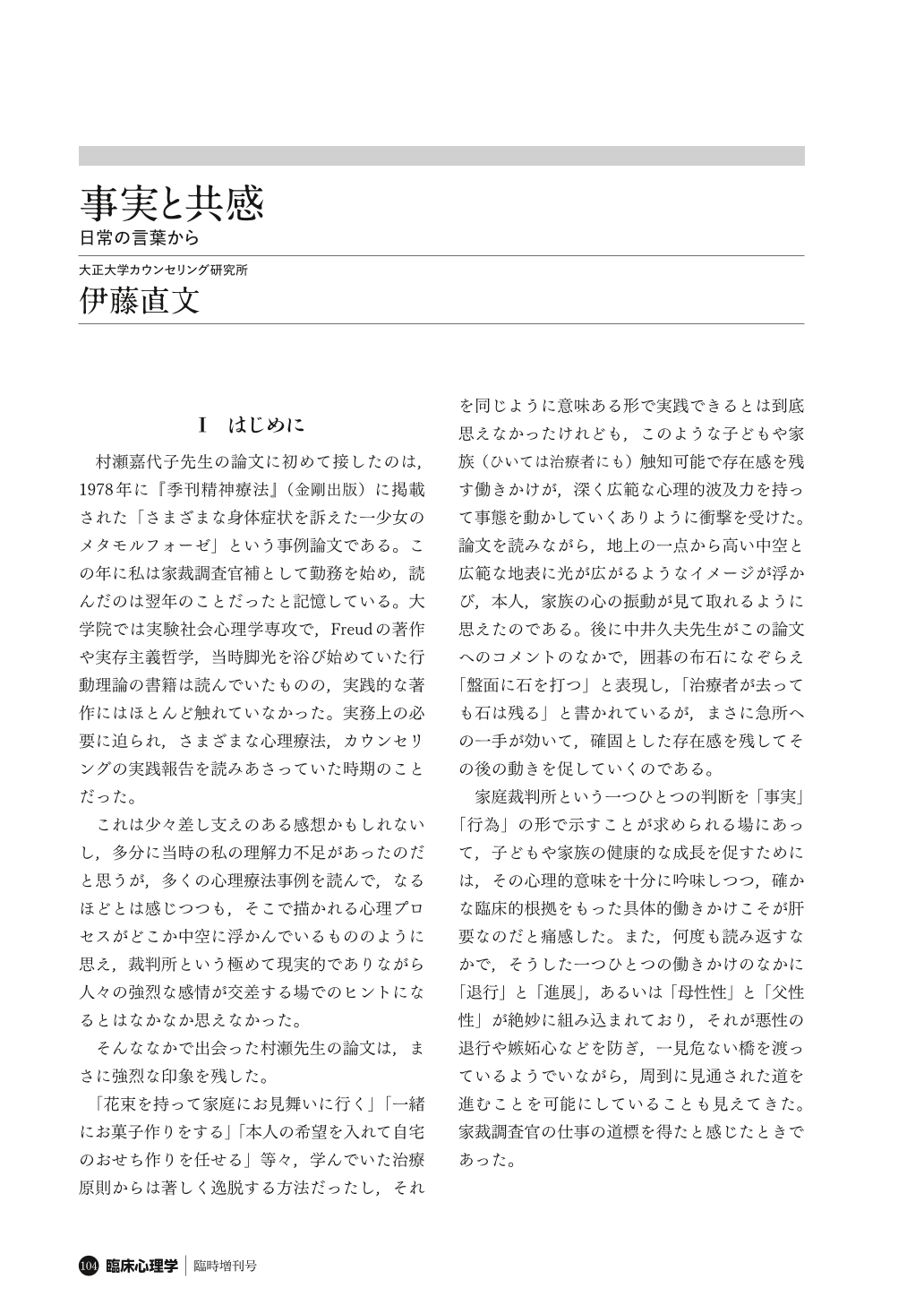
Copyright© 2025 Kongo Shuppan All rights reserved.


