- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
- 参考文献
1 はじめに
地域での臨床実践において,まずは,支援者側の協働的姿勢が重要であると筆者は考えている。この協働的姿勢については,地域精神保健の現場で,利用者やその家族との関わりのなかで学んだ,フィンランドのJaakko Seikkula(Seikkula et al., 2006)が地域に根差した精神科医療において実践してきたオープンダイアローグと,アメリカのAnderson & Goolishian(1988)の提唱するコラボレイティブ・アプローチの考え方に照らし合わせることで,筆者自身のなかで理解を深めてきた。協働的な臨床実践において欠かせないのはクライエントやその家族との対話であるが,それは,ただ会話するということではなく,相手の話を「聴く」ということである。そのなかには,相手の話を先入観なく聴くということ,そして「応答」(Seikkula & Trimble, 2005)が含まれる。応答とは,聴いた内容について質問をしたり,聴いて理解したことを支援者が言葉にして伝えたりすることを指す。
「聴くこと」から始まる対話のなかでは,クライエントのニーズが自然に表現されやすい。何に困っているのか,何を望んでいるのか,何を必要としているのか。支援者との間でクライエントのニーズが言語化され共通認識として表れると,何にどう取り組んでいくかを一緒に検討できる。
本稿では,協働的な地域支援におけるアセスメントとそれに即した支援の展開について,事例を通して論じてみたい。本稿のテーマ「病棟から社会へ」について,まずは,筆者がオープンダイアローグと出会う数年前に,精神科クリニックで経験した支援事例から始めたい。なお,各事例における支援内容は筆者のこれまでの経験に基づいているが,登場人物の名前・性別・年齢などの属性や生活歴,臨床像,団体や機関名などは全て架空の設定であることをお断りしておく。
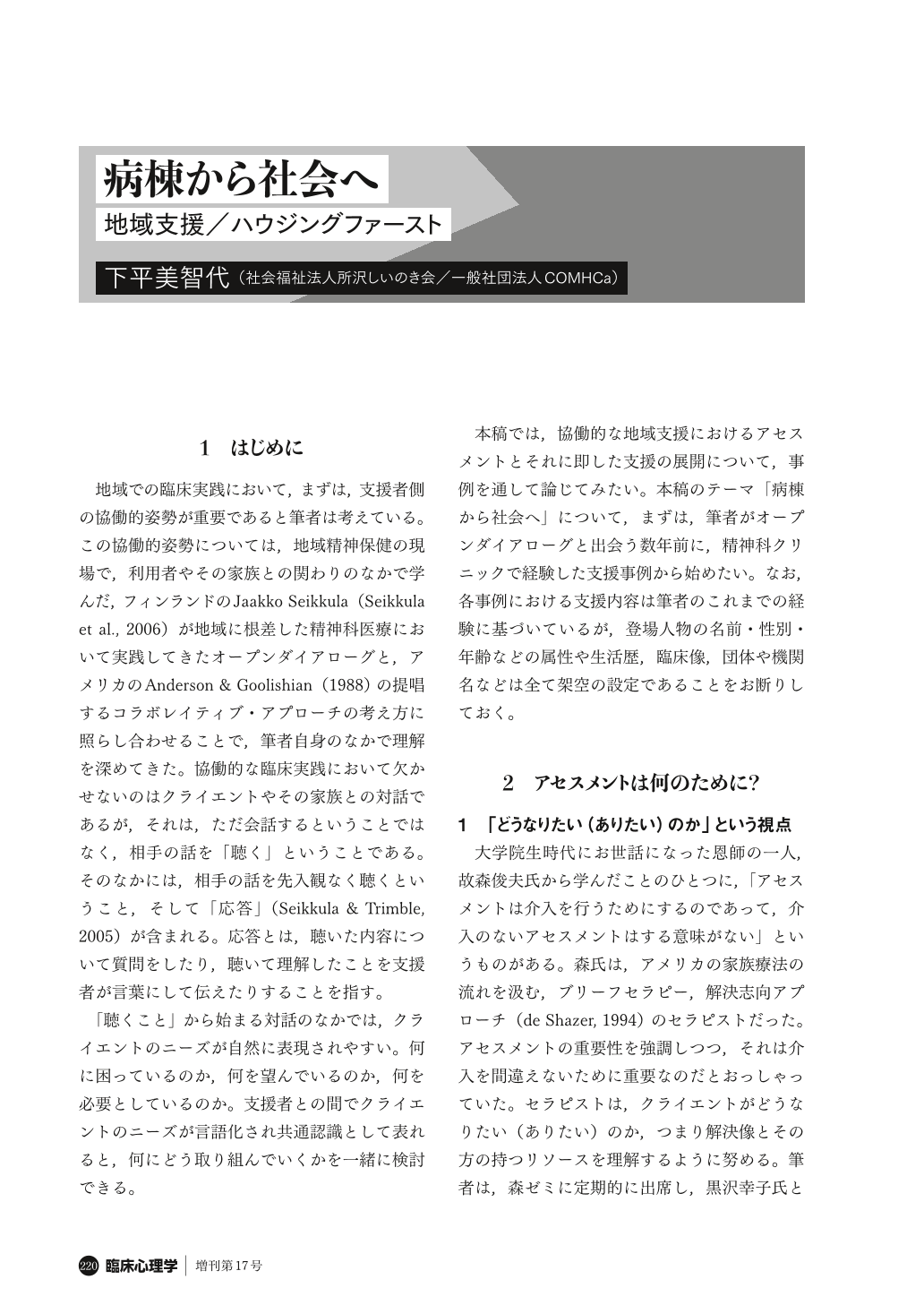
Copyright© 2025 Kongo Shuppan All rights reserved.


