特集 26ケースで学ぶ臨床心理アセスメント――インテークとフィードバックをつなぐ〈スキル7〉
授業になじめない子
日戸 由刈
1
1相模女子大学
pp.120-125
発行日 2025年8月30日
Published Date 2025/8/30
DOI https://doi.org/10.69291/cp25070120
- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
- 参考文献
1 はじめに
学校において,授業になじめず困り感を抱えた子どもは少なくない。文部科学省の最新の調査(2022)では,小中学校の通常学級に在籍する「知的発達に遅れはないものの学習面又は行動面で著しい困難を示す」児童生徒数は8.8%と報告されている。
しかし,このうち子ども本人や保護者が自ら問題を自覚し,主体的に相談行動を取ろうとする事例はそう多くはない。たいていの場合,保護者だけでなく子ども自身も「授業になじめないのは本人の努力不足のせい」と考える。結果,問題を放置され続けた子どもは次第に自尊感情を悪化させ,「誰もわかってくれない」という諦めの気持ちや不信感を内面に蓄積していく。ある日突然学校に行けなくなったり,保護者の些細な言動にカッとなって暴れるような事態に発展する場合もあるだろう。
問題を未然に防ぎ,子どもの自尊感情や心の健康を維持するためには,学校内で子どもの行動や困り感をタイムリーに把握できる立場にある教員によるアセスメントが欠かせない。学校内には児童専任や生徒指導,特別支援教育コーディネーター,養護教諭など子どもの発達や心の問題に対応するための教員が配置され,「チーム学校」の体制づくりがなされている。また全ての教職員を対象に,子どもの発達や心の問題をテーマとした研修会も開催されている。学校外の心理職が学校教員へのスーパーバイズや研修会講師を依頼される機会も多いだろう。
本稿では,学校教員を下支えする心理職という立場から,教員や学校のアセスメント力を高めるために職種を超えて共有したいポイントを,2つの架空事例を通して考察する。
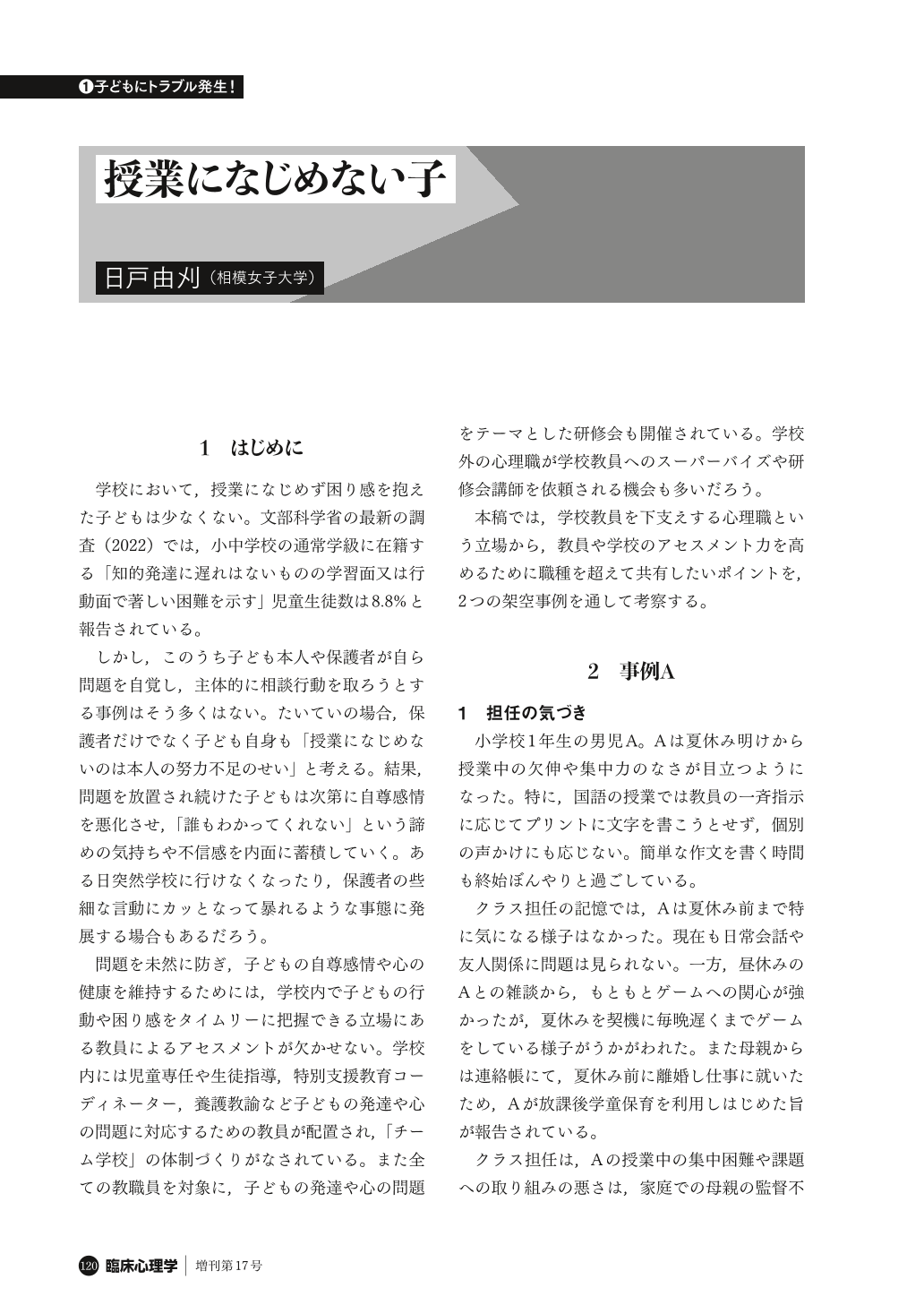
Copyright© 2025 Kongo Shuppan All rights reserved.


