特集 26ケースで学ぶ臨床心理アセスメント――インテークとフィードバックをつなぐ〈スキル7〉
今までの自分でなくなった――高次脳機能障害
小海 宏之
1
1関西大学人間健康学部・大学院心理学研究科
pp.113-118
発行日 2025年8月30日
Published Date 2025/8/30
DOI https://doi.org/10.69291/cp25070113
- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
- 参考文献
1 はじめに
学術用語としての高次脳機能障害とは,一般に大脳の器質的病因により,失語,失行,失認など比較的局在の明確な大脳の巣症状,注意障害,記憶障害などの欠落症状,判断・問題解決能力の障害,行動異常などを呈する状態像とされている(三村,2018)。一方,行政用語としての高次脳機能障害とは,2001年より開始された厚生労働省による「高次脳機能障害支援モデル事業」において定義された診断基準に基づく。具体的には,「脳の器質的病変の原因となる事故による受傷や疾病の発症の事実が確認されている」および「現在,日常生活または社会生活に制約があり,その主たる原因が記憶障害,注意障害,遂行機能障害,社会的行動障害などの認知障害である」(ただし,先天性疾患,周産期における脳損傷,発達障害,進行性疾患を原因とする者は除外する)とされている(表参照)。
本稿では,スポーツ事故により突然,高次脳機能障害を呈した事例を通して,高次脳機能障害者に対する臨床心理・神経心理アセスメントについて考察を加えて報告する。
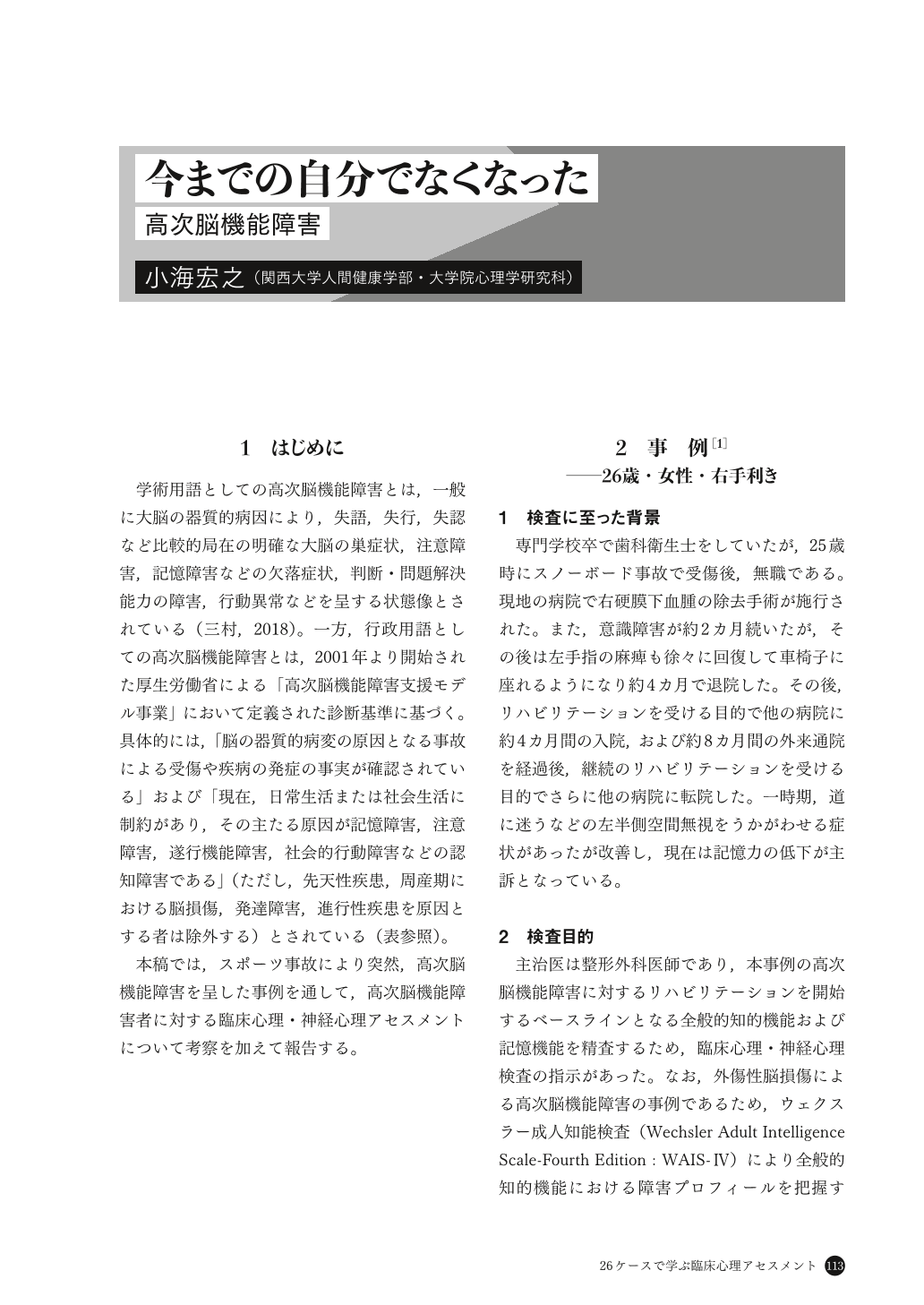
Copyright© 2025 Kongo Shuppan All rights reserved.


