- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
- 参考文献
I はじめに
この雑誌はいうまでもなく臨床心理学の雑誌である。とすると,ここでの「学派school」という言葉は,臨床心理学内部の「学派」のことだと理解していいのだろう。「精神分析を生きる――学派と自己形成」という編者から与えられたタイトルの下で,私は何を書けばいいのだろうか。着手してすぐに,私はこの原稿の執筆を引き受けてしまったことを後悔する仕儀となった。そして大変な困惑の渦中にはまってしまった。
そもそも私は精神分析家であり,精神科医である。心理学の教育は受けていないので,自分が臨床心理学者であると思ったこともなく,臨床心理学実践をやったこともない。だから,臨床心理学における学派という概念がいまひとつ実感的にわかっていない。臨床心理学者やその実践家が学派というものを持つということがどのような体験なのか,追体験できない。そうした自分がこの主題で果たして何か書けるのだろうか。
精神科医としての自分について考えることが参考になるのかもしれないと思ってみた。精神医学に精神分析学派というものがあるだろうか。どうもありそうもない。どう考えても精神分析は精神医学とは独立のディシプリンである。私が精神科医として仕事をしているとき,精神分析派として仕事をしているという自覚など全くない。私が精神科クリニックで週一度の外来診療をやっているとき,私はふつうの精神科医としてできるだけ真っ当に精神医学実践(精神科臨床)をやろうと思っているにすぎない。私にせよ,同僚の精神科医である精神分析家にせよ,自分が精神分析派の精神科医だとは思っていないだろう。
そもそも精神医学実践と精神分析はゴルフとテニスくらい違う。ゴルフとテニスが全く違ったスポーツであることは一目瞭然である。広い野原や森林のなかでボールを打ち,ボールをできるだけ少ない打数でグリーン上にあるホールに入れることを目的にするゴルフ。ネットを挟んでふたりのプレイヤーがボールを打ち合い,相手のコートの範囲内で相手が打ち返せないところにボールを打つことを目的にするテニス。ゆっくり歩いてコースをラウンドして,一日に多くて100回ほどしかボールを打たないゴルフ。走り回ってボールを追いかけ,数時間に1,000回以上もボールを打つテニス。似ても似つかないスポーツである。だが,ボールをある方向に飛ばすためにラケットやクラブをスウィングすること,そしてボールとラケット面,クラブ面とのコンタクトを意識していることは共通している。実際,そのふたつの競技のスウィングには共通点がある。だから,テニスの経験はゴルフをするときに生きるし,ゴルフの経験もテニスに生きる。私の個人的な体験でもそう実感できるが,テニスの名プレイヤーにゴルフのすごく上手な人がけっこういることは事実である。しかし,テニス派のゴルファーだの,ゴルフ派のテニスプレイヤーだのといったものがいるという話は聞かない。
同様に,精神分析実践と精神医学実践は別物である。テニスプレイヤーがゴルフをやるときテニスの経験が役に立つように,精神分析家であることが精神医学実践をやるときに役に立つことはよくある。それは確実である。だが,かといって精神分析派の精神科医がいるわけではない。私はそう考えている。
さて,ここまでの議論の精神医学を,臨床心理学に置き換えることはできるだろうか。臨床心理学者で「精神分析学派」という人がいるだろうか。精神分析家の私が精神医学実践をやることがあるように,精神分析家である心理臨床家も精神分析をやらないときに臨床心理学実践(心理臨床)をやることはあるだろう。そのとき精神分析家であることは,臨床心理学実践に確実に役立つだろう。しかし,だからといって,精神分析学派の臨床心理学者,精神分析派の心理臨床家というものが存在しうるのだろうか。そういうものがありうることが自明のことだと考えている人もいるようだ。しかし,それはそれほど自明なことではないのではないか,というのが私の考えである。
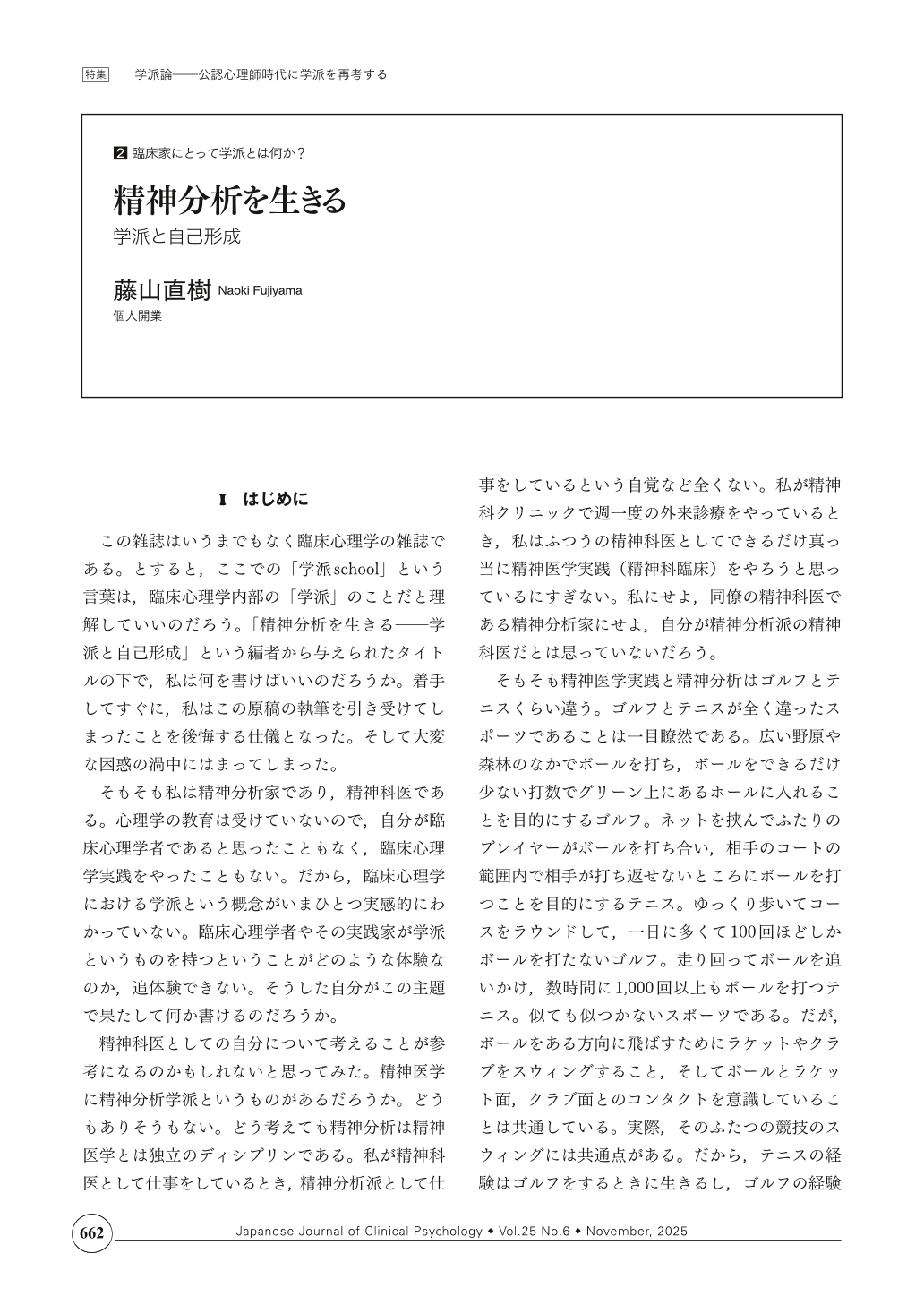
Copyright© 2025 Kongo Shuppan All rights reserved.


