- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
- 参考文献
I 開業はブームである!?
本稿の依頼文によると25年に及ぶ『臨床心理学』誌の歴史において,開業が特集のテーマとなるのは初めてだという。なるほど確かに,日本における開業は実に「捻じれた」存在である。これまでの歴史を振り返ってみれば,個室の「開業」臨床は心理臨床教育の中核的な場の設定でありながら,仕事としては「アウトサイダー」の地位に置かれていたことはその通りであろう。
一方,近年,この界隈においてにわかに「開業」は注目を集め,ブーム(?)となっているようにも見える。本誌でついに特集が組まれたというだけではなく,同じようなタイミングで「臨床心理iNEXT」でも関連する特集が組まれている(例:信田ほか(2025))。この春には第一著者が筆頭編著者となっている『こころを守る仕事をつくる―心理職の新たなキャリアと働き方の可能性』(末木・髙坂,2025)も出版された。また,最新の「第9回 臨床心理士の動向調査 報告書」(日本臨床心理士会,2024)によると(n=11,679),勤務領域として私設心理相談を選択した者は約11.5%おり,主たる勤務領域を私設心理相談とした者は4.7%存在している。これらの割合は,確かに,保健医療,福祉,教育といったボリュームゾーンを占める3領域に比すれば小さなものであるが,産業・組織・労働や司法・法務といった公認心理師の活動する主要5領域の2つよりも大きい(もちろん,主たる勤務領域が私設心理相談であることと,その相談施設を自らの手で「開業」したか否かは別のことではあるが)。そして何よりも,本特集の編者であり開業の第一人者でもある信田さよ子その人が,公認心理師職能団体の代表格のひとつである日本公認心理師協会のトップであることが,もはや「開業」が必ずしもアウトサイダーではないことを象徴している。
このような「開業」への注目がなぜ生じているのかは定かではない。分からないのでChatGPTに質問をしてみたところ,心理職の国家資格化による供給増で有資格者が大量に市場に流入していること,コロナ禍でメンタルヘルスケア需要が顕在化したこと,通信技術の発達(例:Zoom, SNS)による相談行動のハードルの低下/開業(宣伝)コスト・リスクの低下,あたりがブームの原因ではないか?などと品のいいことを言ってくる。性格の悪い私(第一著者)は,少子化による大学の待遇の悪化が力のある中堅・ベテランを開業に向かわせているのではないかと睨んでいるが(何せ大学は日本でも有数の斜陽産業であり,もはや教授の座は胡坐をかいて偉そうにしていられる「あがりポスト」には到底見えない),話の本筋ではないので,ここではとりあえず置いておこう。
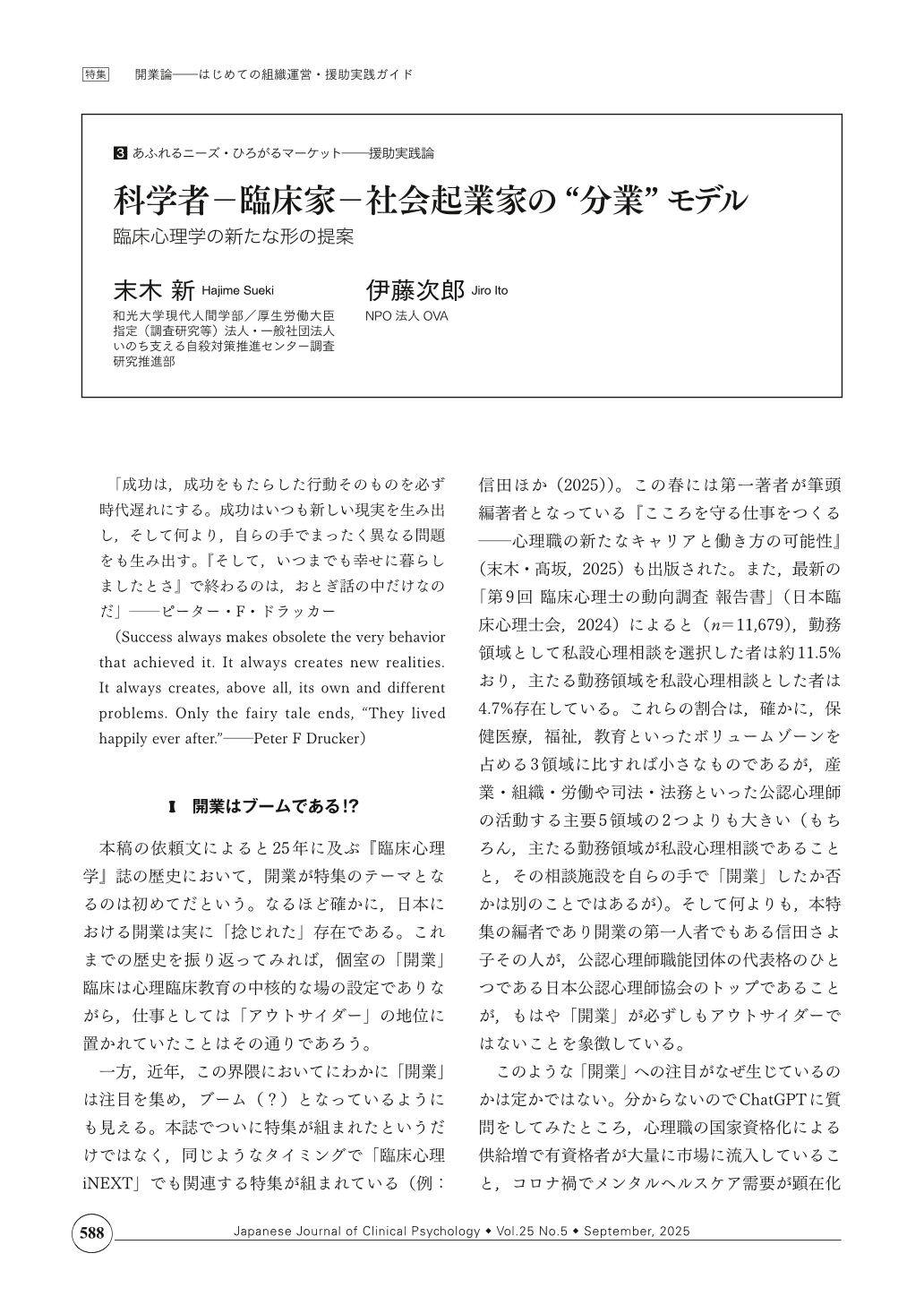
Copyright© 2025 Kongo Shuppan All rights reserved.


