- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
- 参考文献
I はじめに
「アディクションは,心理カウンセリングだけでは歯が立たない」という無力感とともに,アディクション臨床と出会った頃を思い出す。筆者が勤務する精神科クリニックには依存症の専門外来があり,20数年前にそこで初めて多くのアルコール依存症やさまざまなアディクションのケースと出会った。当時は主に心理カウンセリングを担当しており,「傾聴・共感・理解」といった基本をベースに信頼関係の構築につとめ,運よく多くのケースは命を落とすことも中断することもなく通ってきてくれた。しかしながら,アディクション症状としての飲酒は簡単には止まらず,薬の乱用や,過食,自傷もなかなかおさまらなかった。また,アディクションは身体,精神,生活,家族など多面的な関連問題を引き起こすため(樋口ほか,2018),支援者や家族が症状そのものをやめさせようとしても,本人の困りごとは「症状を止めたい」ではなかったりすることも少なくない。面接室の中だけではなかなか変わらないアディクション症状は,どのような支援や治療のアプローチで変わっていくのだろうか?
特に印象に残っているのは,「グループの力」によってもたらされる回復への変化である。勤務先のクリニックには大規模なアルコールデイケアがあり,集団療法を行っていた。「同じアルコールの問題を抱える他者の話を聴き,正直に自分の体験を語れること,それを安心して話せる場,聴いてくれる仲間の存在があること」は,孤立感を和らげ,本人の行動変容を促す大きな力となる。仲間とともに,飲酒によってもたらされた問題を見つめ,飲酒を伴わない考え方や行動を身につけていくプロセスは,医療者だけでは提供できないものがある。
また,多職種チームによる支援も有効であり,医師,看護師,精神保健福祉士らと連携することで,個別支援では難しい包括的な対応が可能となる。そのような多職種協働は,それ以前に勤務していた児童福祉や精神医療の現場で行っていた心理療法とは異なる部分が多く,学んできたこととの差異に多少の戸惑いもあった。しかし,本人たちがグループで語る姿や,実際に回復方向に舵を切り変化していく姿を見ていると,戸惑いよりも「人は変わっていくのだ」という感動の方が大きく,その変化と心情を話してくれる心理カウンセリングは,筆者にとって貴重な学びの場であった。さらに,「依存症の回復支援において,精神科医療はサポートの一面,すべての問題に対処できるわけではない」という言葉を先輩からかけられ,社会資源との連携も不可欠であることも学んだ。生活困窮や法的問題,家族支援など,関係機関との協働による包括的な支援が,アディクション臨床において重要であることを実感した。
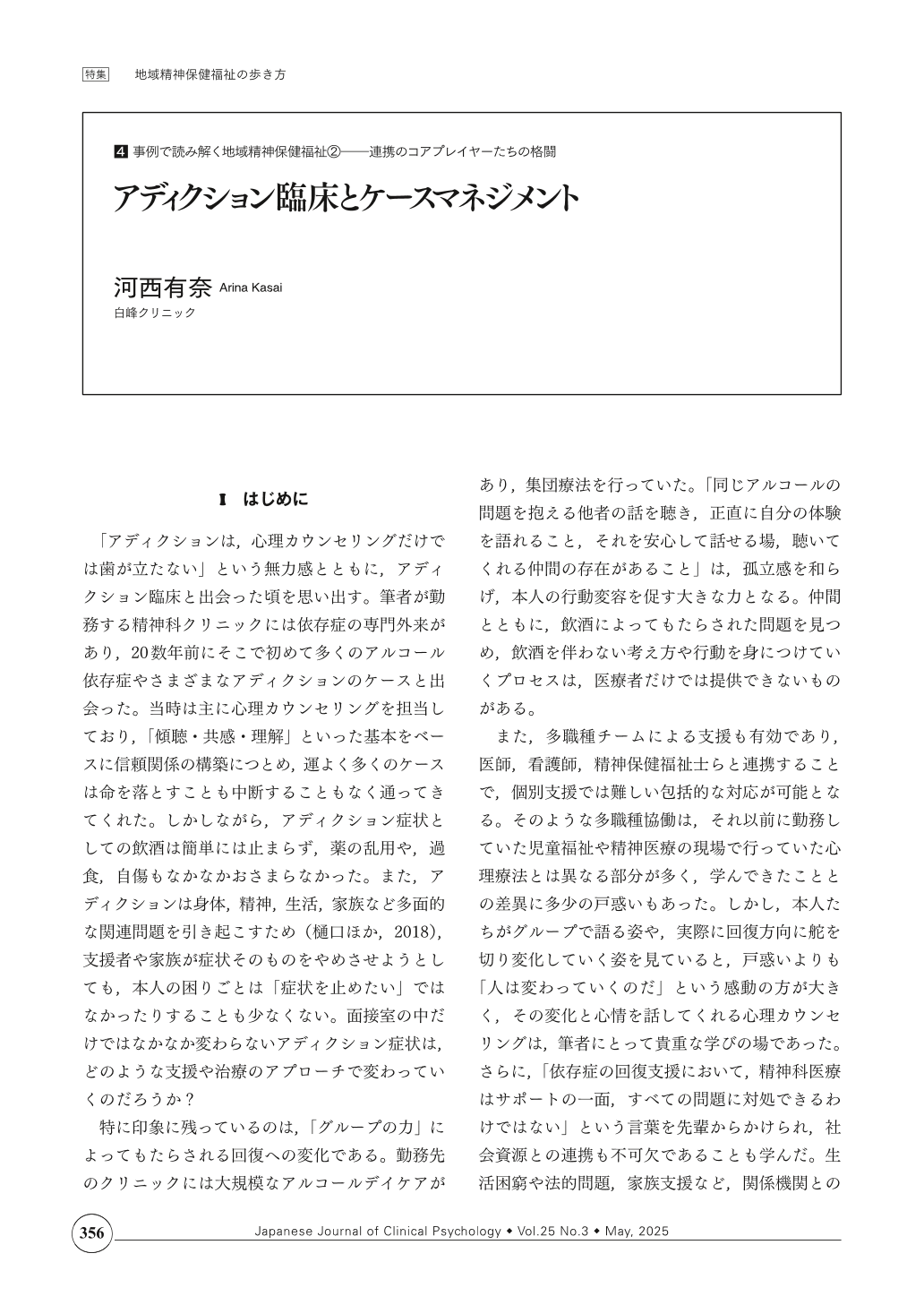
Copyright© 2025 Kongo Shuppan All rights reserved.


