特集 地域精神保健福祉の歩き方
発達障害支援―安心できる地域生活のためにできること
日戸 由刈
1
1相模女子大学人間社会学部
pp.336-339
発行日 2025年5月10日
Published Date 2025/5/10
DOI https://doi.org/10.69291/cp25030336
- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
- 参考文献
I はじめに
横浜市では,9つの地域療育センターがそれぞれ担当エリアの関係機関と緊密に連携し,発達障害の早期発見・早期療育システムを構築している。私もかつて,その1カ所である横浜市総合リハビリテーションセンター(YRC)発達支援部門に26年間勤務していた。療育センターはどこも多職種による診療部門(外来),療育部門(通園),相談部門で構成され,部門同士がつながりを持ちさまざまなチームプアプローチを展開している。チームリーダーは医師が担い,私が入職した1992年当時は佐々木正美先生,清水康夫先生,本田秀夫先生という年代の異なる素晴らしい常勤の発達精神科医がそろっていた。この先生方は海外の動向を踏まえYRCで最先端の取り組みを目指しており,後進の発達精神科医の育成とともに心理士の育成にも力を注いでくださった。
ただし,私は最初から心理士を目指していたわけではない。私には強度行動障害と最重度知的障害のある自閉症の兄がおり,1960年代から1980年代という自閉症に対する支援体制がほぼ何もなかった時代,兄も家族も日常生活に大きな困難を抱えて生活してきた。その経験から,私は大学院で障害児教育を専攻し,「自閉症の人が,地域の中で安心して生活できる」ことを考えてYRCに就職した。初年度は外来の児童指導員であったが,2年目,上司から「肢体不自由児の通園や外来で働く心理士が欠員になった。やってくれないか」と言われて心理士に転向した。この特異な経歴により,私は現在でも心理士としての専門性やアイデンティティが大して身についていない。しかし,ふり返ってみると,この弱みが多職種連携・地域支援における強みとなっていたのかもしれない。
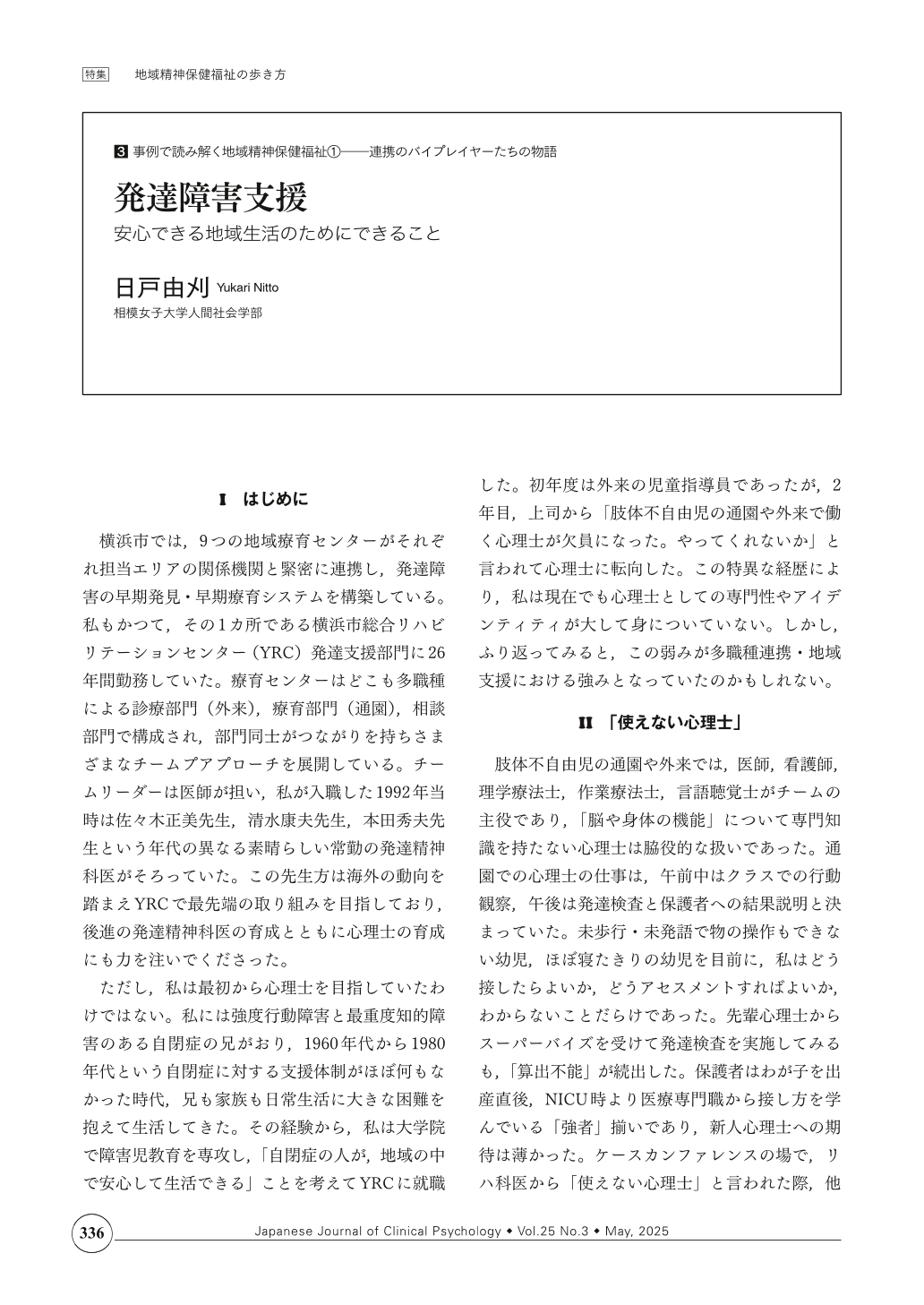
Copyright© 2025 Kongo Shuppan All rights reserved.


