- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
- 参考文献
I はじめに
地域精神保健医療福祉において,多職種が連携することは非常に重要である。精神科医や看護師,精神保健福祉士,精神科作業療法士,薬剤師,医療事務など,さまざまな専門家が協力し合いながら,患者やその家族が地域で安心して暮らせるよう支援している。そこに公認心理師や臨床心理士(以下,心理職)も加わり,チームの一員として活躍してきたが,近年はその重要性がさらに高まっていると感じる。
一方で,こうしたチーム医療において「心理的ケア」が十分に位置づけられ,さらに経営面でも持続可能な形で活用されているかというと,必ずしもそうではない。実際の現場では,「心理職を雇用する余裕がない」「診療報酬に直結しないためコスト面で厳しい」といった声が聞かれ,心理職の専門性が十分に活かされていない場面も少なくないのが現状である。
それでも,多くの診療所や病院,社会福祉法人などでは,心理職の専門性を活かして患者の支援の幅を広げようと,日々試行錯誤が続けられている。筆者自身も,地域に根差した精神科診療所を管理する立場として,心理職に大いに期待を寄せる一人である。ただし,現場を維持・発展させるためには,経営的・制度的なハードルが数多く存在する。それらを乗り越えるには「情熱」だけでなく,「エビデンス」に裏付けられた政策提言が必要だと強く感じている。また,心理職側にも「専門性を掲げるだけでなく,チームの一員としてどのように連携し,どう成果を示すか」を意識してもらいたいと考える。
本稿では,「チームにとけこむパートナー―チームリーダーの視点から」をキーワードに,心理職に対する管理者としての実感や問題意識を述べつつ,地域精神保健医療福祉の現場における心理職の役割,可能性,そして経営的持続性を確保するための課題について考察する。特に,筆者自身が日頃から感じている「心理職への期待」と「制度化が進みにくい現状のジレンマ」,さらに「データを取り,エビデンスを示すこと」の重要性に焦点を当て,議論を深めていきたい。
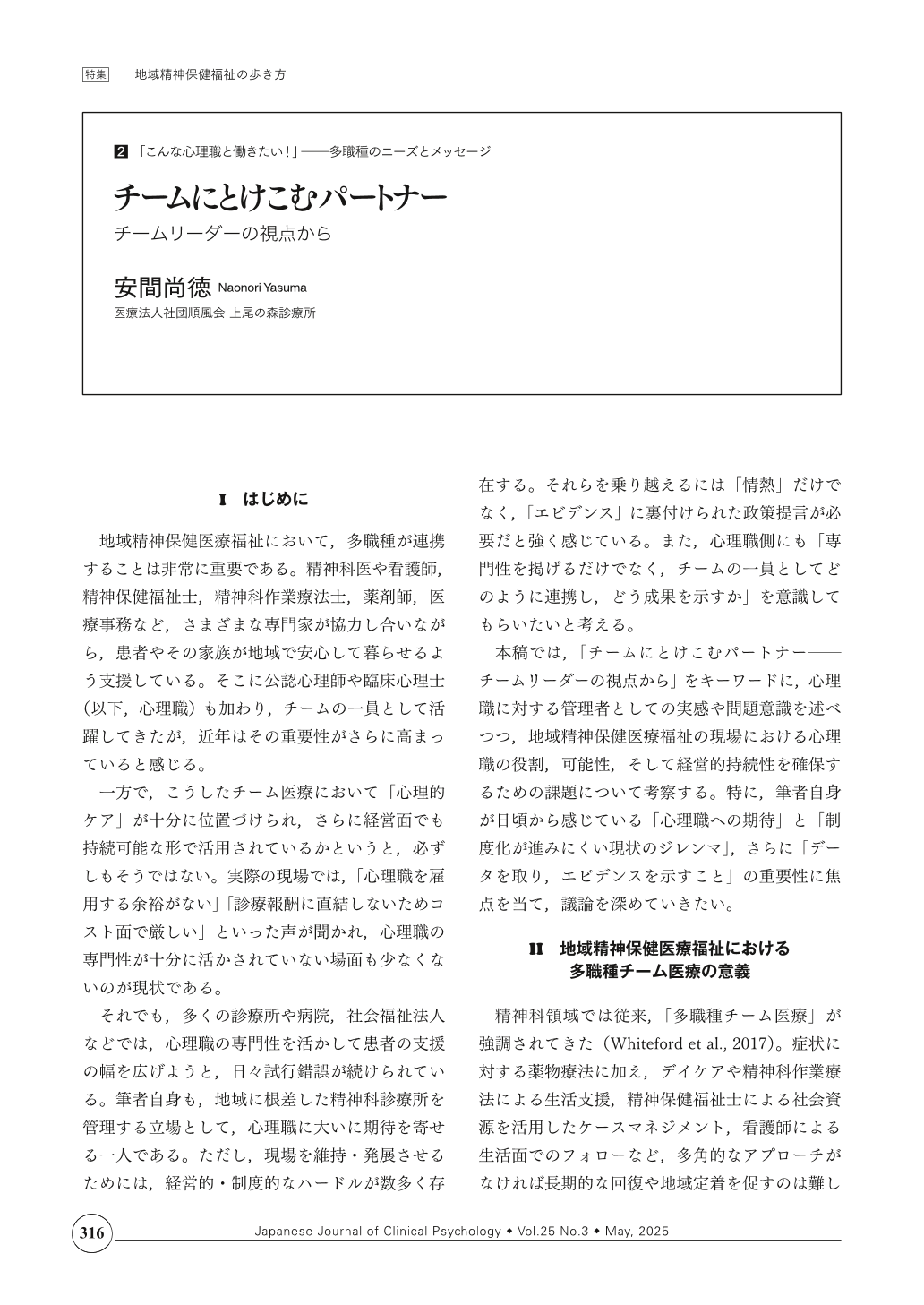
Copyright© 2025 Kongo Shuppan All rights reserved.


