- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
- 参考文献
I はじめに
私の心理臨床の仕事の出発点は,国立精神科単科病院の社会復帰病棟に10年以上入院している統合失調症をもつ人を対象とした,地域への退院促進のためのプログラム開発とその実施であった(Sato et al., 2012)。海外で効果ありと報告されていたプログラム(Liberman, 1995)を日本でも,医師,看護師,精神保健福祉士,作業療法士,心理職で構成される多職種チームで実施できるように改訂した。プログラムを運営していくなかで心理職以外の職種が患者さんの何に注目してアセスメントし,どのような治療,ケア,支援をしようと考えるのか,その思考の習慣のようなものを学ぶことになった。そこでは心理職にとってはなじみのある視点や評価法,支援があまり活用されておらず,心理職が自分たちができることをもっとアピールすれば患者さんにも他の職種にもメリットがあるのに……と思ったことを覚えている。こうした環境で仕事を続けるなかで,重症精神障害をもつ人を対象とした地域生活支援や就労支援に心理学的支援を入れ込むにはどうしたらいいかと考えるようになり,実践や臨床研究を行ってきた(佐藤,2019;Yamaguchi et al., 2017)。そしてこれらの取り組みを学会などで発信したが,心理職のコミュニティでは思うような関心を集めることはできなかった。
もちろんこれは筆者の力不足が大きく関係していたと思うが,発信の内容が「心理職が好むクライアントや支援」からずれていた,という理由もあったかもしれない。例えば,アメリカ心理学会が認定する臨床心理学の博士課程の責任者を対象とした調査によれば,多職種連携や地域支援が必須である重症精神障害をもつ人の支援に焦点を当てたコースがあるという回答は,全体の14%に過ぎなかった。そしてこの要因として,臨床心理士(Clinical psychologist)は「洞察力」や「治療への意欲」をもったクライアントを好むことが挙げられている(Reddy et al., 2010)。おそらく日本の公認心理師や臨床心理士が好む支援対象も似ているのではないかと思われる。他方,社会の喫緊の課題であるメンタルヘルスケアに関わる資格として公認心理師という国家資格が誕生した。だが,公認心理師が支援すべき対象のなかで「『洞察力』や『治療への意欲』をもったクライアント」はどれくらいの割合なのだろう?
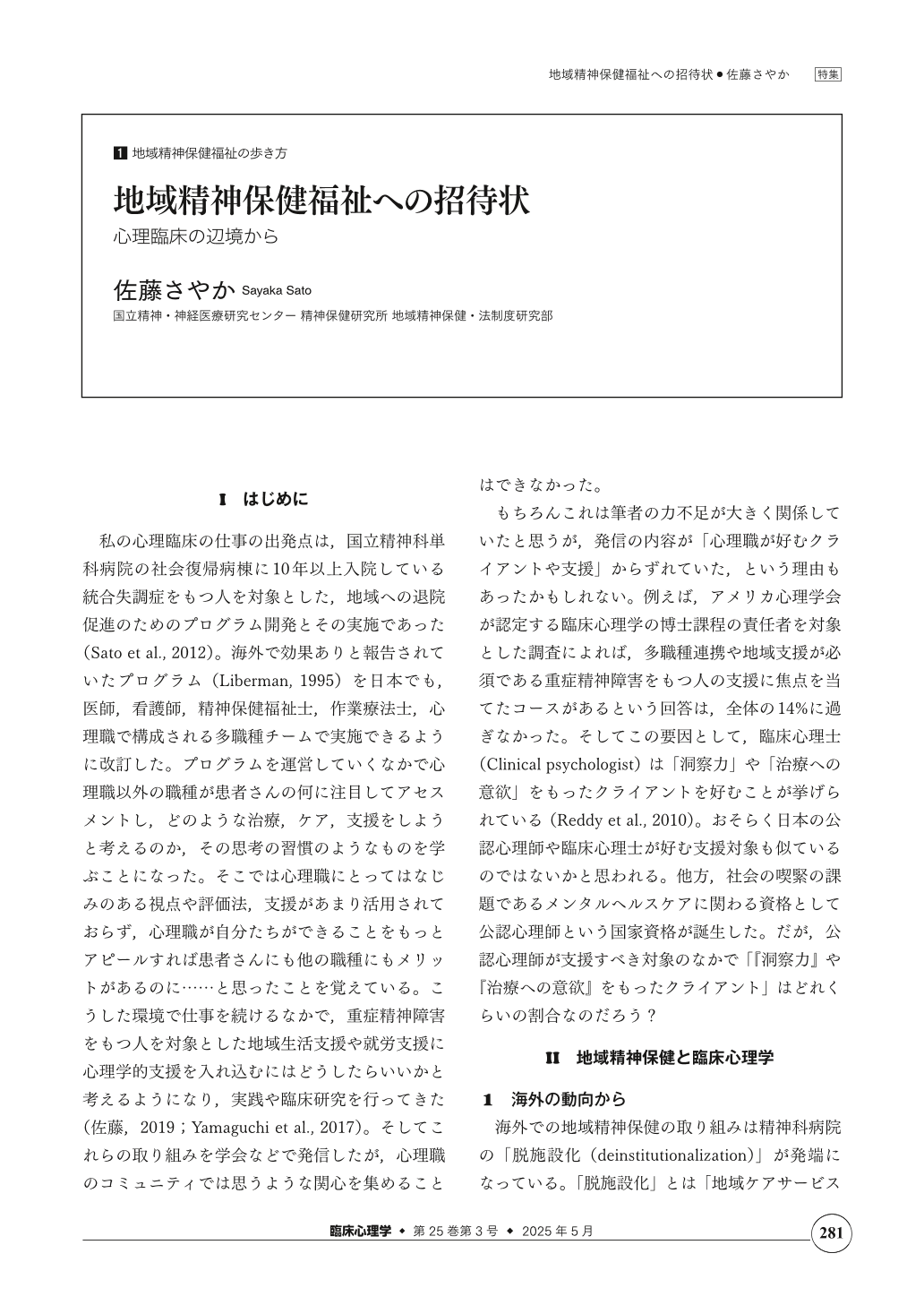
Copyright© 2025 Kongo Shuppan All rights reserved.


