- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
- 参考文献
Ⅰ 門番としての日常
常勤スクールカウンセラーの私の日常は,正門で生徒の登校を見守り,あいさつをすることから始まる。
私は,名古屋市にある,なごや子ども応援委員会という組織に所属し,市立中学校で常勤スクールカウンセラー(以下,常勤SC)として毎日働いている。正門での朝のあいさつは,平日週5日のうち1日は朝から出張があるため,週4日の実施。私だけでなく校長先生や生徒指導主事,係生徒たちと一緒に,毎朝登校する生徒の表情を眺め,「おはよう」と声をかけ続けている。もともとは「他の学校で働く常勤SCがしていたから/前任者がしていたから」という理由で始めた慣習的なもので,特に深い洞察があったわけではない。あいさつのために,勤務開始時間の8時15分より随分早く出勤する必要があり,「これにどれだけ意味があるのか……」と正直思っていた。
しかし,意味もわからず続けてきたなかで,生徒の些細な変化に気づくときがあった。例えば,「いつも複数人で登校しているのに,今日は1人で登校した」「いつもより遅い時間に来た」「その表情は何?」等々。そして,そういうことに気づいたときには,「あれ,今日は遅いね」「今日はどうしたの?」などと声をかけるようにしている。そのうちの多くは,「寝坊したんです……」とか「忘れ物を取りに帰って,走ったから疲れた……」といったその日限りの理由だが,なかには時々「朝,家族とけんかして……」とその場で泣き出す生徒がいたり,「友達とうまくいっていない」と話し始める生徒がいたりする。昇降口(名古屋では“土間”と呼ぶ)まで話を聴きながら一緒に歩き,「頑張ってよく来たね」とねぎらいつつ「行ってらっしゃい!」と送り出すと,ほとんどの場合は「行ってきまーす」と教室に入っていくことができる。そのあと朝の会が始まる前に,担任に「Aさん,今日の朝,家族とけんかしてきたみたいで」「最近Bさん,友達とうまくいっていないみたいで」などと伝えておくと,教室での様子を上手に見守ってもらうことができ,それだけでも多くの生徒は気持ちを落ち着かせられるようだ。
これらの大半は個別面接にまで至らないが,それでも常勤SCが子どもの「日常」の様子を知ることで,「異常と呼ぶほどでもないような些細な変化」に気づくことができ,ささやかではあるが,一次支援(予防開発)的・二次支援(早期発見対応)的なかかわりを増やすことができると実感している。そして個別面接に至る場合も,全く知らないSCではなく,「門に立っている南谷さん」と「あの話の続きをする」ということで,子どもたちの抵抗感はかなり低いように感じている。
常勤SCになって,これまで習ってこなかったけれど,仕事をするなかで「これは臨床的な意義があるのでは……」と感じるありふれた日常の瞬間が何度かあった。しかしその意義を上手に言語化できず,そんなとき東畑開人氏の『居るのはつらいよ』(東畑,2019)を読んで,「自分の言いたかったことはまさしくこれだ!」と膝を打ったのを覚えている(その後同い年だと知り,こんなおもしろい文章が書ける“タメ”がいるなんて!と正直ジェラシーに震えたりもした)。
本稿では,専門性をふんわり纏わせた「おはよう」の一言から始まる数十秒のやりとりに,どういった臨床的な意義があるのか,慣れないながらも書いてみようと思う。なお,組織の詳細や制度に関わる説明は,川岸ほか(2024)を参照していただき,常勤SCとは,かなり平たく言って「同一校に毎日勤務するスクールカウンセラー」だと思って読んでいただきたい。
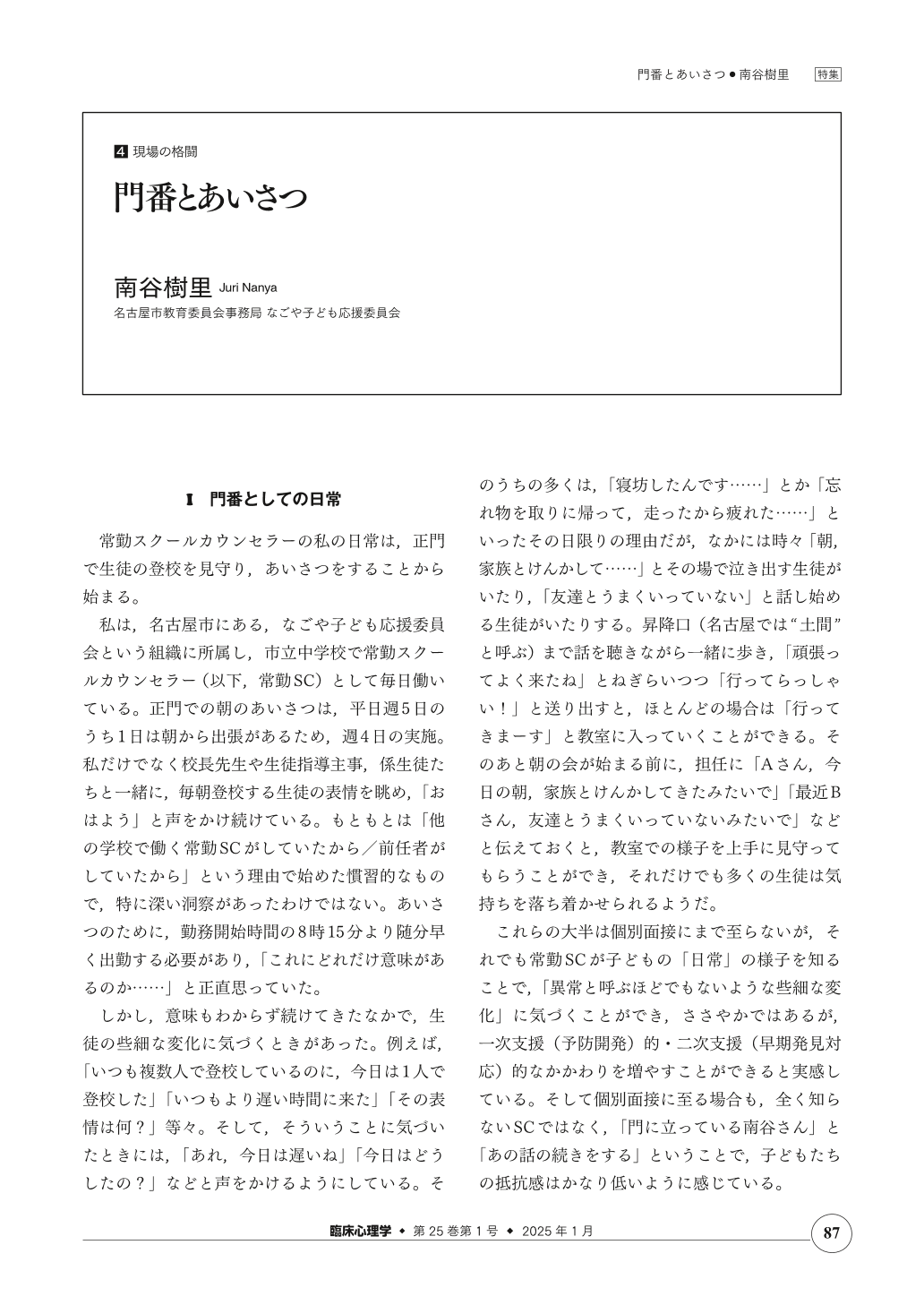
Copyright© 2025 Kongo Shuppan All rights reserved.


