- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
- 参考文献
I 自己啓発書が求められる社会的状況
筆者に与えられたテーマは「自己啓発」である。このテーマについて考えるにあたって,すでにいくつかのところで書いてきたことではあるのだが,自己啓発書が求められる状況についての社会学的理解を包括的に整理するところから始めたい。
近代以降の社会は,人・モノ・情報の流通が前近代よりぐっと激しくなることで,人々がそれまで有してきた規範や価値観を揺るがせることになった。たとえば,あるムラのなかで通用していたしきたりは,近代国家の法制や資本主義など,これまでとは比べものにならない広い文脈とつながることがらが入り込んでくるなかで修正を余儀なくされることになる。人々の日常的な規範や価値観,人生行路のモデルも同様に修正の対象となる。人生行路に関していえば,近代学校制度の開始は人々(かなり長い間男性のみ)に能力の発揮を通した立身出世という新たな可能性を夢見させた。伝統的共同体から脱出し,能力による立身出世を勝ち取ろうとするアスピレーションは,当時の書籍や雑誌における「成功」ブームと共振しながら増幅していった。前期近代における自己啓発の典型的モデルはこのような共同体からの立身出世的脱出・栄達にあるといえる(竹内,1997など)。
しかしながら,前期近代における共同体からの脱出先は,学校や企業,家族などのいわゆる中間集団にあった。より包括的には,戦後になって教育・仕事・家族をめぐる「日本型循環モデル」(本田,2014)が成立していくなかで,それぞれの中間集団ないしはサブシステムのインプットとアウトプットの相互関係が安定化し,そこに多くの人々が包摂されるに至った。だがこのような安定を支えた社会経済的状況が崩壊して各中間集団にもほころびが生じ,また社会の成熟に伴う規範や価値観の多様化(後期近代への移行)が進むなかで,人々はかつてなく流動化・不安定化した人生行路に中間集団の支えを以前ほど期待できないような状況で向き合わねばならなくなっている。より端的にいうと,人々は自らが何のために,またどのように生きていくのかを自ら決めていかねばならなくなっている。それを支援するツールの一つがまさに自己啓発書で,各種のセミナーやサービスと合わせて人々のセルフ・エンパワメントを支援・促進している。包括的にはこのように,今日において自己啓発書が求められる状況を整理することができる。
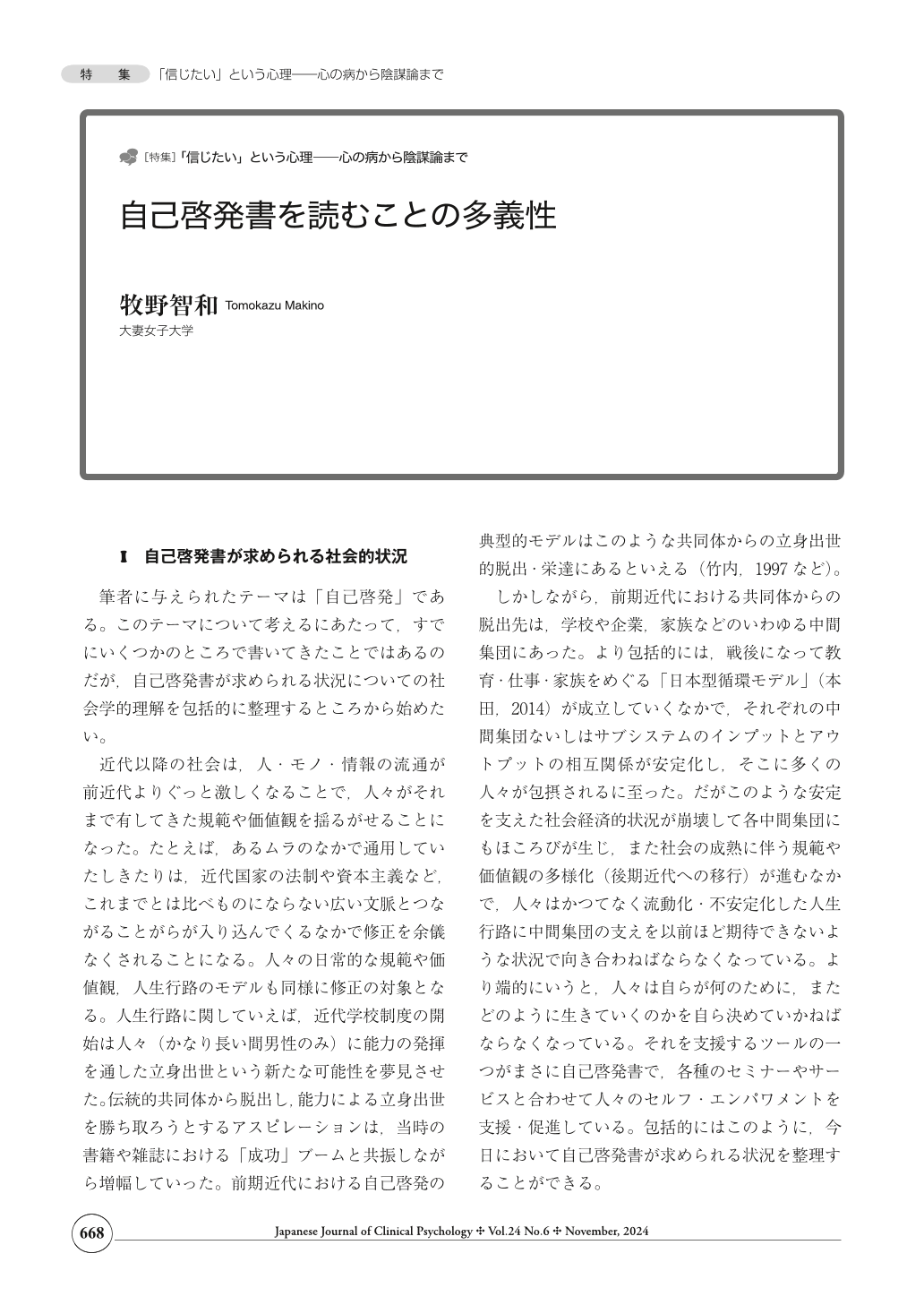
Copyright© 2024 Kongo Shuppan All rights reserved.


