特集 臨床的時間論―生きた時間の回復と治癒
ダイナミズムとシンクロニシティ―ひきこもりとデス・ドライブ(死の欲動)と精神分析
加藤 隆弘
1
1九州大学大学院 医学研究院 精神病態医学
pp.571-577
発行日 2024年9月10日
Published Date 2024/9/10
DOI https://doi.org/10.69291/cp24050571
- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
- 参考文献
I はじめに―精神分析家は時空間を取り扱う運転手?
村上春樹の短編小説「ドライブ・マイ・カー」に登場する家福は,妻を亡くした中年男性俳優である。妻の死後,彼の時間は止まり,残りの人生をどう生きるべきか絶望していた。視力障害で愛車の運転ができなくなった家福は,若い女性ドライバーのみさきに毎日劇場までの運転を頼んでいた。ある日,みさきの運転中,家福は昔話をした。家福は,妻の死後親しくなった若手男優の高槻の言葉を思い出したのだ。
筆者は,この小説を読み,この映画を観て,これらと精神分析臨床とのシンクロニシティを感じたのである。つまり,家福=「クライエント」(以下,患者),家福を劇場まで運転して運ぶみさき=「精神分析家」という構図である。そして,冒頭に記した高槻の言葉は,精神分析の営みそのもののようである。本稿では,「ドライブ・マイ・カー」により筆者が得た「精神分析家は時空間を取り扱う運転手なのでは?」という着想を元に,ひきこもりと「死の欲動(Freudが提唱した原始的欲動のひとつ:英語ではデス・ドライブ(Death Drive))」と精神分析のつながりを論じてみたい。
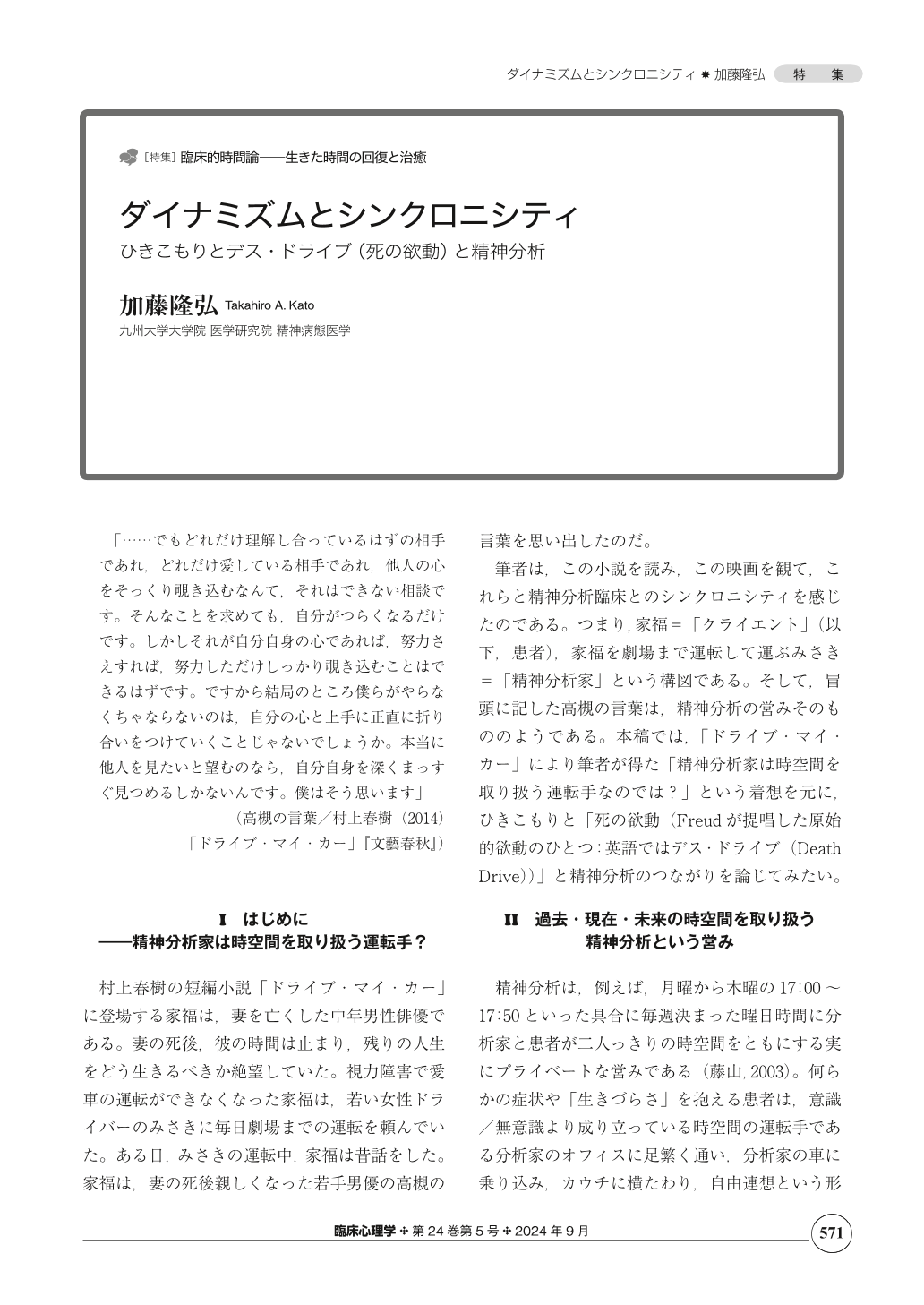
Copyright© 2024 Kongo Shuppan All rights reserved.


