- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
- 参考文献
はじめに
筆者が精神科医になりたてだった1980年代後半,日本精神分析学会の演題には境界性パーソナリティ障害の治療に関するものが多く,議論も活発だった。印象に残っているのは,当時,気のおけない研究室の仲間同士の会話の中で聞いた「米国の患者のように自動車の横転事故やアクロバティックな性行為などの激しい問題行動を繰り返すような人は日本では現実検討(現実感覚)が悪すぎるから,むしろ統合失調症を疑ったほうがいい」,あるいは,「同じような心の構造を持っている人は,日本では激しい問題行動よりも,ひきこもりとして事例化するのではないか」というような発言だった。つまり,社会とパーソナリティ病理の表現型との関係性についての議論だった。
境界性パーソナリティ障害という診断名は,1980年に刊行された米国精神医学会による精神疾患の診断・統計マニュアル第3版(通称DSM-Ⅲ)で初めて登場したが,その後の世界保健機構(WHO)による国際診断分類第10版(通称ICD-10)の編纂会議でも,社会とパーソナリティ病理の現れ方が議論されたという2)。すなわち,ヨーロッパの精神科医たちは「衝動的で激しい自己破壊的行動を繰り返す患者はほとんどいない」と主張して,ICD-10に境界性パーソナリティ障害の診断名を組み込むことに反対した。結局,それは情緒不安定性パーソナリティ障害の下位分類の「境界型」に位置付けられることになったが,それほど時を待たずして,ヨーロッパでも激しい行動化を繰り返すパーソナリティ障害患者が社会問題化するようになり,その治療研究に多額の予算が割り当てられるようになった。
ところが,最近になって,「大学病院には境界性パーソナリティ障害患者はほとんどいない」と言われるようになったと聞いて,正直,驚いた。というのは,現在,筆者は,精神科救急対応や入院治療をしていない総合病院の精神科外来で診療していて,予約の時点で,そのためのトリアージをさせてもらっているが,それでもなお,境界性パーソナリティ障害と診断できる患者は一定の割合で存在し,講演を頼まれて出かけた先では,相変わらず患者の激しい感情や問題行動に巻き込まれて苦労している家族や職場の人たちの嘆きをよく耳にするからである。
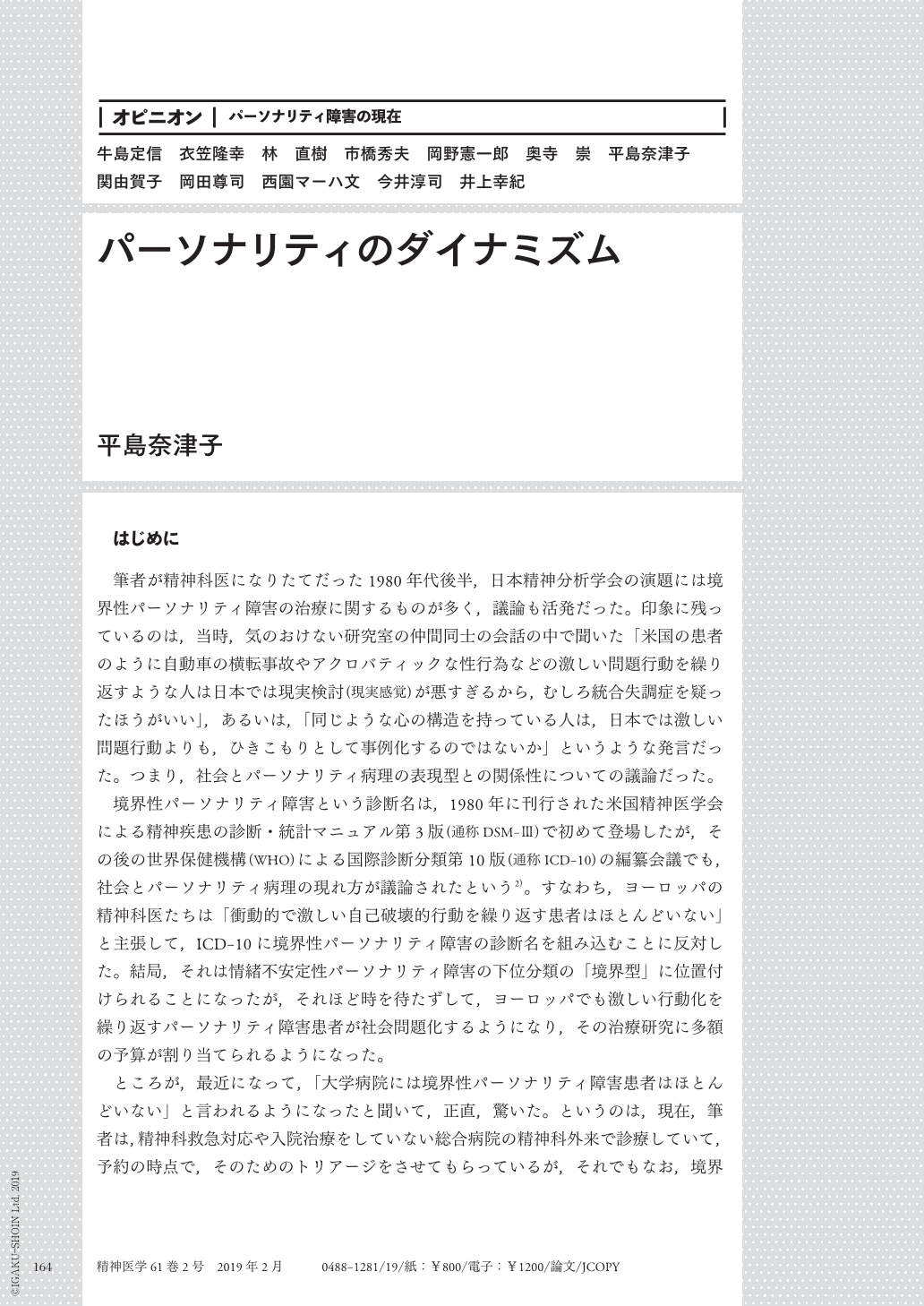
Copyright © 2019, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.


