- フリーアクセス
- 文献概要
- 1ページ目
更年期障害を構成する症状の種類は数十とも数百ともいわれる.これらは血管運動神経症状,精神神経症状,非特異的身体症状に大別されるが,それぞれの症状は相互に関連しあっており,また内分泌学的なゆらぎと多岐にわたる心理社会的ストレッサーの影響を受けて,長い病歴のなかでも様々に変化する.更年期障害の統一的な診断基準はなく,また「ゆらぐ」ことが本質である血清エストラジオールの単回測定も診断に寄与しないため,「月経が不順である40~60歳くらいの女性が,多種多様な身体精神症状を訴え,明らかな身体疾患の存在確率が現時点では低いと見積もられる場合に, “更年期障害” の診断のもとに外来で診療を行いつつ経過をみていく」というのが診療現場の実態である.難しいのは「多種多様な身体精神症状」と「存在確率が低いと見積もられる身体疾患」で,とりあえず「更年期障害」と考えて診療を行っていたが後から実は疾患Xの存在が明らかになった,という経験をお持ちの先生も,あるいはまた,その症状が更年期障害に由来するものであるかどうかはわからないが,軽度であれば専門医に紹介する前に自分で対応してみよう,と思われる先生もいらっしゃるであろう.もしかしたらそのような患者には「不定愁訴」というラベルを貼って早めに他診療科に回す,という先生もいらっしゃるかもしれない.本特集ではそのような問題意識から,更年期外来で遭遇することの多い症状を15種類採り上げ,各分野の専門家から,①症状の評価法(問診・身体所見・検査等),②鑑別診断,③プライマリ・ケアで可能な初期対応,④専門医への紹介のポイント等について,性差を念頭におきつつご解説いただいた.本特集が,いたずらに患者を抱え込むことなく,一方でせっかく意を決して来院された患者を門前払いしないような,そんな外来診療に役立てば幸いである.
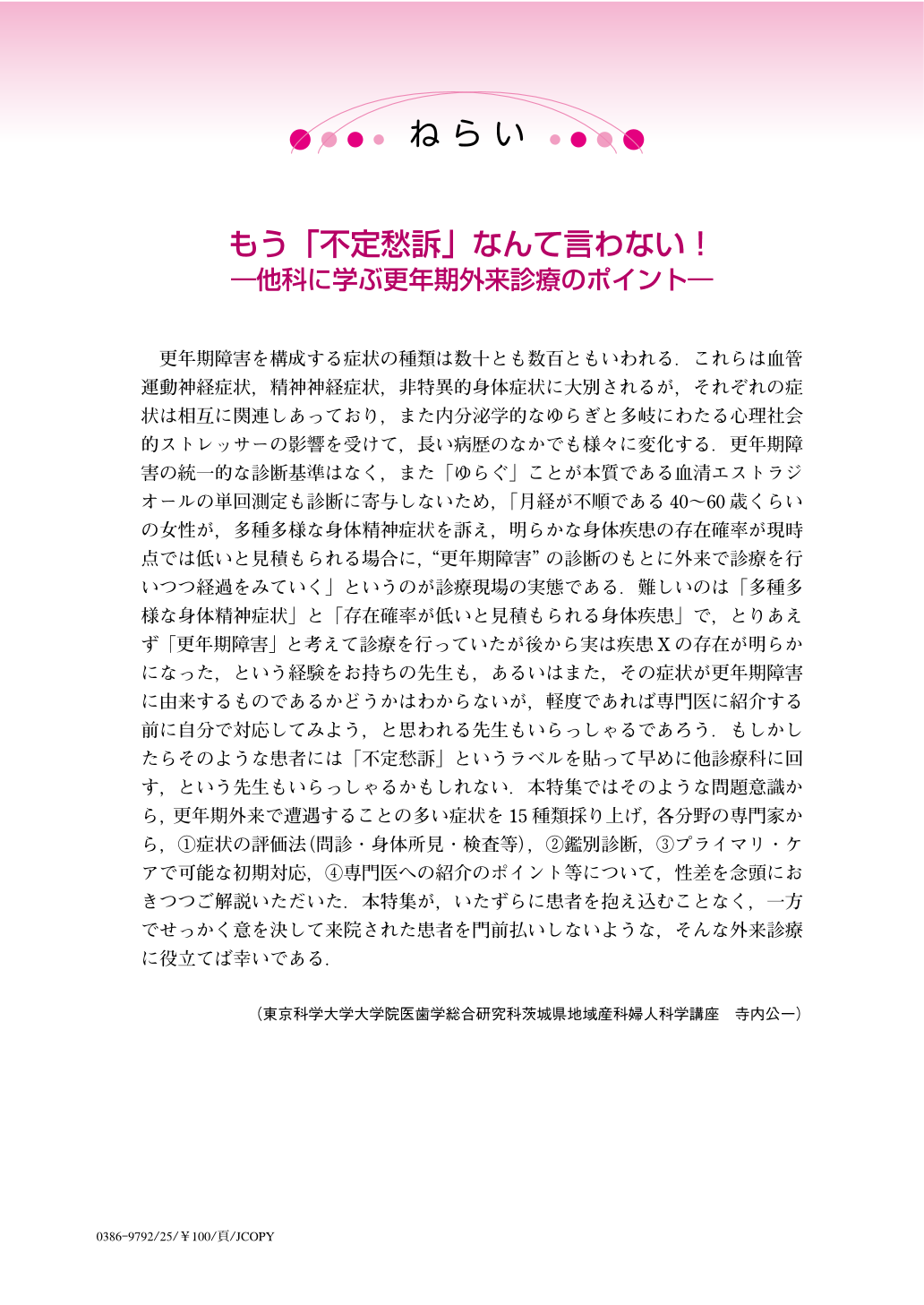
Copyright © 2025, SHINDAN TO CHIRYO SHA,Inc. all rights reserved.


