- フリーアクセス
- 文献概要
- 1ページ目
ホルモン補充療法(HRT)または閉経期ホルモン療法(MHT)は,現在女性医学・女性ヘルスケアとよばれる分野の黎明期から今日に至るまで常に関心の的であり続けており,またその評価はロウラーコウスターのように変転をくり返している.1960年代の “Feminine Forever”(by Robert Wilson)を合言葉とするHRTの勃興は女性の自己決定権確立と同期したムーヴメントであったが,1970年代にエストロジェン単独使用が子宮内膜増殖症・子宮体癌のリスク因子であることが明らかになると,HRTは大きな逆風に曝される.しかしながら黄体ホルモンを併用することによりリスクが非使用と同等になることが明らかにされ,HRTは1980年代に復活を遂げた.その後学界が大きくEBMに向かって舵を切ると,心血管疾患のHRTによる一次予防に関するエヴィデンスの確立が要求されるようになり,アメリカの国家的プロジェクトとしてのWHI研究が実施された.しかし2002年に第1報が発表されたWHI研究は,心血管疾患の一次予防不成功のみならずHRTの様々な負の側面を強調することとなり,HRTマインドは世界中で一挙に冷え込んだ.その後,血管運動神経症状の治療を目的としてなるべく少ない量・なるべく短い期間の使用なら許される,という制限つきでHRTの復権がはじまり,さらにMansonによって観察研究とRCTとのギャップを埋めるために提唱されたタイミング仮説が2016年のELITE研究によって証明されると,「閉経移行期に症状緩和目的で開始したHRTを継続することにより,閉経後の心血管疾患や脆弱性骨折のリスクを減らし,死亡率をも低下させることができる」,というHRTの一石二鳥的側面が再び世界的なコンセンサスを得るに至っている.日本女性医学学会が中心となって2009年に初版を発刊した「ホルモン補充療法ガイドライン」は,まさにHRTを翻弄するこの荒波をかいくぐりながら,2012年,2017年の改訂が進められてきた.爾来8年,さらなるエヴィデンスの蓄積や新たな製剤の発売という環境の変化に応じて改訂された2025年度版の作成にかかわられた専門家の先生方に,本特集のご解説をお願いした.改訂版とあわせ読み,行間を探る一助としていただければ幸いである.
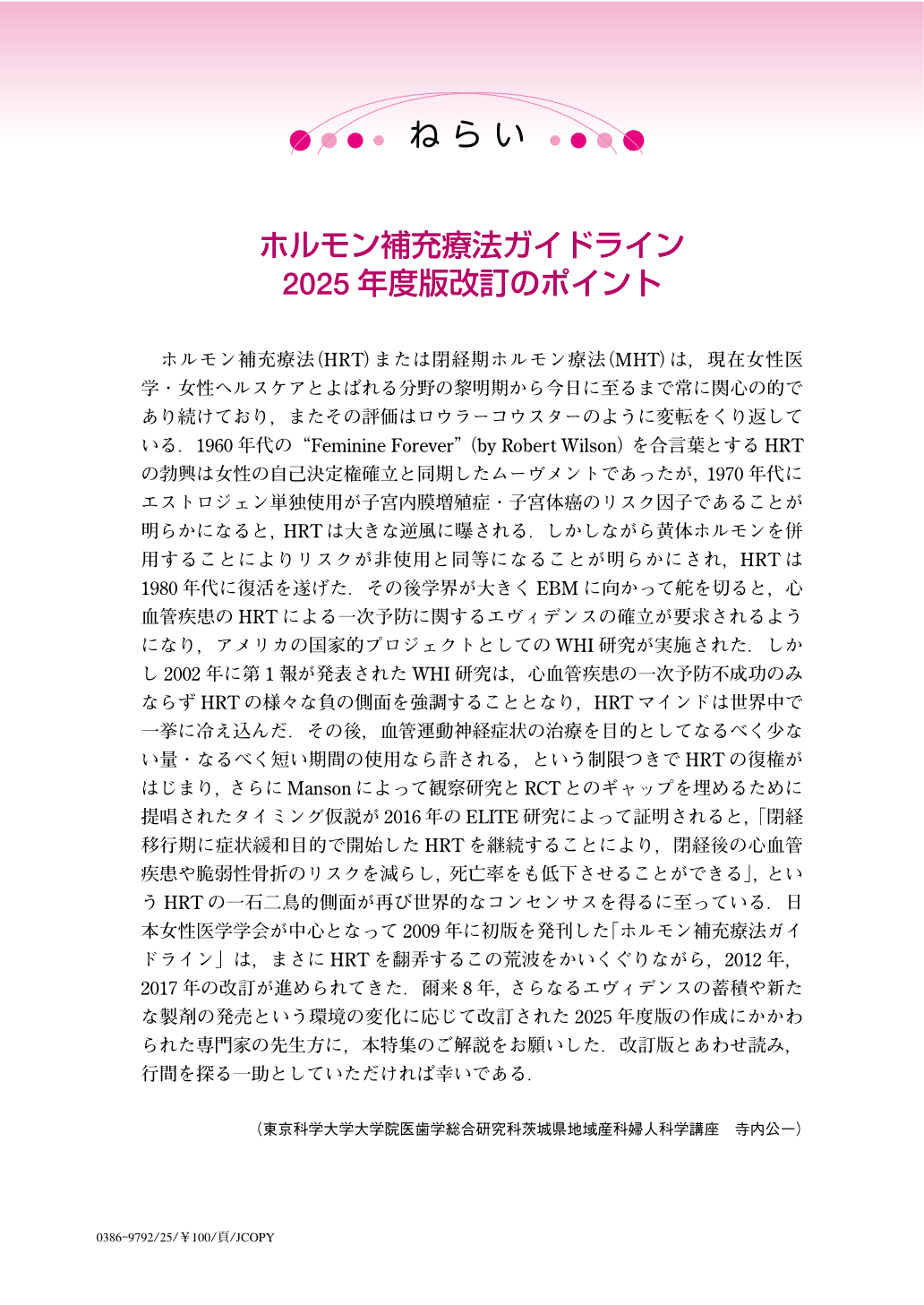
Copyright © 2025, SHINDAN TO CHIRYO SHA,Inc. all rights reserved.


