Japanese
English
特集 小児リハビリテーションの5W1H─超少子時代を迎えて
第3章 小児リハビリテーションの実践
小児リハビリテーション(学校作業療法)と遊び・学び ─ インクルージョンの実践
Pediatric Rehabilitation(Occupational Therapy for School)and Play & Learning:Practices of Inclusion
仲間 知穂
1
Chiho Nakama
1
1こどもセンターゆいまわる
キーワード:
小児リハビリテーション
,
学校作業療法
,
遊びと学び
,
インクルージョン
,
学校と家庭の協業
Keyword:
小児リハビリテーション
,
学校作業療法
,
遊びと学び
,
インクルージョン
,
学校と家庭の協業
pp.1408-1412
発行日 2025年11月25日
Published Date 2025/11/25
DOI https://doi.org/10.32118/cr034131408
- 有料閲覧
- Abstract 文献概要
- 1ページ目 Look Inside
- 参考文献 Reference
内容のポイント Q&A
Q1 Why? What? なぜ,小児リハビリテーション診療と遊び・学びを関連させる必要があるのか?
子どもは「育っていく」存在である.訓練と生活,機能と学びは本来切り離せず,作業を通じた実体験が自信と発達を促す.遊びや学びの場で「できた!」と子ども自身が感じる成功体験を積むことこそが,その子の生活の質向上および発達促進の鍵となる.
Q2 Who? どのような子どもを対象として取り組むのか?
対象は診断名がついた子どもだけでなく.日常生活において何らかの困難を抱えるすべての児である.本人も周囲の大人も"気づきにくい困難"に対しても支援を行っていくべきである.また子どもは環境の中で育っているからこそ,双方への働きかけが重要であり,その子がその環境の中で期待されていることや,やりたいことができるという関係性の中で「自分らしく育つ」ことを支援する.
Q3 When? Where? この取り組みはいつから,いつまで,どこで行うのが適切か?
支援は成長過程の中で違和感を覚えた時点で開始し,園,学校,家庭,地域を含むあらゆる場所で行う.支援の終了時期は「できるようになったとき」ではなく,作業バランスを維持しつつ,児と教員・保護者が協働して有意義な生活を営める状態に達した時点が望ましい.
Q4 How? 今後注目される手法や取り組みはあるか?
作業療法は,個人訓練に留まらず,「その人の生活環境での作業遂行の拡大」へと展開しつつある.保育所等訪問支援事業や地域委託事業等,保育園や学校への多様性を活かした学校作業療法により,インクルーシブ教育の実現,教育の質の向上が可能となる.
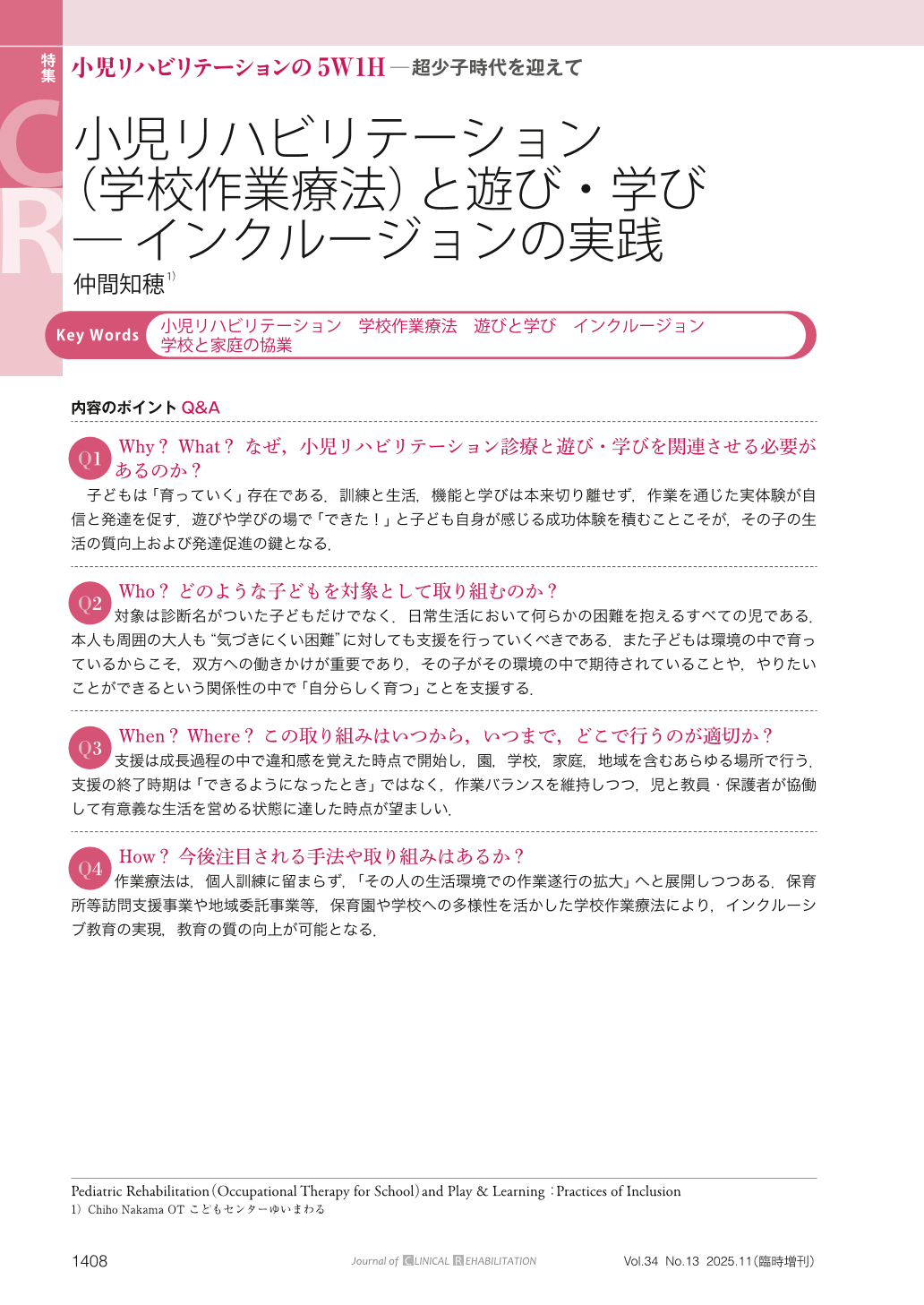
Copyright© 2025 Ishiyaku Pub,Inc. All rights reserved.


