Japanese
English
- 有料閲覧
- Abstract 文献概要
- 1ページ目 Look Inside
- 参考文献 Reference
内容のポイント Q&A
Q1 Why? What? 小児リハビリテーション診療における出口戦略が必要になる理由とは?
重篤な疾患で入院した小児は,脳が広範囲に損傷すると,慢性的な運動障害,嚥下障害,知的障害,てんかん等の後遺症が残存することがある.急性期のリハビリテーションを退院後の在宅や外来のリハビリテーションへ引き継ぐことが重要だが,リハビリテーションの課題が呼吸,嚥下,運動,言語と多岐にわたるうえに,移行後のスタッフや機器が大きく変わるため,引き継ぎが困難なことが多い.そのため,課題の引き継ぎ事項を整理しておく必要がある.
Q2 Who? どのような子どもを対象として取り組むか?
小児リハビリテーションの対象となる疾患は,新生児であれば重症新生児仮死(その後,脳性麻痺と診断されることが多い),新生児脳室内出血(超低出生体重児に多い),小児であれば急性脳症(インフルエンザ等高熱に伴うことが多い),急性硬膜下出血(事故か虐待によることが多い),脳梗塞・脳内出血(脳血管の先天的な異常によることが多い)等がある.
Q3 When? Where? このような取り組みは,いつからいつまで行うのか?
急性期治療中であっても,バイタルサインが徐々に安定してきた頃からリハビリテーション介入を始めたほうがよい.終了時期については,呼吸,嚥下,運動,言語の各分野において支援の必要がなくなったときといえるが,患者によっては明確な終了時期が存在しないこともある.小児は長い時間をかけて発達するため,6カ月でリハビリを終了させる,というわけにはいかないだろう.
Q4 How? 今後注目される手法や取り組みは?
呼吸理学療法においては,Electrical Impedance Tomography(EIT)を用いて肺内の空気像を可視化することで最も効果的な介入方法を探ることができる.言語療法においては,優秀なタブレット端末と視線入力装置を組み合わせた拡大・代替コミュニケーション(AAC)を構築することで,コミュニケーション訓練を実施することができる.作業療法においては,充実した遊びアプリで手先の動きを訓練することができる.今後,テクノロジーの発展によって新たなリハビリテーションのツールが開発されていくだろう.
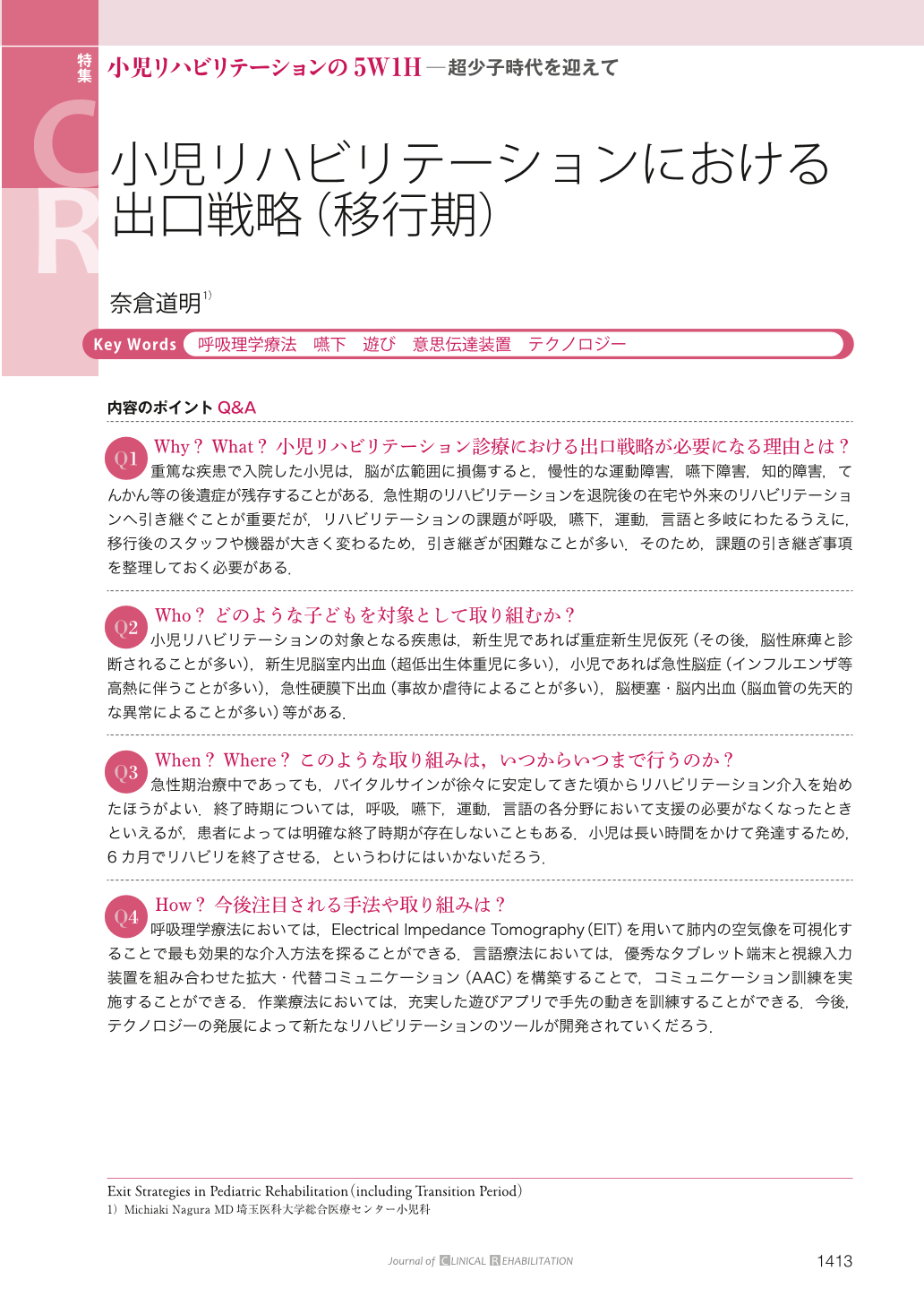
Copyright© 2025 Ishiyaku Pub,Inc. All rights reserved.


