Japanese
English
- 有料閲覧
- Abstract 文献概要
- 1ページ目 Look Inside
- 参考文献 Reference
内容のポイント Q&A
Q1 高齢者や脳障害者の運転特性は?
高齢者・脳障害者とも,運転特性については,身体機能と認知機能の両面から考える必要がある.高齢者では,下肢筋力の低下,瞬発力の低下,固有受容感覚の低下,関節可動域の低下,前頭前皮質の過負荷等によるペダル操作異常が起こり得る.脳障害者では,麻痺,痙縮,失調,感覚障害,不随意運動等により障害下肢のペダル操作に問題が生じるのみならず,非障害下肢のペダル操作も必ずしも安全ではないことを考慮に入れなければならない.
Q2 高齢者の運転適性の判断は?
高齢者の運転適性判断は,原則として免許センターでの適性検査を行う.70〜74歳は,高齢者講習(2時間)を,75歳以上の場合は認知機能検査(手掛かり再生,時間の見当識)と高齢者講習を受ける必要がある.認知機能検査は,その得点により「認知症のおそれがある方」「認知症のおそれがない方」の2段階に分けられ,前者の場合は臨時適性検査(専門医の診断)の受験,または医師の診断書が必要となる.
Q3 脳障害者の運転再開手順は?
脳障害者が運転再開をする場合,公安委員会より診断書を求められる場合が多い.医療者は診察,机上評価,実車評価等を経て運転に対する危険性を判断して診断書に記載することとなる.実車評価はgold standardといわれているが,そこに至る前の段階で,健康状態,認知機能,性格,環境の4点に考慮したうえで,最終的な運転再開に関する情報提供を行う必要がある.
Q4 必要な診察,机上検査とその判断は?
医療機関では,最低でも視力・視野,麻痺,失調,感覚障害,痙縮,不随意運動等をチェックし,可能であれば,運転シミュレーター検査を行う.机上評価としてはTrail Making TestやClinical Assessment for Attentionが実施されることが多い.日本高次脳機能学会(旧 日本高次脳機能障害学会)から提唱されている「脳卒中,脳外傷により高次脳機能障害が疑われる場合の自動車運転に関する神経心理学的検査法の適応と判断」は,現在多くの医療機関で使用されている.
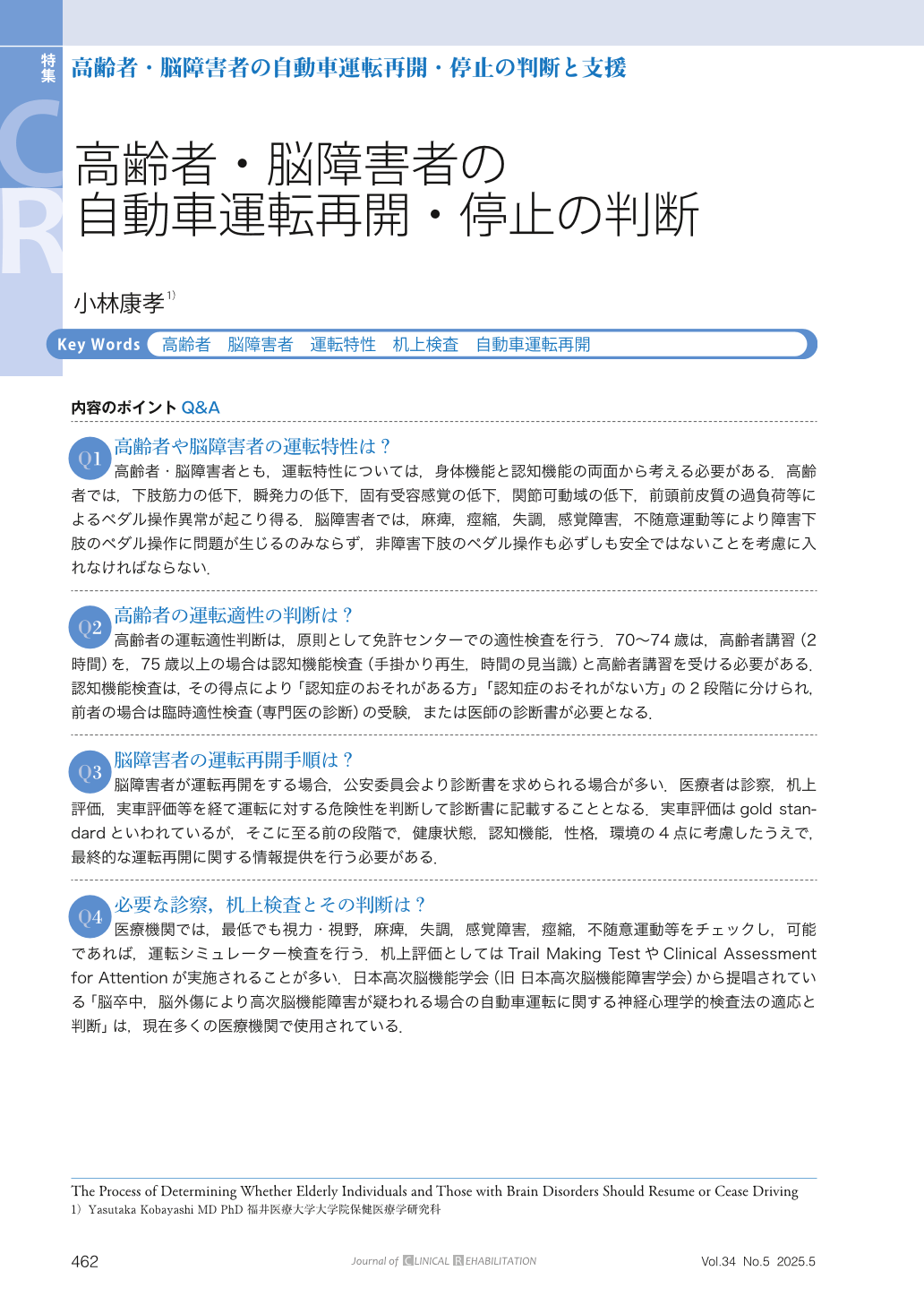
Copyright© 2025 Ishiyaku Pub,Inc. All rights reserved.


