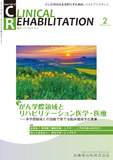- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
- 参考文献
はじめに
義足の足部(以下,足部)は,失われた人間の足(足関節を含む)の形態または機能を補い,日常生活動作においてさまざまな立位姿勢や歩行といった移乗・移動動作を代償する.その研究開発の歴史は,1957年にカリフォルニア大学でPTB(Pateller Tendon Bearing)式下腿義足と同時に開発されたSACH(Solid Ankle Cushion Heel)足部から始まり,生体工学観点から失われた足の機能を補うことを明確に示した 1).こうした研究が礎となり1980年代にはカーボン繊維を主材料とした板バネのエネルギー蓄積型足部(以下,エネルギー蓄積型足部)が開発され,現在では低活動の切断者から高活動のパラアスリートまで,幅広く用いられるよう設計がなされている.
また,足部の機能には生活様式や履物文化にも適応することが求められる.欧米のように屋内でも靴を装着する文化では,その機能はあまり重要視されてこなかった.しかし日本の和式生活では日常履物の脱ぎ履きは常であり,足部にはこうした生活様式に合わせて履物のヒールの高さに義足の差高が調整できる機能が求められた.このような要望を受け,今仙技術研究所はLAPOCシステムの中で,世界に先駆けて履物のヒールの高さと座敷で差高が調整できる2段階の差高調整型足部を開発した.その後,女性の社会進出に伴い女性切断者の中にもヒールの高い靴を履く人が増え,欧米のメーカーはエネルギー蓄積型足部に差高調整機能を組み込んだ足部(以下,差高調整エネルギー蓄積型足部)を開発するようになった.最近では男性切断者の中にも多様性に応じてヒールの高い靴を履くようになってきており,需要が広がりつつある.
そこで本稿では,まず人間の足の機能と代償する足部の構造を解説し,次に最近改良が加えられ注目を浴びつつある差高調整エネルギー蓄積型足部のプロフレックスLPアライン(Össur社製)とタレオ アジャスト(Ottobock社製)について解説する.
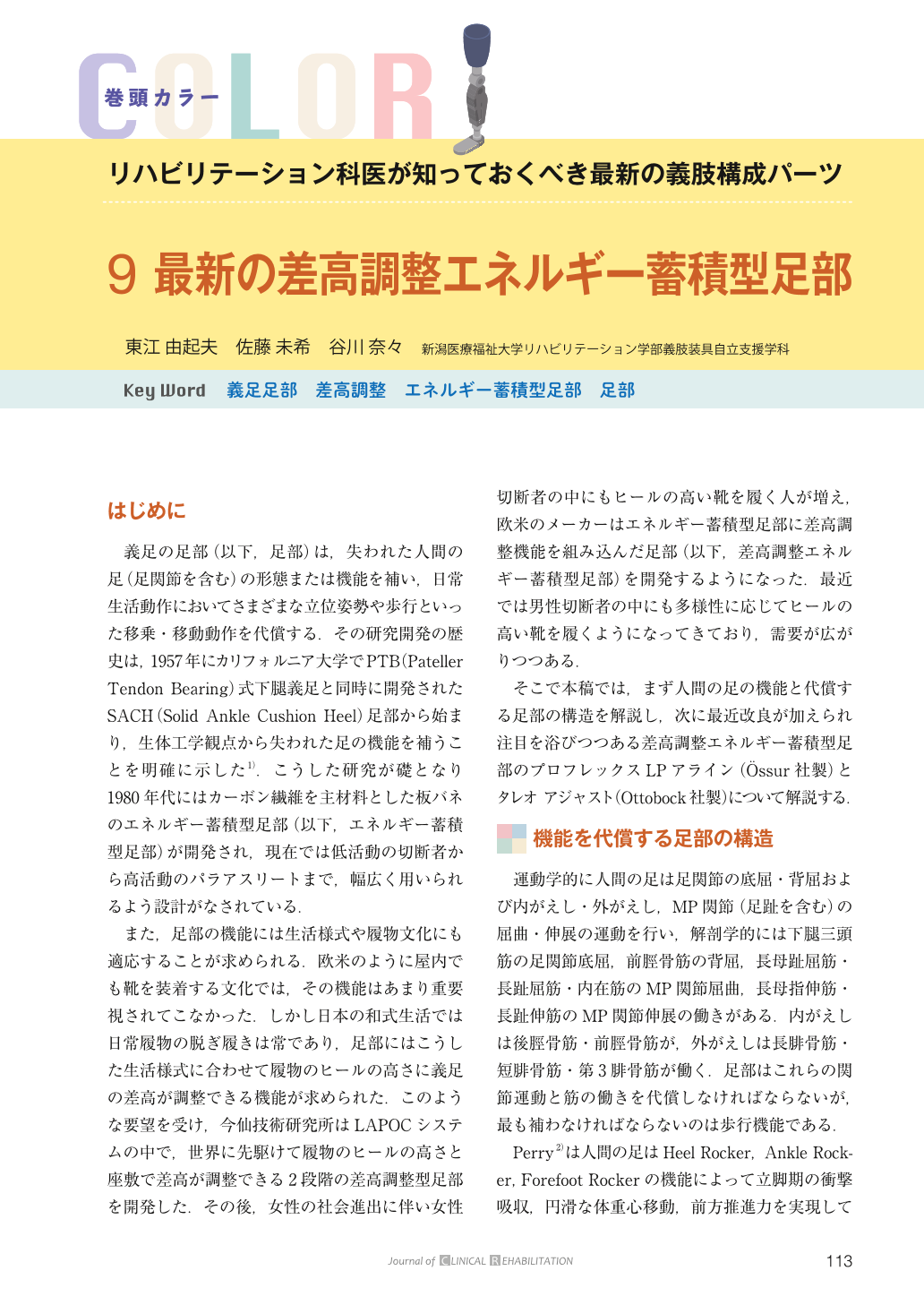
Copyright© 2025 Ishiyaku Pub,Inc. All rights reserved.