- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
- 参考文献
Case 集中治療の過程で人工栄養を開始したが,多発脳梗塞で寝たきりとなったケース
患者Aは80代前半の女性で,大学生の孫2名を含む長男夫婦家族と同居していた.Aの認知機能は保たれており,5年前にラクナ脳梗塞を指摘された既往はあるものの,一切の介助等なく日常生活を送っていた.Aの夫は数年前に肺炎で亡くなっていた.近所には70代の妹が生活しており姉妹仲はよかった.
ある日,Aは特に思い当たる原因がなく発熱し,体調を崩した.経口摂取が低下し,ぐったりして,数日後にはふらついて歩行もできなくなった.さらには傾眠傾向が出現したため,近くの病院に緊急入院した.検査の結果,腎盂腎炎および敗血症状態にあることが判明した.当初の抗生物質治療への反応が悪く,意識障害が悪化し循環動態が不安定になったため,集中治療室での1カ月にわたる治療が行われた.経口摂取ができないため,経鼻チューブによる水分・栄養補給が行われていた.その後,感染症はコントロールされたが,集中治療中に両大脳半球に深刻な多発性脳梗塞を起こして,寝たきり状態になってしまった.
経口摂取ができないため,一般病棟に移ってから胃瘻が造設された.このときには胃瘻中止については話し合わなかった.Aは発語なく,コミュニケーションはほとんどとれず全介助状態で,意識状態の改善なく半年以上が過ぎた.開眼し覚醒睡眠周期はあるものの,家族やケア担当者を含め,外界にほとんど反応しなかった.しかし,まれに動くものを追視することや視覚固定があった.発声はあるが,家族が理解できる発語はないと思われた.他者の指示に従った行動や合目的な動きはほとんどなかったが,まれに質問に反応することがあった.この半年間,意識状態を含めたAの状態に改善の兆しはなかった.
Aは事前指示を記載しておらず,意識障害に陥る前に表明された医療に対する希望を知る他の手がかりもなかった.アドバンス・ケア・プラニング(ACP)も行われていなかった.
ある日,Aの長男がふと思い出したように,「人工栄養というものは中止することができるのか」と担当医に尋ねた.最近,Aの親族のなかで,現在の胃瘻による人工栄養投与についていろいろな意見が出ているという.数人の親族は人工栄養投与に否定的態度である一方,他の親族たちは人工栄養継続に前向きだった.担当医から臨床倫理コンサルテーションチームに,「Aさんの家族にどのように回答したらよいか」と問い合わせがきた.同チームはどのように対応したらよいだろうか.
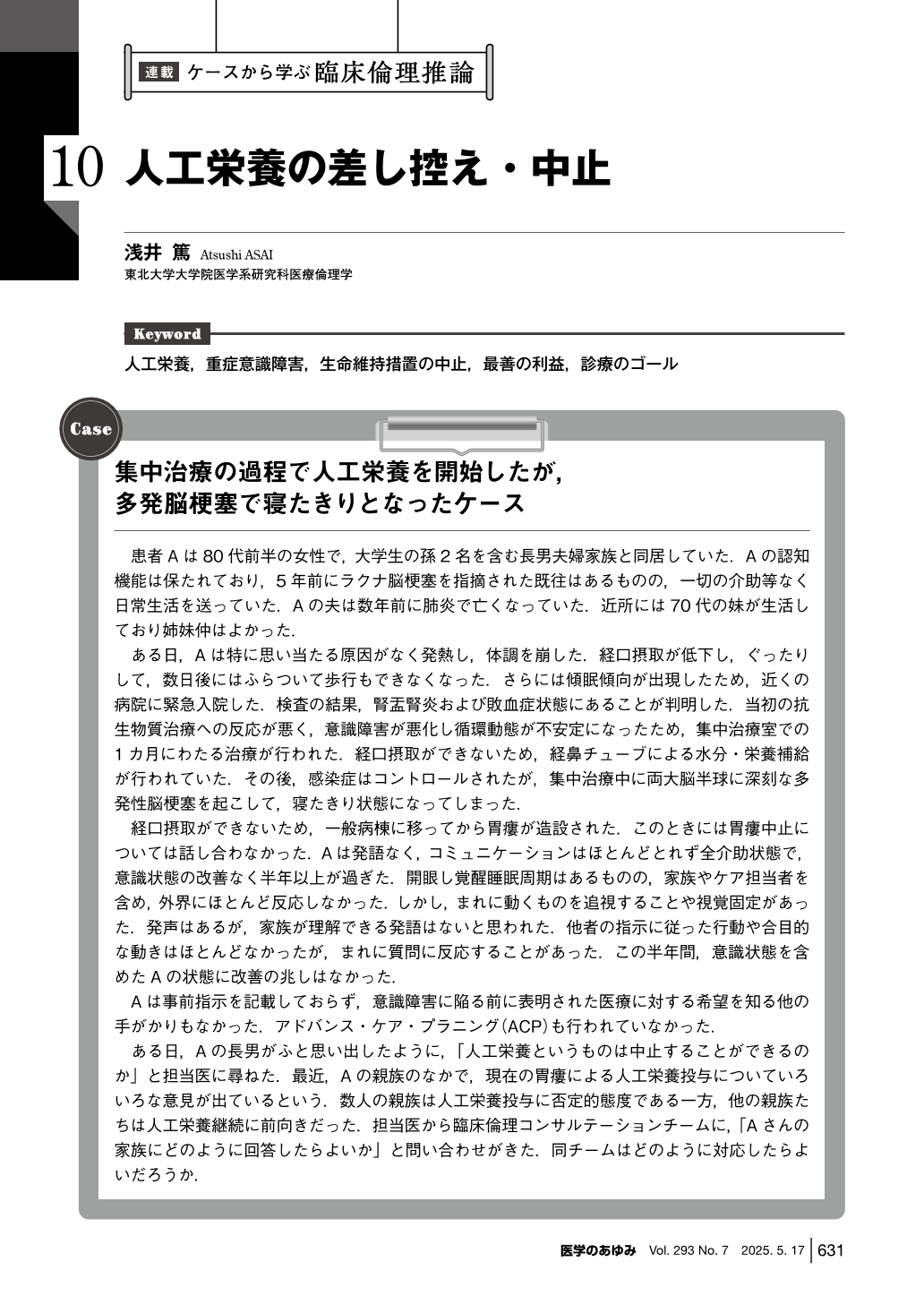
Copyright © 2025 Ishiyaku Pub,Inc. All Rights Reserved.


