特集 周産期救急システム―初期対応と災害対策
母体救急発症時の対応 羊水塞栓症の初期対応
東堂 祐介
1
,
小田 智昭
1
,
伊東 宏晃
1
TODO Yusuke
1
,
ODA Tomoaki
1
,
ITOH Hiroaki
1
1浜松医科大学産婦人科
pp.688-692
発行日 2025年6月10日
Published Date 2025/6/10
DOI https://doi.org/10.24479/peri.0000002176
- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
- 参考文献
羊水塞栓症の病因・病態
羊水塞栓症は,従来,羊水・胎児成分が母体に流入し,肺血管に塞栓することで発症すると考えられていたが,現在では肥満細胞や補体系の関与したアナフィラクトイド反応が主病態とされている。これはアナフィラキシーとはIgEが関与しないという点で異なり,肥満細胞が補体系の産物であるC5aなどにより直接活性化され,脱顆粒によりヒスタミンやトリプターゼ,ロイコトリエン,プロスタグランジンなどが分泌される。主に肺と子宮でアナフィラクトイド反応が観察でき,これが呼吸循環不全や子宮弛緩を惹起していると考えられる(図1)。血液凝固障害の原因については,消費性凝固障害だけでなく発症初期から線溶亢進もきたし1),著明なフィブリノゲン値低下,プロトロンビン時間延長,FDP・Dダイマー上昇が特徴的である。同じ産科DIC(播種性血管内凝固)を引き起こす常位胎盤早期剝離症例では,トロンビン量を表すプロトロンビンフラグメント1+2(PF1+2)とプラスミン量を表すプラスミンα-2プラスミンインヒビター(PIC)との間に正の相関を認めたが,羊水塞栓症症例ではPF1+2に相関しないPICの上昇を認めた。羊水塞栓症ではtPAが高値であった一方で,線溶抑制因子であるトロンビン活性化線溶阻害因子(TAFI)が低値であった(図2)。これらの因子が羊水塞栓症の特異的な線溶活性化に関連すると考えられている2)。
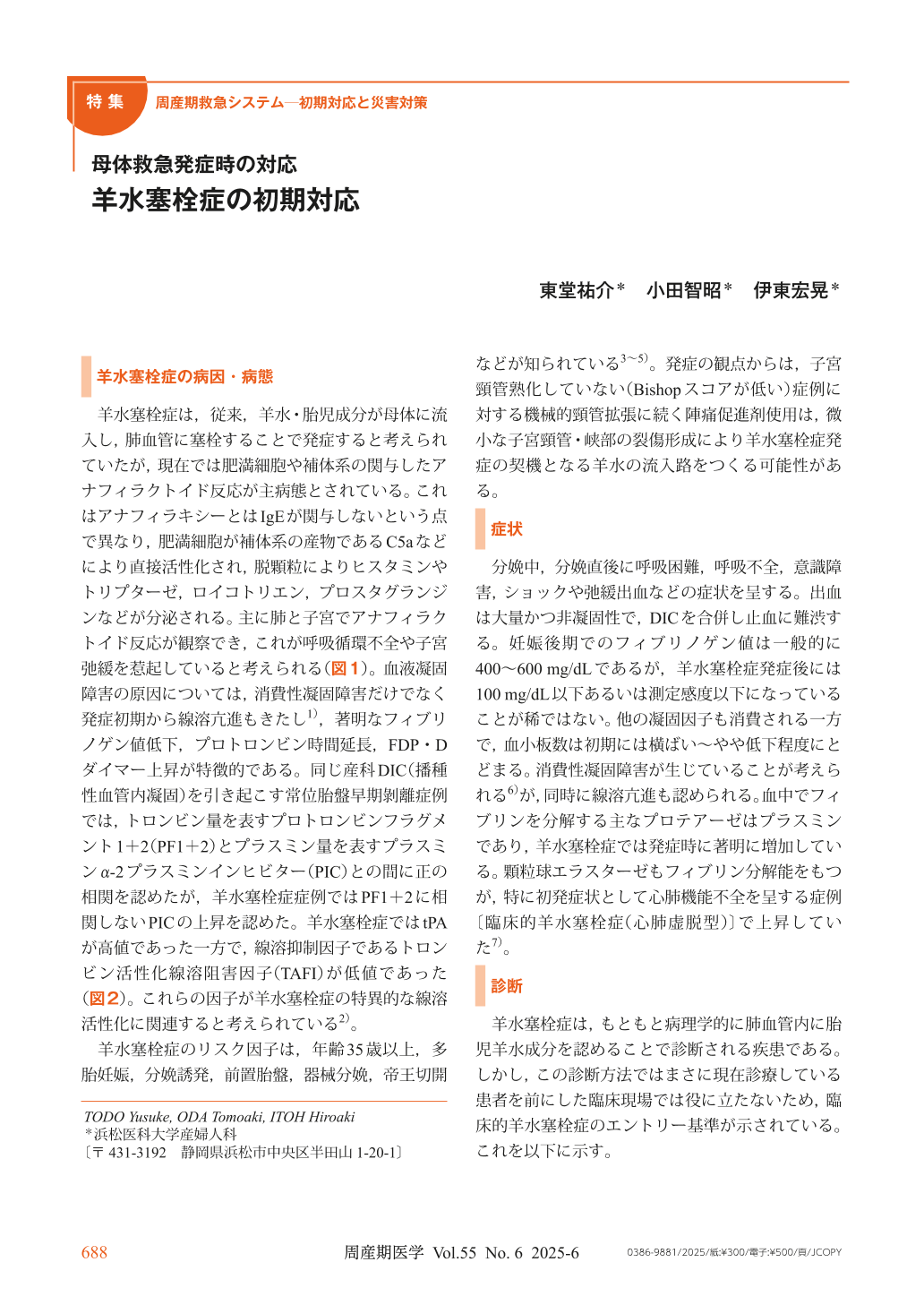
© tokyo-igakusha.co.jp. All right reserved.


