Japanese
English
- 有料閲覧
- Abstract 文献概要
- 1ページ目 Look Inside
- 参考文献 Reference
は じ め に
わが国は超高齢社会に突入しており,近年高齢者を含む世帯は夫婦のみ,もしくは単独世帯といった構成が増加している1).自立した生活を送るためには,年を重ねても人の手を借りずに自力で移動できる身体機能を保つことが必要である.しかし『平成28年国民生活基礎調査』では要支援,要介護にいたった原因は関節疾患に骨折,転倒を含めると22.1%が運動器由来のもので占められ2),移動機能の低下がただちに介護問題を引き起こす結果になりうることは明白である.年を重ねても可能な限り自分の足で歩き続け,介護を必要としない自立した生活を送るためには比較的若い世代からの運動器への対策と予防が必要である.ロコモティブシンドローム(ロコモ)の中心となる移動機能(歩行機能)の低下は年齢そのものによる経年的な体力的要因と運動器に代表される骨,関節軟骨,筋,末梢神経の器質的な要因で起こりうる.加齢に伴う運動能力の個人差は生活の多様性からみても大きく,歩行機能の低下は日常生活活動範囲の狭小化につながる.昨今,問題となっている高齢者の引きこもりの一要因としても考えられ,さらに活動量が低下するという負のスパイラルに陥る可能性が高くなる.
歩行機能のなかでも顕著に認められる速度の低下は,50歳以降から徐々に始まり,急激な低下がみられるのは男女ともに62歳ごろである3)といわれている.われわれは地域在住高齢者を対象にロコモの啓発活動の一環として運動教室を年に数回開催している.本稿では,ロコモ度テストのなかでパフォーマンステストに位置づけされている立ち上がりテストと2ステップテストでロコモ度を判定した.ロコモ度1,2の該当者を対象にステッピング訓練を行い,歩行機能の改善と2ステップテストの距離の延長,またロコモ度による訓練介入効果の推移を認めたので報告する.
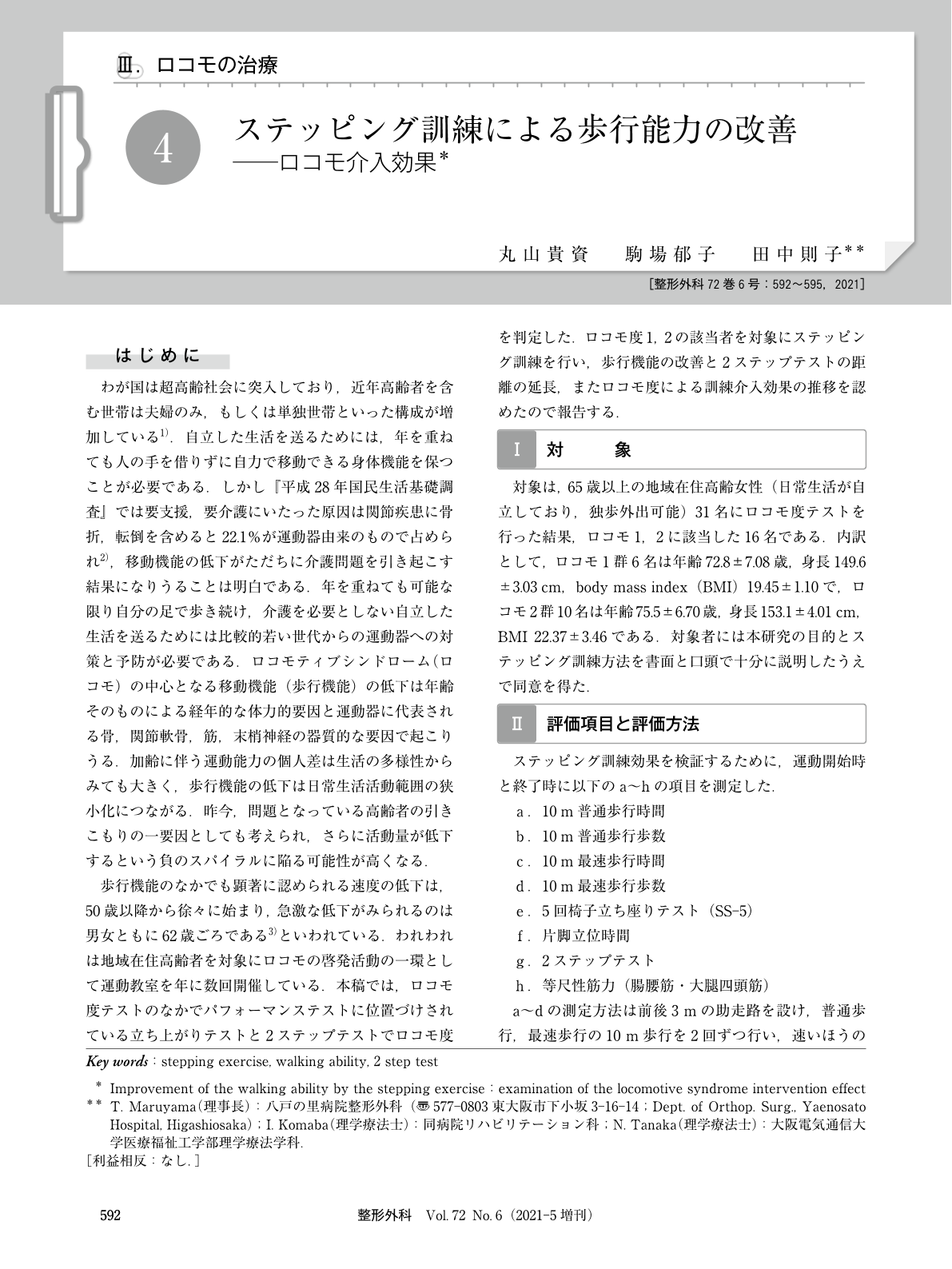
© Nankodo Co., Ltd., 2021


