特集 ある看護チームの挑戦―『脳治療革命の朝』の現場から
医師としてなぜこの職場を選んだのか,そして何を学んだのか
雅楽川 聰
1
1日本大学医学部附属板橋病院救命救急センター・救急医学教室
pp.634-638
発行日 2000年8月10日
Published Date 2000/8/10
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1686901996
- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
"チーム"への入団
運命の日
私が,林成之先生(現救急医学教室主任教授)に初めてお会いしたのは,卒後臨床研修の1年目も終わりに近づいた3月のことであった。私は,学生当時から救急医療に興味があり,卒後臨床研修も救急医療を十分経験でき,なおかつ,教育システムが充実した病院での研修を希望し,ハワイ大学のスタッフが教育に携わる沖縄県立中部病院での生活を選択していた。研修医生活はハードで,休日はほとんどなかった。先生にお会いする日も,当日の朝まで手術があり,もうろうとした頭で飛行機に乗り込んだ。シートベルトを締めた記憶はあるが,すぐに意識は暗黒の世界へと吸い込まれていった。
研修医の習性か,「急病人が発生しました」との機内放送に目が覚めた。乗客の1人がサンドイッチをのどに詰まらせ,窒息状態になったようである。すでにフライトアテンダントが異物除去にあたり,あえぎ様の自発呼吸もみられ始めていた。当時は機内で使用可能な医療機器はなく,借りることができたのはペンライトのみであった。頸動脈および幌骨動脈の触知は良好。意識状態は深昏睡,瞳孔は両側5mmと散大,対光反射は消失していた。口腔内に残存する食物は,直視下には認められなかった。気道確保後,酸素マスクを引き下ろし,呼吸補助をしながら,患者の前胸部を露出し,胸郭に直接耳をあてて呼吸音を聴診する。両側呼吸音左右差なし。次々と所見を口頭で伝え,メモしてもらった。
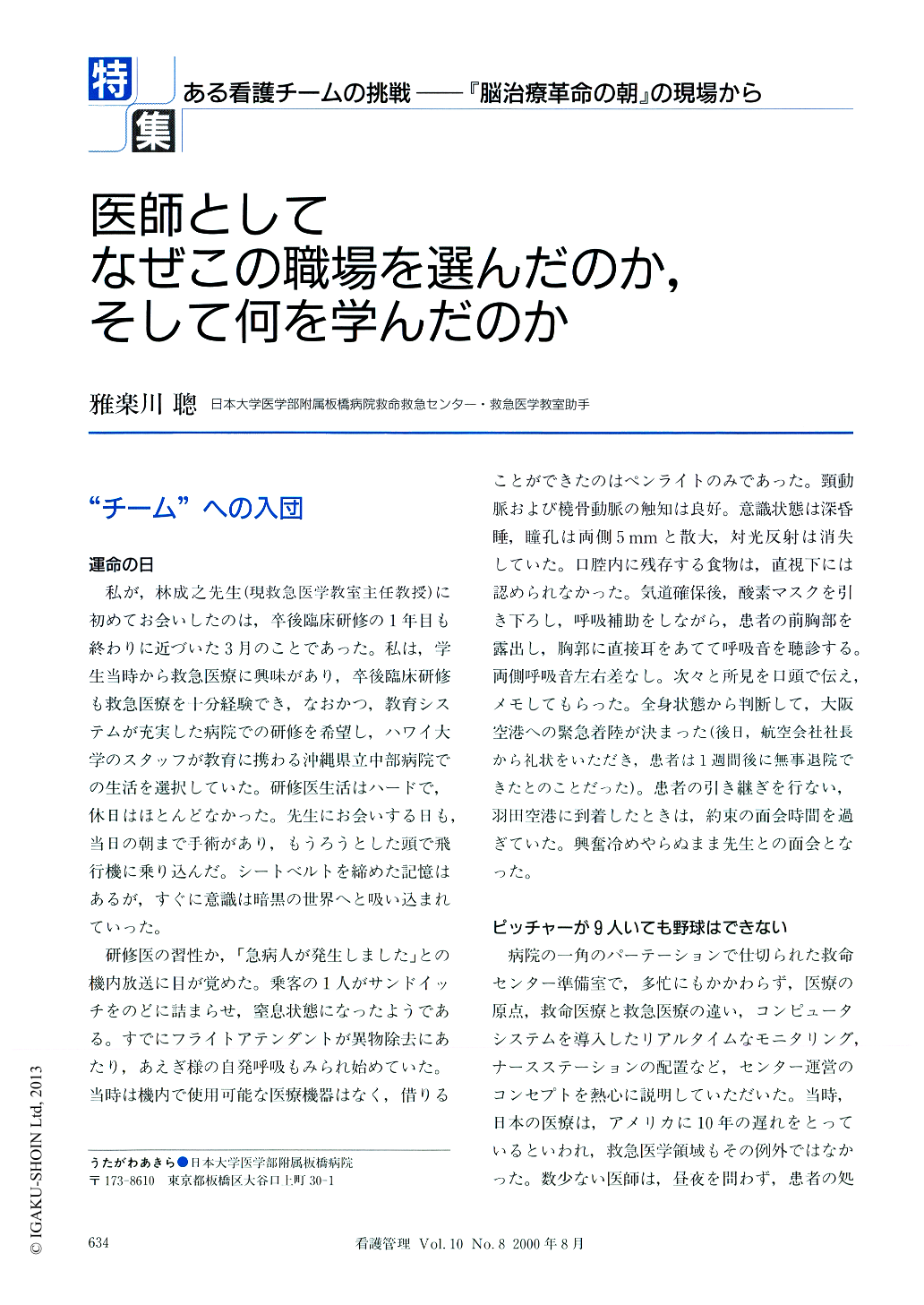
Copyright © 2000, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.


