実践報告
血液透析受療者による授業サポートの意義―「生活者」として語ること
程塚 京子
1,2
1さくら総合専門学校
2元 日本医療科学大学
pp.1028-1032
発行日 2019年12月25日
Published Date 2019/12/25
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1663201383
- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
- 参考文献
血液透析受療者の授業参加
リアリティのある看護学教育のために
医療教育の方法の1つであるOSCE(Objective Structured Clinical Examination/客観的臨床能力試験)*1は、医学部および歯学部、薬学部(6年課程)での卒業要件である他、看護学においてもその重要性は意識され、演習などの形式で導入されている。OSCEにおいては、SP(Simulated Patient/模擬患者)*2として養成された一般市民が患者役を担い、学習に沿って作成されたシナリオどおりに演じる。SPを起用した演習は、机上で学ぶことが難しいチームワークやコミュニケーションのスキルを主体的に学ぶ機会となり1)、臨地実習に準ずるようなリアリティのある学習を可能にする。しかし一方で、臨床技能習得を叶えるシナリオ作成などの教員の負担が指摘され2)、特にOSCEにもとづく評価における「演技の標準化」についての課題が報告されている3)。
このようなリアリティのある教育方法は、わが国における看護教育史にも見て取れる。患者の世話をその家族や付添婦*3が行うのではなく、看護師がその役割を担うとされた*41950(昭和25)年の完全看護体制では、看護師不足を背景として、看護学生は「実習」と称した医療機関での貴重な労働力となっていた4)。主に大部屋の患者の身のまわりの世話が看護学生の実習となっており、その大部屋は「実習病棟」とされ、医学生にとっての医術習得の場にもなっていた5)。また、看護師養成においても、演習では生身の人間を対象としていたことから、現代のようなモデル人形の使用はやむを得ない手段であった6)といえる。
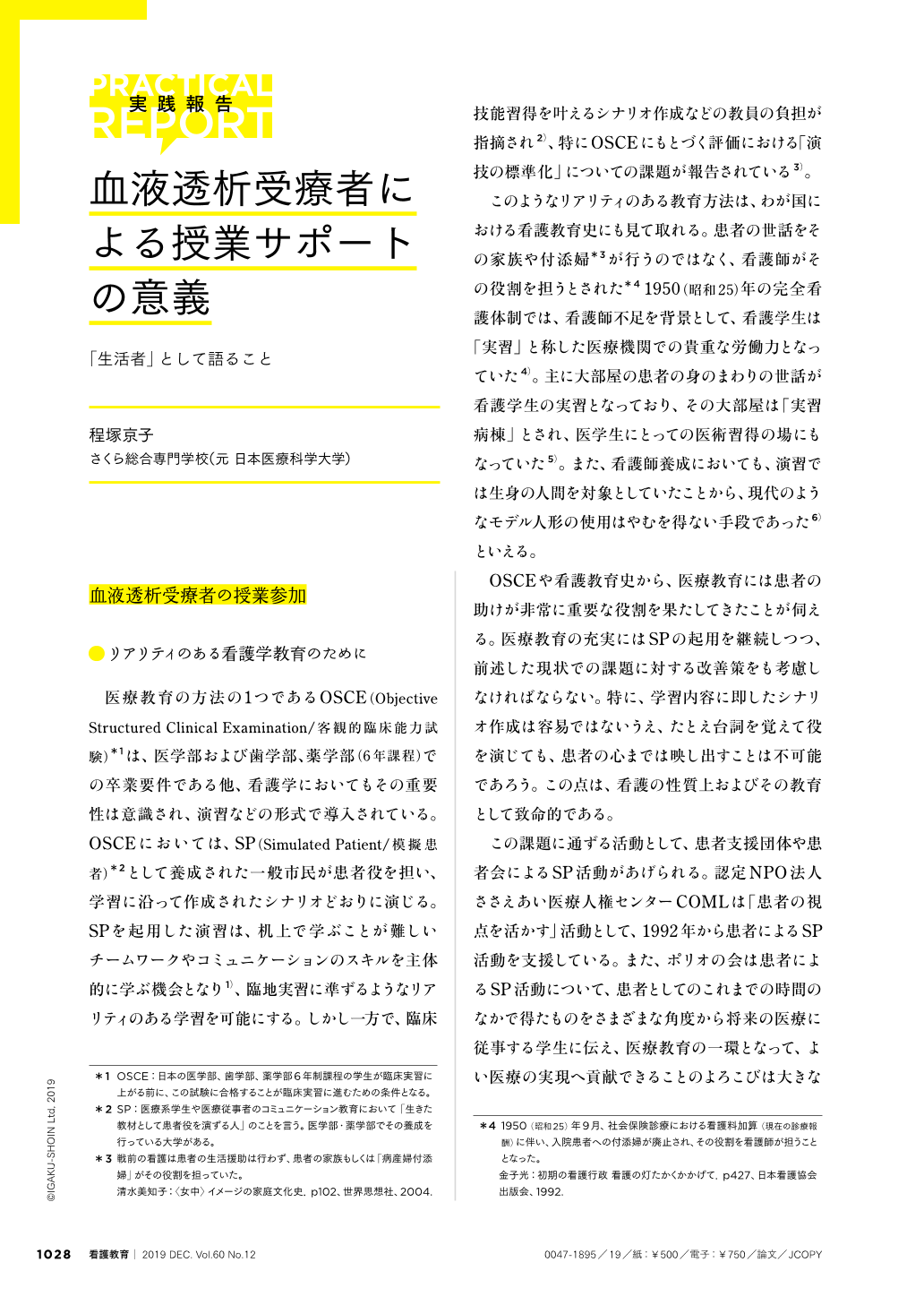
Copyright © 2019, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.


