医学と看護
疼痛とその治療
稲本 晃
1
,
村山 良介
1
1京都大学医学部麻酔学
pp.77-81
発行日 1968年10月1日
Published Date 1968/10/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1661914164
- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
一生に一度も痛みを経験しないという人は決してないであろう。椅子のかどに下脚前部,いわゆる“弁慶の泣きどころ”をぶつけて強い痛みのため息もできず,かがみこんでしまったり,引出しを開けようとしてひじを打ち手のしびれた痛みをこらえたことは幾度となくあるにちがいない。長時間の正座で足のしびれとともに痛みが出てくる,次に正座を止めて足をのばすと熱い感じとともに針でさされるような痛みがあらわれてくる。これらの痛みは数分がまんすることによって自然におさまってゆくものである。針の先や刃物にふれた時“痛い”といって反射的に手を引込めるのは生体の一つの防禦反応であり,虫垂炎や胆嚢炎の痛みは体の異常を気づかせる警鐘と受けとることができるものである。
しかしこのように痛みは人の注意をうながすために必要なものであるとしても,それはあまりにも度を越すことが多くはないであろうか。京大の木村教授らは“はたして痛みは人間を保護するものか”という疑問を10年も前からなげかけておられる。人生で一番恐しいものはと問われたならば“死”と答えることは当を得ているであろう。いつやってくるかわからず,何よりも確かにおとずれる死。有から無の世界への変転,人は実感としてとうてい理解しにくい恐怖であり,そのことを考えるのをなるたけさけたいとするのは人の情というものである。
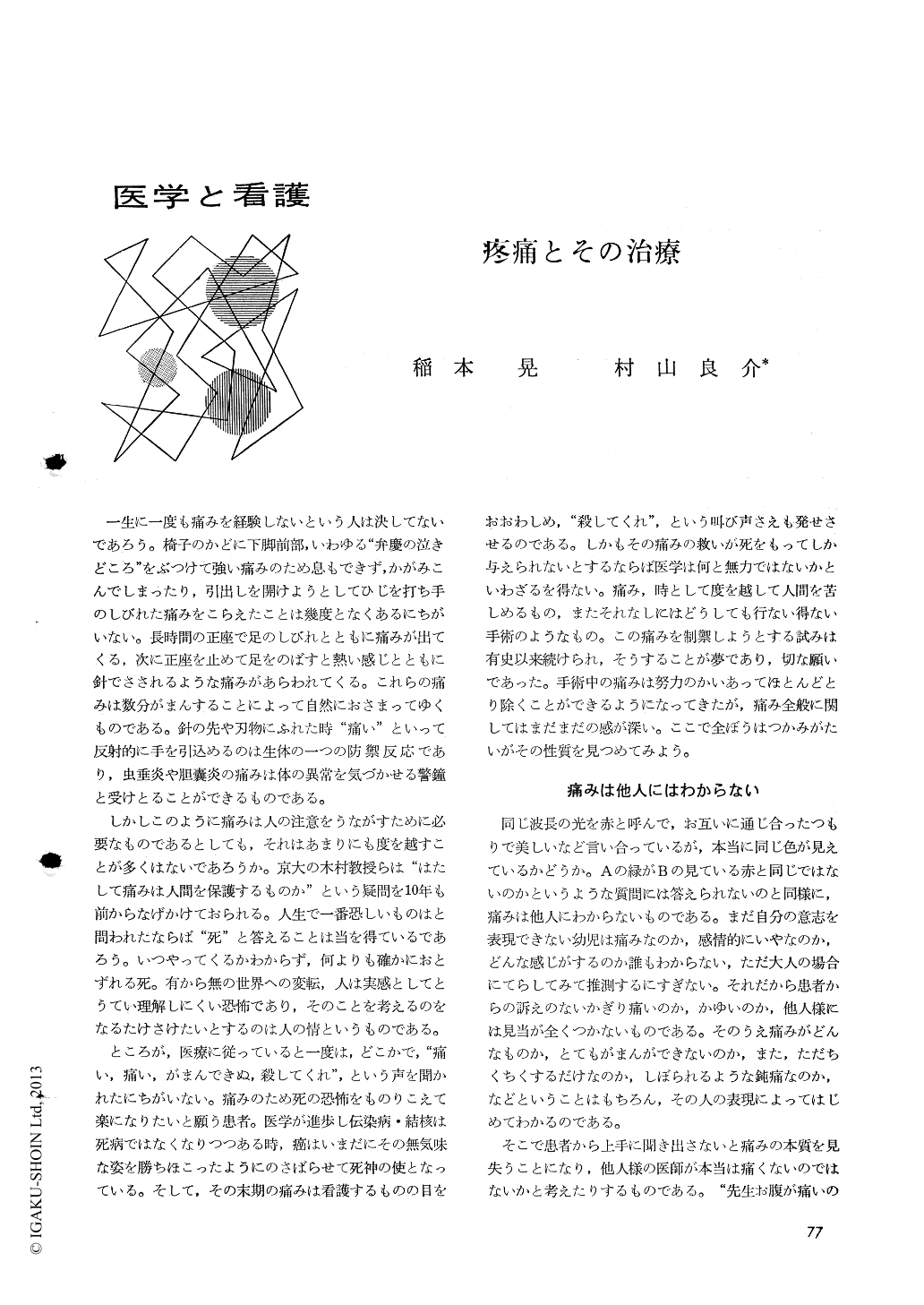
Copyright © 1968, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.


