特集 肝臓病
肝炎の看護—自覚症のない患者の指導
橋本 秀子
1
1淀川基督教病院
pp.36-39
発行日 1963年3月1日
Published Date 1963/3/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1661911878
- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
1.肝炎の自覚症について
一般にビールス性肝炎,流行性肝炎の急性期(黄疸前期)では,発熱,胃腸症状その他の自覚症があるが,黄疸期に移行すれば自覚症が軽快する。潜伏期が数週間あるが,この期間に全身倦怠,食飲不振,下痢,嘔気・嘔吐があるが,他の疾患とまぎれやすく,発熱をもって始まっても,本人は感冒その他の疾患と思いやすく,数日経過を延引させて行くうちに,ひどい食欲不振や黄疸が現われて,始めて医師を訪れることが多い。まして急性肝炎の軽症,または黄疸をともなわない不全型については,なおさら自覚症状を欠くので気づかない場合が多く,血清肝炎に至っては,自覚症状がまったくなく,肝機能検査が陽性となって始めて治療を強要される例が多い。
2.急性肝炎の予後と看護および指導の必要性
急性肝炎の予後は決して楽観を許さず,急性期から急に肝性昏睡にたおれるもの,慢性化に向かい,ついには肝硬変にまで移行するものなどが明らかになってきた。さらに肝炎の完全治癒は精査によれば意外に困難で,未治癒のまま放置すれば,再発,再燃を繰り返し,慢性化の速度を早めることも知られている。肝炎の治癒判定は臨床上かなり困難で,肝機能がいちおう正常化した後にもなお肝の組織学的変化は完全に治癒していないことが報告されている。そこで肝炎では,早期の徹底した治療と行き届いた看護が必要であるが,同時にその回復期および遷延性肝炎患者への療養指導もじゅうぶんに行なうことが望ましい。
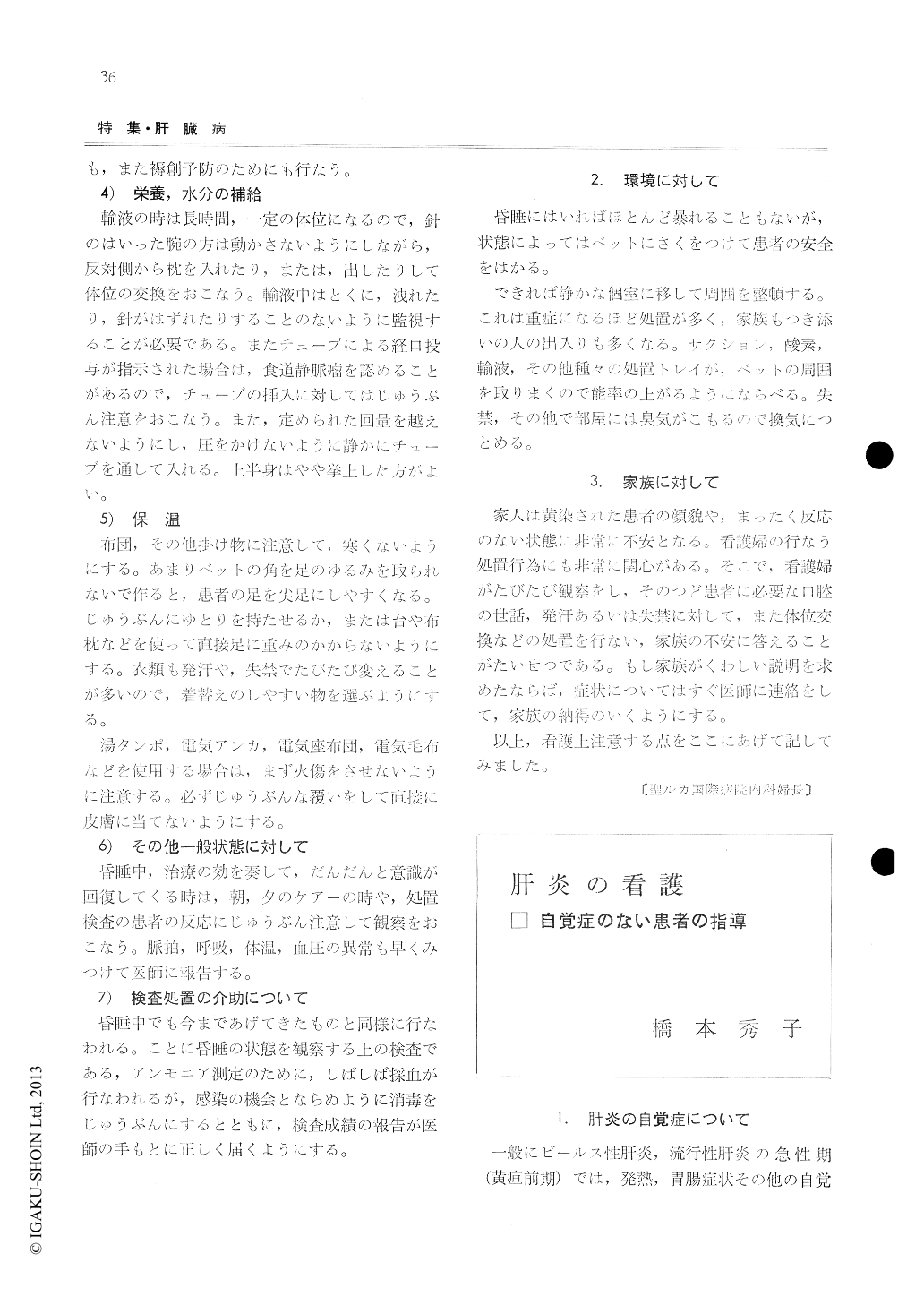
Copyright © 1963, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.


