連載 道拓かれて—戦後看護史に見る人・技術・制度・12
死の瞬間までその人らしく—がん告知・ターミナルケアから緩和ケアへ
川島 みどり
1
1健和会臨床看護学研究所
pp.1168-1171
発行日 1997年12月1日
Published Date 1997/12/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1661905491
- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
病院における死の情景
「ご臨終です」と告げる医師,泣き崩れる家族.直前に婦長や主任のさりげない指示により,丸盆に水の入った茶碗と綿撒糸,二つ折りの正方形のさらし木綿を添えて持参したこずえは,周辺のアンプルや注射器などを静かに片づけながら,臨終場面での先輩たちの処し方を目に入れたものである.あらかじめ予測された死,突然の急変と,死の形もその迎え方もさまざまではあったが,そして家族の嘆きの態様もいろいろであった.
看護の道を志した以上,死に何時かは出会わなくてはならないと覚悟はしていたものの,身近な人の死を未だ知らないこずえにとっては,どのような死の場面も,厳かでドラマティックで,心の奥底に氷の彫刻をはめ込んだような感じをしばらくのあいだ忘れることができなかった,その場に居合わせた先輩看護婦たちの対応も一様ではなかった.涙一つ見せず能面のような無表情,目を真っ赤にして家族の嘆きに感情移入する人.
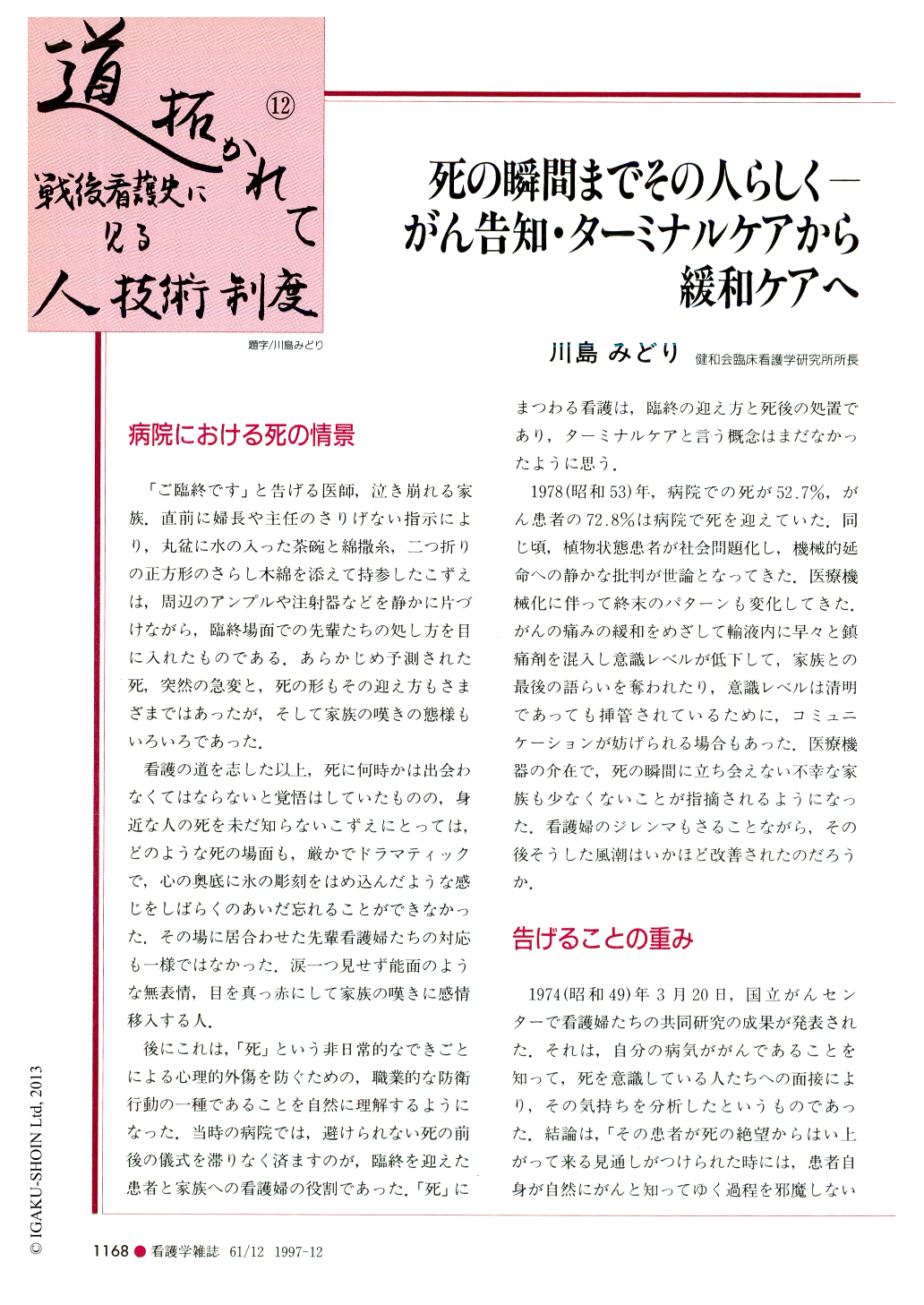
Copyright © 1997, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.


