Japanese
English
- 有料閲覧
- Abstract 文献概要
- 1ページ目 Look Inside
はじめに
脳性麻痺(以下CP)に代表される脳原性運動機能障害の疾患群が,近年,従来見慣れていた(典型的)病態像とはいささか異なる状況を呈していることは,しばしば指摘されることが多い1).特に,周産期医療の飛躍的向上がみられ,CPの超早期・早期治療の定着がなされた以降の10年間は,その傾向は一層明らかとなり,これらの因果関係の論議も絶えない現状といえる2).すなわち.周産期の異常を有するCP自体がしだいに減少し,その代りに原因不明の種々の脳障害児の比率が増すという傾向である3).
この結果,一方では独歩や杖歩行を獲得する運動機能障害としては軽症例が目立つ反面,視聴覚も含めた感覚障害や,治療に抵抗するてんかん発作,摂食障害や言語障害,知的発達遅滞等を合併したり,何歳になっても頸定すら獲得できない脳奇型や脳形成不全を伴う重症例も,その比率を増していることである,当然のこととして,乳児期の早期に脳障害の確定診断のつくものほど症状は重いといえる.
しかしCPの多くは,実は未確定診断のまま,4~6カ月頃に“要治療児”として治療訓練が始められ,その後の経過の中でCPの確認を得るのが通例といえる4).
一般に脳損傷児の特徴として,運動麻痺等が明らかとならないうちからでも運動発達が遅れることはよく知られているが5),訓練を受けているCPでは個々の症例により,これらの遅れの程度は千差万別であり,ほぼ正常範囲の場合から何年と遅れる場合まで多様な広がりをもっていることが多い.まして,彼らの予後を発達途上で予測することは極めて困難といえる.
他方重度の合併症を有するCPでは,姿勢や運動の障害が将来的に重篤であることを予測することは,たとえ乳児期であってもそれほど難しくはない.このように多面性と多様性をもつ脳原性運動機能障害児を,身体障害者福祉法(以下身障法)に沿って評価しようとする時,小児の発達障害の質的把握について,第一線の臨俵場面ではいささか困惑することがめずらしくない.このような現場での迷い,評価を行う時の思考過程の中で生ずる問題点について述べてみたい.
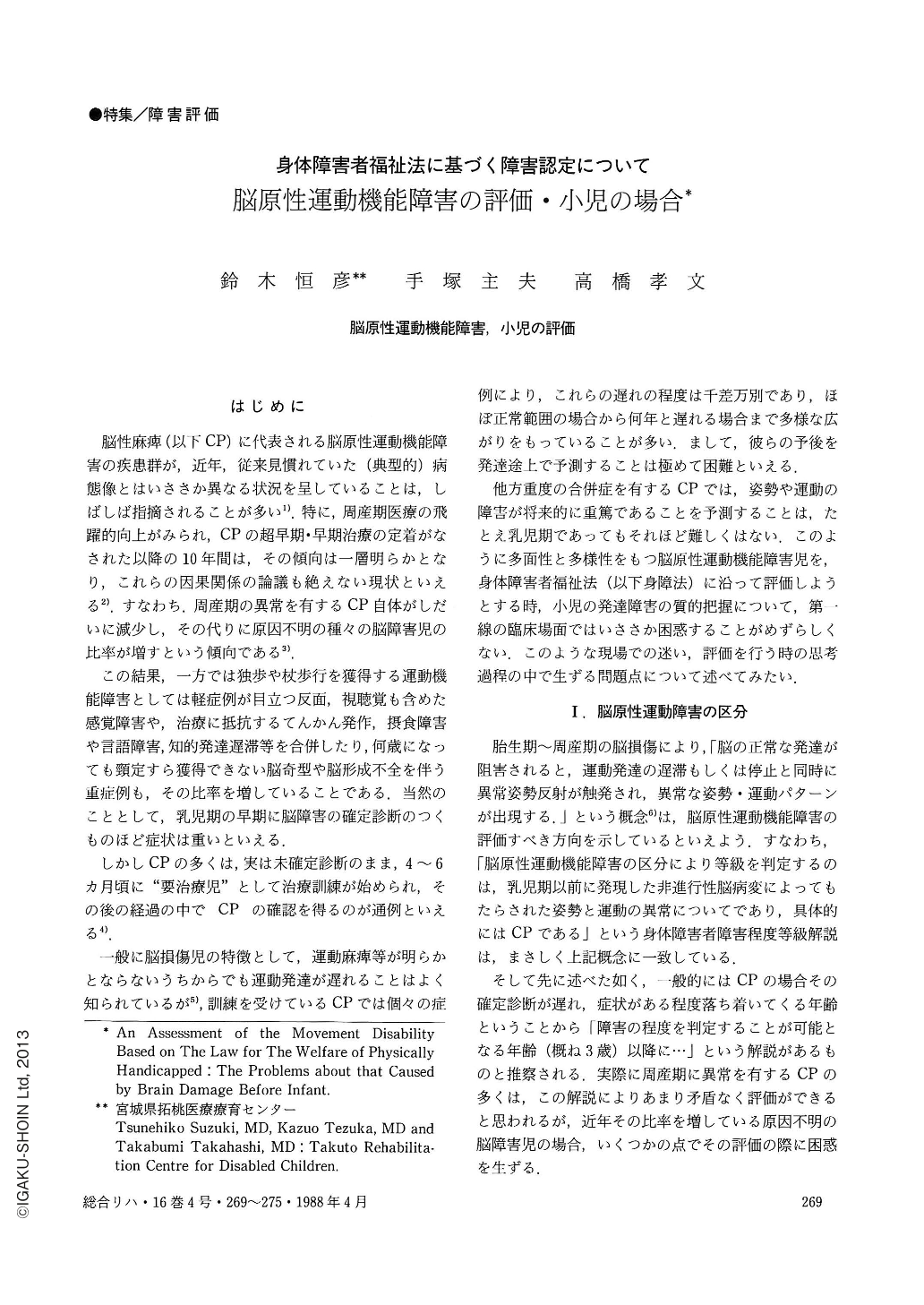
Copyright © 1988, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.


