Japanese
English
- 有料閲覧
- Abstract 文献概要
- 1ページ目 Look Inside
はじめに
諸家の報告1,2)によるとリハビリテーションを受けた脳血管障害片麻痺患者の90%前後は独立歩行あるいは杖なし歩行が可能となるといわれている.しかし一方,地域実態調査3,4)にみられるリハビリテーションを受けなかった群のそれは80%前後とより低い値を示している.
歩行機能の予後を決定する因子としては種々のものがあげられようが,そのうちでももっとも重要と思われる因子の一つとして,たとえば年齢について,原5)の成績では55歳以下の者の独立歩行は86%であるのに対し,56歳以上の者では57%と低く,また服部6)の成績では60歳以下71%,61歳以上29%とさらにその差は大きくなっている.
歩行不能の原因としては,Lorenze7)の分析によると,1)筋力不足,2)筋緊張低下,3)痙牲がもっとも多い理由とし,それに次いで,4)意欲欠除,5)平衡感覚の障害,6)小脳性失調症をあげている.また,しばしば引用される片麻痺のリハビリテーションの成績を悪化させる因子としてPeszczynski8)は,とくに歩行に関しては下肢の屈曲拘縮(15°以上)がもっとも重要であるとしているが,さらに重要なものとして,1)長期にわたる弛緩性麻痺,2)知覚障害(とくに深部知覚,位置覚障害),3)半盲,4)痛み,5)心理的異常,6)意欲不足,7)body imageの障害なども大いに歩行機能の予後に影響を与える因子としている.
以上,片麻痺の歩行機能の回復を左右する患者サイドの重要な因子としては,年齢のみならず上記のような種種のものがあげられようが,一方,セラピーをする者の側からも患者の歩行機能の予後に大いに影響をおよぼす重要な因子のあることも決して忘れてはならない.すなわち,急性期(臥床期)から将来の回復期(離床期,歩行期)を予期しての準備的正しいリハビリテーションプログラムの遂行こそが,その後の歩行機能の回復を決定づけるもっとも重要な因子といえるだろう.
いずれにしても,脳血管障害片麻痺患者の身体機能とその予後は,脳にある病巣の部位と広がりとの密接な関係があり,皮質・皮質下性のものや橋性のものは内包障害性のものよりも機能回復の程度は悪く,内包障害性のもののうちでも,内包後脚後半部の障害例では著しく回復の悪いものが多いとされている4).
以上述べたように,片麻痺の歩行機能の回復に関しても種々の問題があるが,とりわけ失認・失行症といった高次の機能障害を合併した症例の治療法,失調症,不随意運動を伴った場合の対策,深部知覚障害による歩行時のinstabilityに対する対策,さらには装具処方の適応の決定と,足変形に対する整形外科的機能再建術の適応とそのタイミングの決定など,片麻痺のリハビリテーションの日常臨床面での多くの未解決の問題を解決していくためにも,今後この方面でのリサーチが重要と考えている.
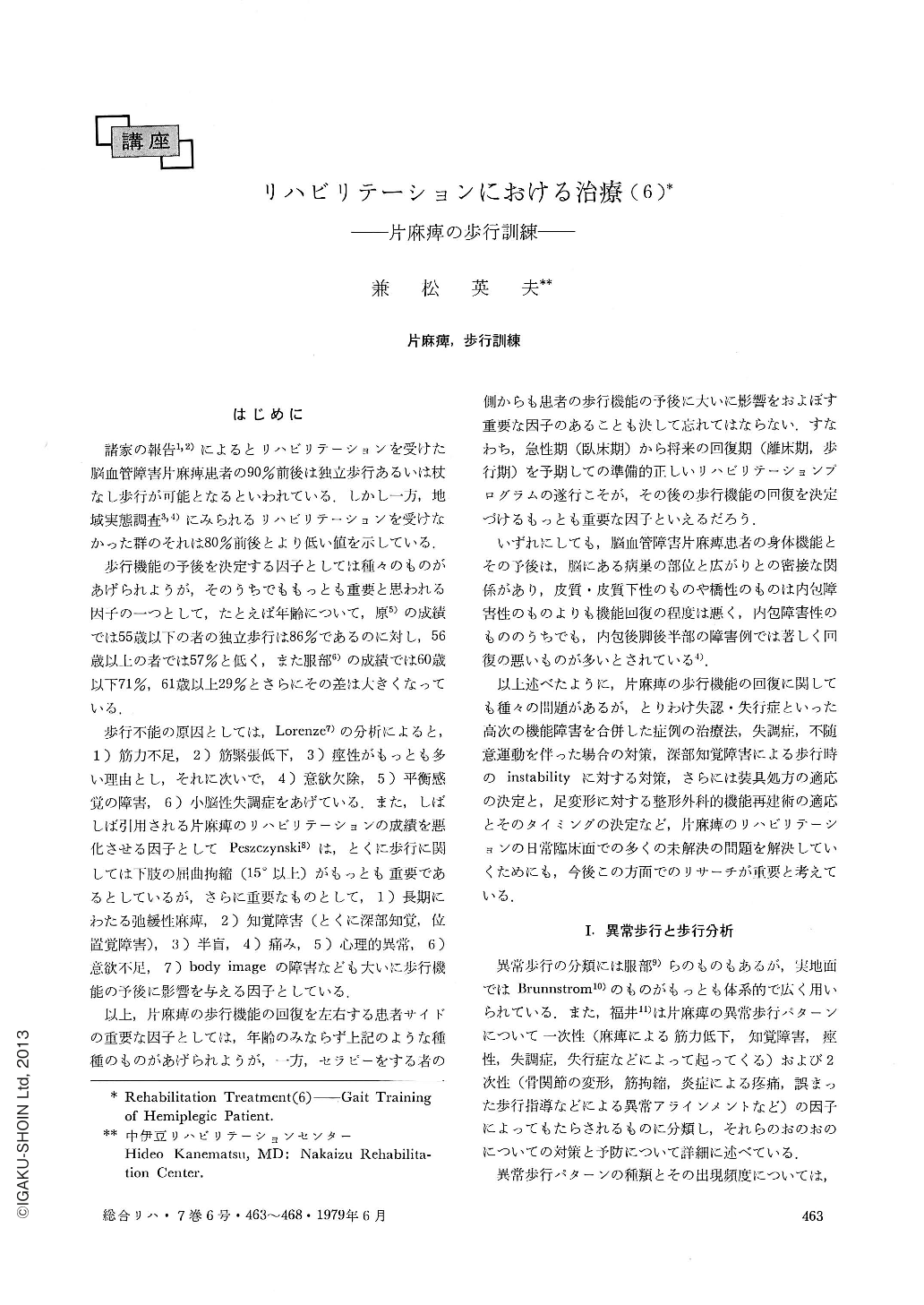
Copyright © 1979, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.


