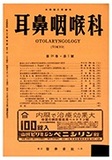- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
1944年Wacksmanにより分離されたStreptomycin(SM)は結核化學療法に卓効を奏しているがその副作用としての第8腦神經障碍も1945年Hinshaw and Feldmanの發表以來その特異性の故に多數の研究報告が續いている。然し筋注に於てPAS併用SM間激療法で第8腦神經副作用を殆んど除き得る現在では臨床上結核性髓膜炎治癒後に於ける難聽に重點が移つて來ているがこれも種々新抗菌劑の出現投與法の進歩により發生は減少しているものと思われる。さて現在迄にSMによる副作用特に難聽を主訴として本外來を訪ねし患者は合計47名で結核性髓膜炎によるもの15(内全聾8)結核症で筋注によるもの27,結核以外の疾患に髓腔内及筋内適用で夫々2及3となつている。その内興味ありと思われる6例に就きAudiogramを中心としての症例報告,更に核結性髓膜炎での副作用發現機序を臨床像との關連に於て文献的考察を行つた。
UCHIYAMA AND KAWAMURA, basing their study on 24 audiograms taken on 6 cases with whom involment of the 8th nerve occurred by streptomycin therapy particularly, in cases with tuberculous meningitis where dihydrostreptomycin was used intraspinally, conclude that, under the premises, there is no way in which involvement of this nature may be avoided excepting to be on the alert for recognition of symptoms early in their manifestation.
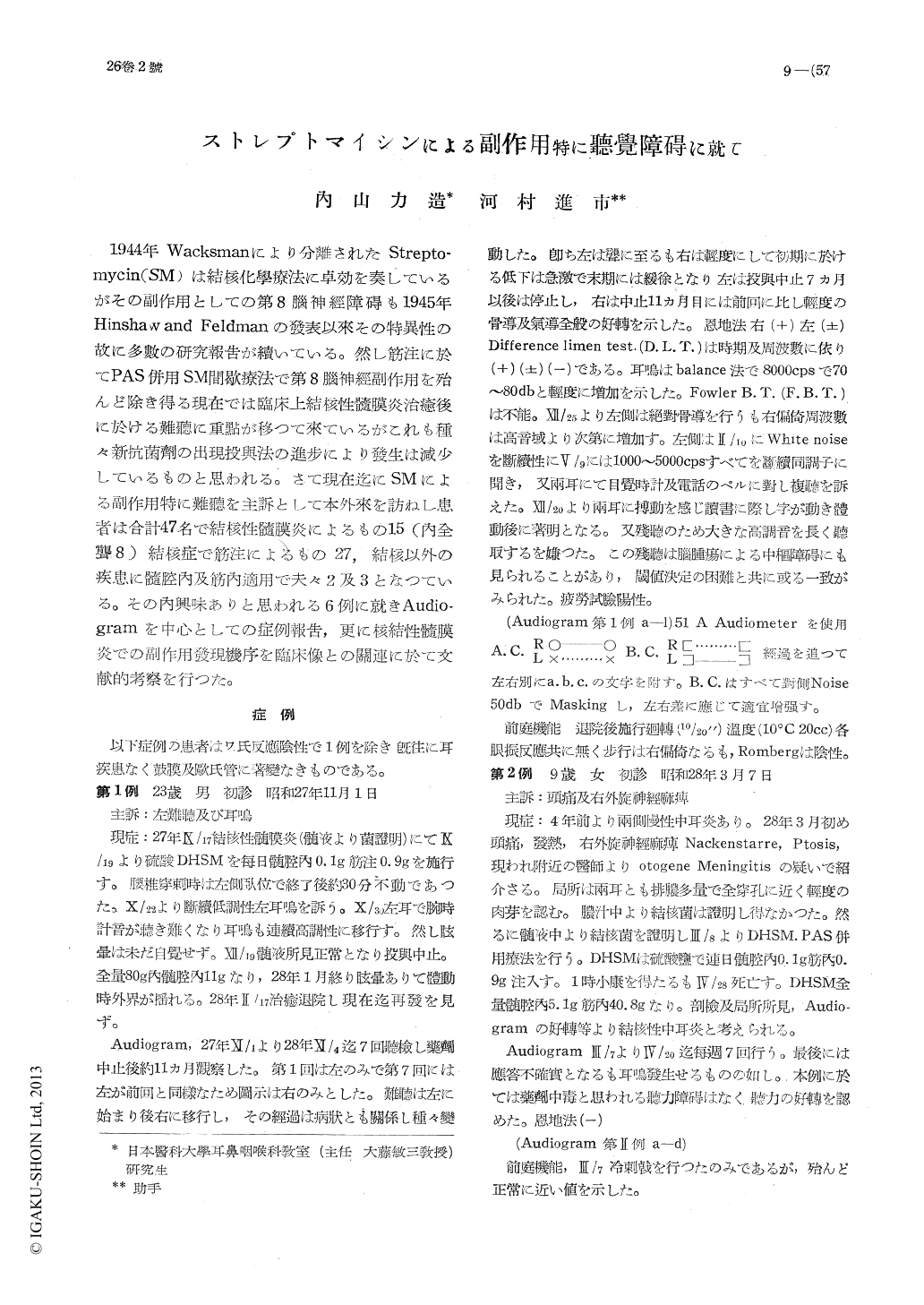
Copyright © 1954, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.