- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
聽覺と音聲に關する私どもの研究で,臨牀に比較的關係の深いものを,綜轄的に記載して,學的良心旺盛なる畏友西端新主幹に敬意を表し且つ本誌の今後の發展に寄與せんことをねがう。ここに私どもというは,1930年以來,東京帝國大學耳鼻咽喉科教室及び同附屬醫院分院で,私と苦樂を共にし,それぞれの研究に從事した人々を意味する。
私は元來,聽力及び聽能の檢査には特殊の興味を感じ,その重要性を信ずるものであるが,咡語檢査の際,既定の方法に從えば,健康人の聽取距離は既定の6米を遙に超過し,時には9米以上にも及ぶの多いのに異樣な感をいだいた。始めこれを日本人の聽力の優秀性に歸して,簡單に解決してゐたのであるが,それではどうにも納得のできないいろいろの事實に遭遇して遂に健康人に據る咡語聽取距離6米なる測定値は,現今の如く無響室内で行はれた實驗でないところに原因があるのを知つた。檢査音以外の音の存否が聽取距離の大小に影響を與へてゐることに氣がついたのである。健康者6米といわれた時代の檢査は診察乃至廊下等で測定されたのに對し,現今では無響室内で實施される場合が多い。實際に就て考察する場合,無響室の如き環境内での實驗が正しいが,普通の室でのそれが一層眞實性を得ているかは,充分考慮しなければならない要點である。何れにせよ檢査音以外の音の存否が測定結果に多大の影響をもつてゐるのは否定することのできない事實であつて然も目的音だけしか存在しないというやうな環境は實際には殆どないとすれば,吾人の聽力或は聽能と稱する事實は,音の隱蔽作用の結果なりということもできる。即ち聽いてゐるというのは色々の音の大なり小なりの隱蔽作用のもとで,目的音を認知するという事實を意味してゐるのである。この見地から私どもは聽力及び聽能の研究にさきだちて,音の隱蔽作用なる現象の研究に着手した。二つの音が同時に存在する場合,その中の目的音は,他音の強さにつれて次第に大きくされないと認知はだんだん困難となり,きこゑるかきこゑないかの境の數値も漸次その大きさを増し聽閾の上昇を示す。この聽閾上昇量を音の隱蔽度と言ふのであるが,これをきめるために先人は,他音の存在に於て目的音のやつときこゑてくるところ,即ち聽閾に達する點を測定した。私共はこれとともに,逆にそれ迄明瞭にきこゑてゐた目的音が始めてきこゑなくなる點,即ち目的音が聽閾から姿を消すところをも測定し然もこの始めてきこゑてくる點と,次第にきこゑなくなつてしまふ點との間には,目的音の大きさに,常に相當の差のあることを確認することができた。先人のやうに始めてきこゑのくる點のみを測定してゐたのでは,きこゑてきたと訴へても,目的音がきこゑたのか何か他の音感覺が起つて來たのかわからない。事實,被驗者が,あツきこゑてきましたと訴える時にも,それは目的音以外の唸り現象であつたり,單なる騷音にすぎない場合も屡々ある。これは目的音を始め大きく被驗者に認識させ漸次きこゑなくなる點をはかるという私どもの方法を併用することによつて始めてまねかれることのできる現象である。然も聽閾測定値がこの兩方法によつて常に全くちがうということはわれわれ生物學の學徒にとつて頗る興味の深いものであるのみならず隱蔽作用ということが誠に複雜な現象なのを物語るものといわなければならない。即ちことがらがかくの如くこみいつてゐるので,私どもの結果を先人のそれと比較して記載することとする。私どもの實驗でも二つの音の音高が接近するに從て目的音の認知は次第に容易となる。振動數の近似する二音に因て起る唸りのためにさうなるのであるが,唸りは目的音ならずというやうな議論は別として,この點では私どもの實驗は先人と結果に於て同一なりといつても好い。つぎに成書に於ては,二つの音の音高がますます接近して全く同一のものとなれば隱蔽度は極めて小さくなると主張してゐる。即ち目的音は他音に妨害せられることなく頗る容易に認知せられるというのである。これは私どもの實驗では全く逆である。即ち同一音高の同時2純音を二つなりと認知することは殆ど不可能なりとの結果に到達した。こんなことはくだくだしく説明するまでもなく同時同音高の二純音といえばそれは同一音の強さの變化にすぎないものであつて音の隱蔽作用の問題ではない。こんなことは一目瞭然の事實のやうであるが,この先人の誤りを發見するのに私どもは可なりの長年月を要し相當數の實驗をかさねた。先入主なるものの影響の大きいのにおどろいてゐる。然し〓のことは同一音高二純音間に於ける隱蔽作用に關して一つの新事實を發見したと言つても好いと思うが,つゞいて私どもは同一音高と性質の頗る類似する八度音程即ちオクターブ關係にある二純音間の隱蔽作用に關して實驗した。結果はここでも全く同一の傾向を示し,目的音の認知頗る困難なりといふ結果に到着した。そこで私どもは五度,四度,三度というやうな音の協和關係に從つで實驗のあゆみをつづけたのであるが,かくの如き協和關係にある二音の間で目的音を明確に認知することは,他の不協和關係にある二音間中の一音をとらゑるよりも逆に困難なりという事實を確かめることができた。即ちかくの如き事實から見れば,音の隱蔽作用なる現象は,在來の如く二つの音の物理學的性質にのみ依存して全ぼうを知悉しうるやうな簡單なものではない。二音の融合度或は分離度というやうな生物學的考察をも充分にこうりよしなければ解決全く困難なりといふことを確かめることができた。單に二音間の量的關係のみでこの現象を説明しやうとしたためにこれまでのやうな過誤におちいつたものと確信する。ここに於て私共は所謂隱蔽作用なる現象が,二音間の親和性即ち音樂に於て言うところの和聲乃至對位等の質的關係に多大の聯關を有することを主張し,この點に着目しなければ現象の闡明は不可能なりと斷言するものである。
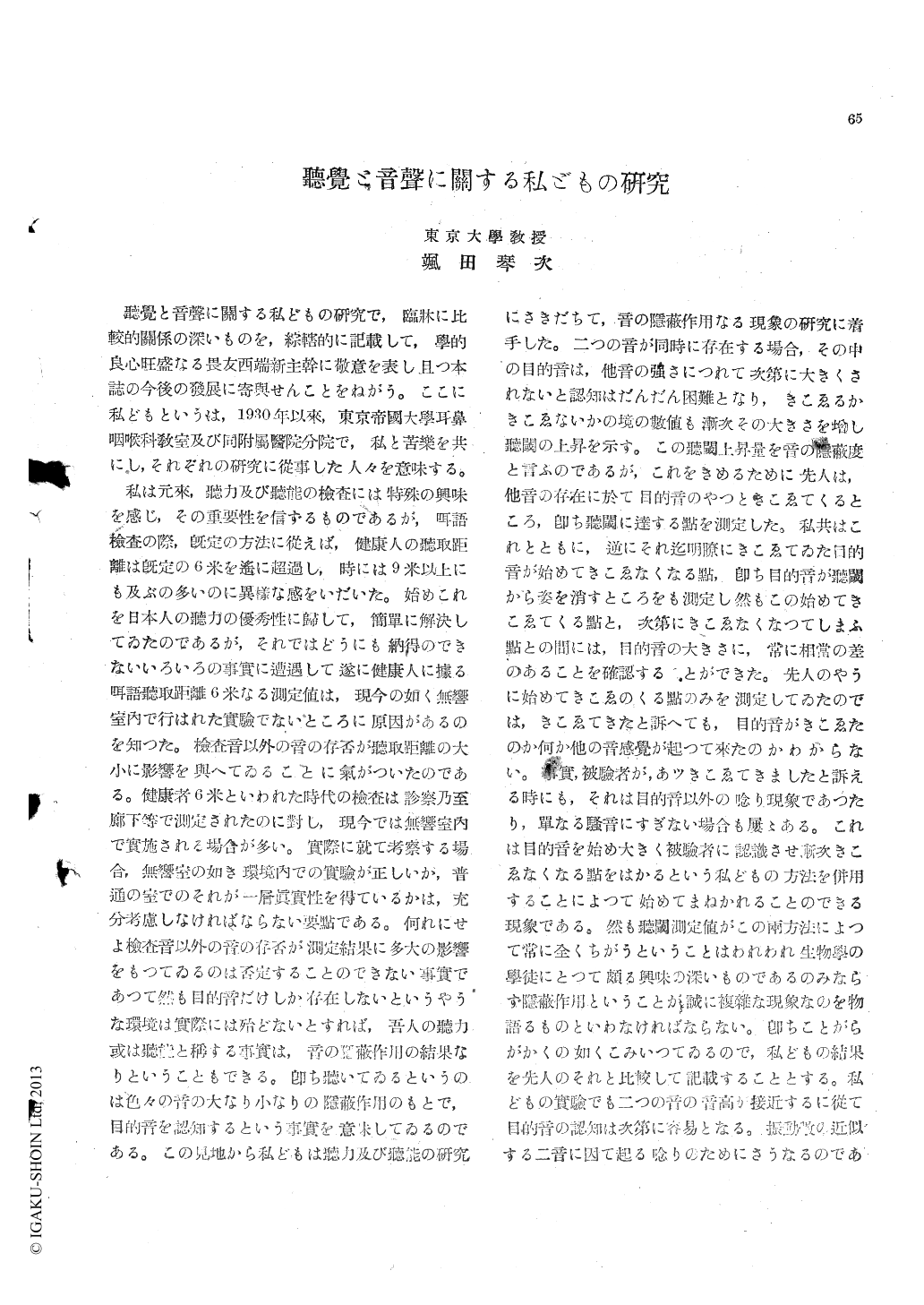
Copyright © 1947, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.


