連載 人間はいつから病気になったのか—こころとからだの思想史[6]
「痛み」と「病気」の乖離
橋本 一径
1
1早稲田大学文学学術院
pp.362-366
発行日 2017年7月15日
Published Date 2017/7/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1430200210
- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
- 参考文献
痛みと叫び声の分類学
「常に不愉快であるとはいえ、大半の痛みとはその目的において有益なものである1」。1803年に刊行された『苦痛論』において、医師のイポリット・ビロンはこのように述べる。ビロンによれば、痛みとは身体をさまざまな危害から守ってくれる「生命の番人」である。痛みは「目が強すぎる光を受けたときに瞼を閉じるように」知らせてくれ、「強すぎる音が聴覚を痛めそうなときには頭の向きを変えるように」促し、筋肉の痛みは「既に疲れている筋肉を酷使するのを防いでくれる2」。痛みは体に差し迫った真の危険を前もって伝えてくれる声なのだから、医師もまたこの声に耳を傾ける必要があるのは言うまでもない。ビロンの場合にはこれは比喩ではない。彼が提唱するのは、痛みに苦しむ患者たちが上げる叫び声を聞き分けることだからである。
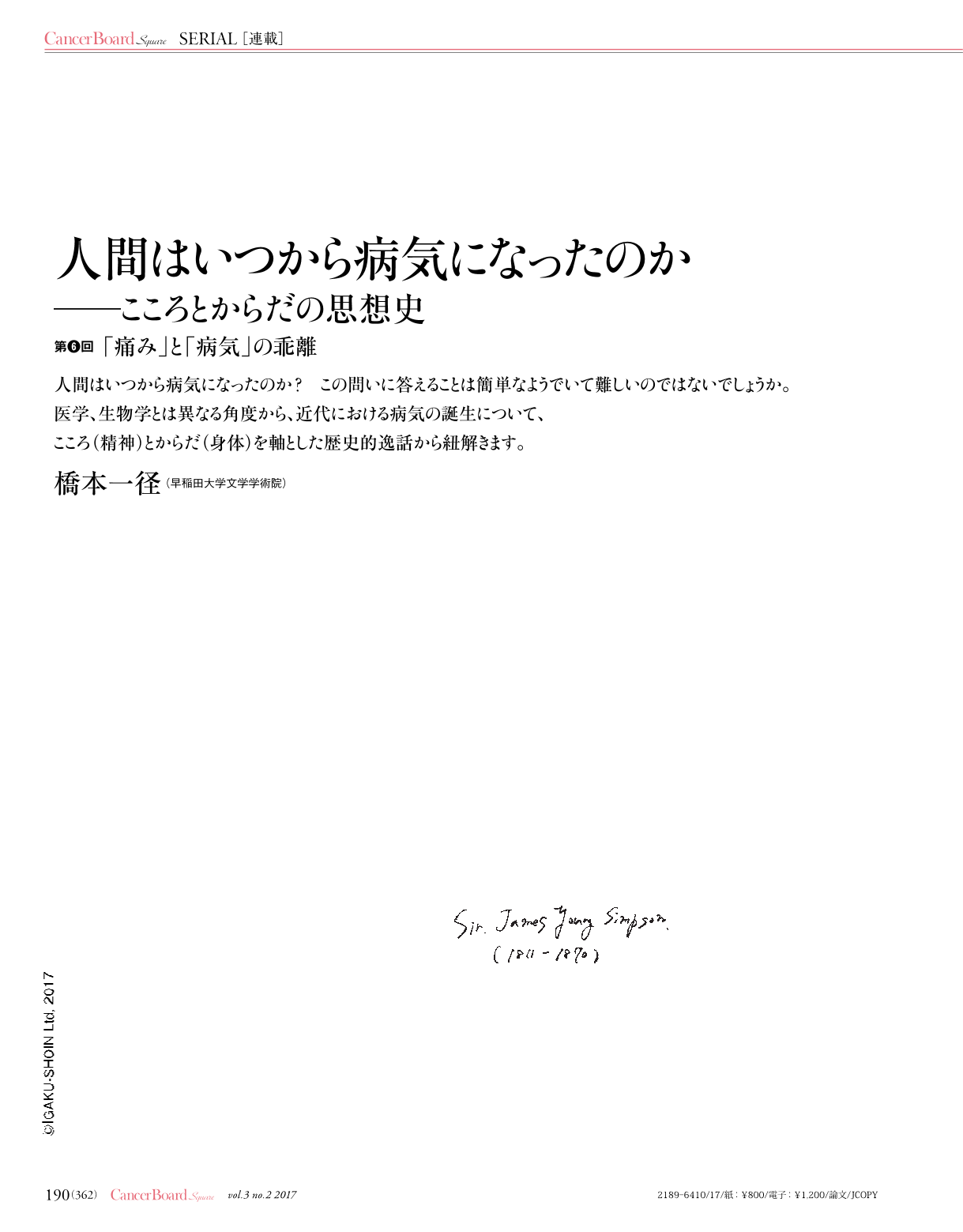
Copyright © 2017, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.


