Japanese
English
- 有料閲覧
- Abstract 文献概要
- 1ページ目 Look Inside
- 参考文献 Reference
- サイト内被引用 Cited by
はじめに
心因性非てんかん性発作は,てんかんを疑われて来院する人のほぼ1割,難治の人が集積するてんかんセンターでは2割近くに及ぶとも言われており,けいれんしながら救急搬送される成人の3割を超えるとも言われている5,6)。こうした背景からは総合病院の精神科医がコンサルトを受ける可能性も少なくない上に,時には精神科クリニックで診療中の人がけいれん様の症状を起こす事態は十分想定される。心因性非てんかん性発作(psychogenic non-epileptic seizure:PNES)に対する研究はその臨床的な重要さから等比級数的に増加しており,きわめて多数の論文が英文論文では発表されている。しかし臨床という観点からはいくつかの喫緊の課題が存在している。
第1に,臨床と研究の深刻な乖離の問題を挙げることができる。Cognitive behavioral therapy(CBT)が有効という論文は枚挙にいとまがないほど発表されてきたが,確かにCBTの開始時点と終了時点を比較すれば発作回数は減りはするが,長期的なQOLの改善にそれがつながるかどうかについては信頼性の高いデータは存在していない2)。物言わぬ精神科医,ケースワーカー,臨床心理士が個々のケースを自らの患者として受け入れ,長期間にわたって社会的な側面を含めて介入しつつフォローすることこそが真のQOLの改善につながっているのではないかという臨床実感がある。しかし,それを裏付ける研究デザインを作成することは構造的な困難さを伴うため,PNESの研究においては,長期的な実臨床を担う現場と論文発表をするCBT研究者との間に,必然的に深刻な乖離が生ずることになる。
第2にはPNESが神経学と精神医学の境界領域にあるという古くから強調されてきた問題である。神経内科医は自身にとって理解が難しい症状を精神科領域の問題だと考え,精神科医は逆に神経内科領域の問題だと考える傾向は世界的にみられ1),精神医学と神経学が別の領域に分けられてから一貫して存在し続けてきた問題であるとも言える。てんかん専門医が非てんかん性の病態だと判断して,地域の精神科医に紹介した患者がしばしばてんかんを再度疑われて送り返されてくるという事態が稀ならず起こることをこぼす国外のてんかん専門家は多い。他方で今世紀に入ってからでも爆発的な勢いで新たな病態が見つかっており,たとえばvoltage-gated potassium channels(VGKC)抗体脳炎では,faciobrachial dystonic seizureというこれまでてんかんの専門家が非てんかん性の病態だと判断しかねなかった特異な形態のけいれんが実はその診断に不可欠な特徴的な症状の1つとしてクローズ・アップされるという展開も起こっている。こうした背景を考えるならば,たとえ専門家が器質性疾患ではないと判断した病態についても,精神科医が独自の視点から,どうしても心因性の病態だとは思えないという事態が繰り返し起こるのはむしろ当然のことではないかとも思われる。
第3は,「心因」という言葉に対する精神科医の敵意の問題がある。これはアメリカ精神医学における風土病が日本に伝播したものとも考えることができる現象でもあるが,精神分析への強い傾斜とそれへの反発というアメリカ特有の歴史的・政治的な経緯がDiagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders(DSM)という診断体系のうちに具現化され,これを通して「心因」を連想させる疾病名はDSM第3版以降は可能な限り解体され,排除されてきた。PNESの「心因性」という冠は確かに必ずしもすべてのPNESに関して実態を表しているとは言い難いところはあるが,他方で心因性非てんかん性発作にも器質因では出現し難く除外診断ではなく積極診断が可能な場合もあり,さらに失神その他の非てんかん性ではあるが器質性のてんかん類似症と線引きをするという意味でもこの冠を現時点で外すのは混乱をもたらす可能性がある。実臨床において,薬物療法ではなく,環境調節と心理療法が一次的な治療手段であることを明確に意識するという意味でも,今のところはこの病名の有用性は有害性を上回っているのではないかと思われる。
以下,本稿では第1,第2の問題に焦点を絞って論じたい。
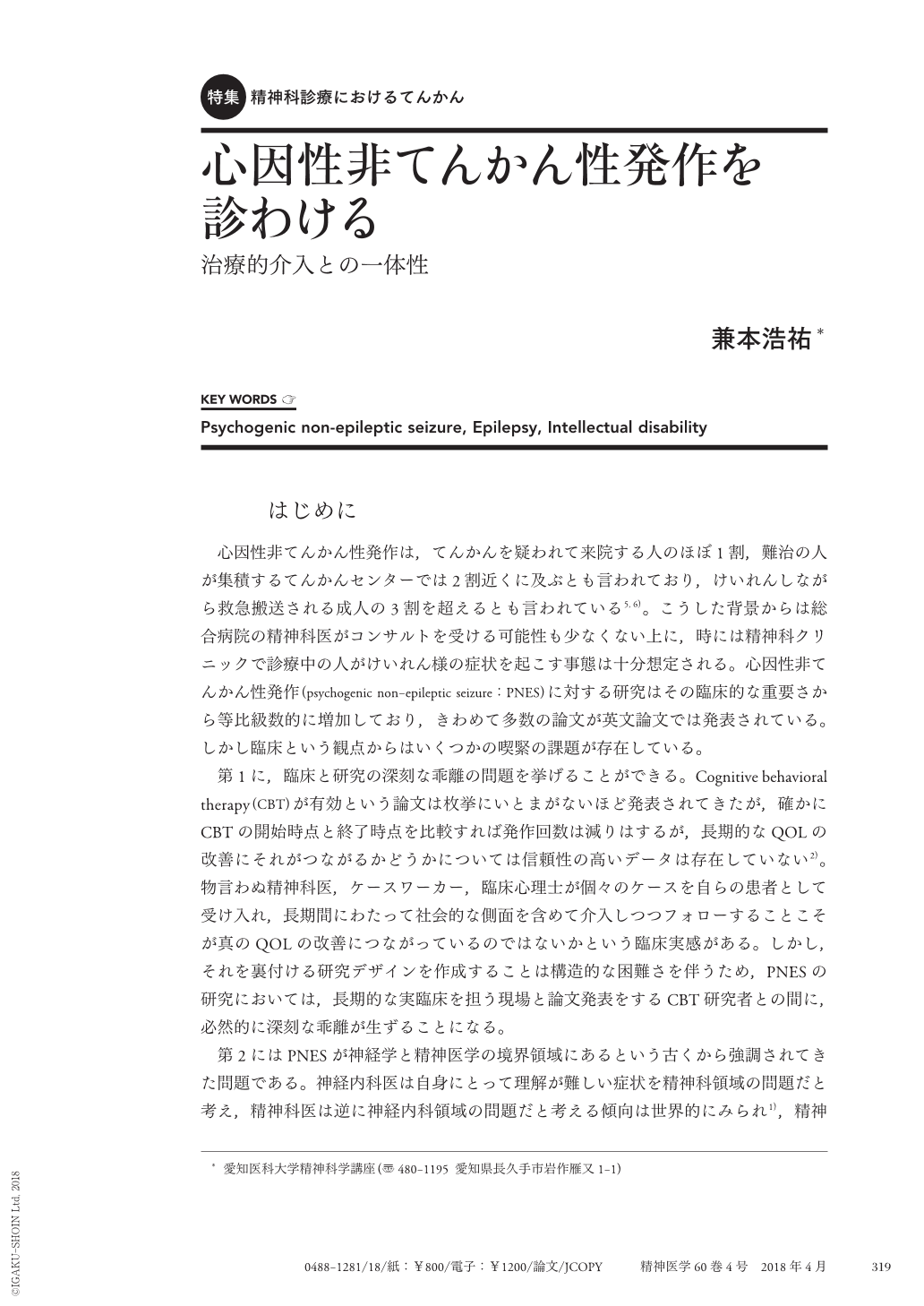
Copyright © 2018, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.


