特集 児童精神医学の現状と将来—都立梅ケ丘病院30周年記念シンポジウムから
〔指定討論〕
山崎 晃資
1
Kosuke Yamazaki
1
1東海大学医学部精神神経科
1Department of Neuro-psychiatry, Tokai University School of Medicine
pp.820-824
発行日 1983年8月15日
Published Date 1983/8/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1405203625
- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
I.はじめに
自閉症の考え方と治療・処遇の変遷について,演者の石井氏は,①自己刺激的行動,②予後像,③指導技法の3点を中心に論じた。長年にわたる氏の精緻な観察と情感にあふれる対応の仕方には深い感銘をおぼえた。
1943年,Kanner, L. 7)によって初めて報告された「(早期幼児)自閉症」概念は,それぞれの時代的影響をうけて変遷してきたが,1970年代以降,臨床経験の積み重ねと基礎的研究とくに生物学的研究の抬頭により,次第に一定の見解に到達するようになってきた。すなわち,アメリカ精神医学会のDSM-IIIには多くの問題点がある29)にもかかわらず,自閉症を「汎発達障害(Pervasive Developmental Disorder)」としてとらえ,明確に発達障害と規定したことは,Rutter, M. 15),De-Myer, M. K. 4)らの器質論的病因論を十分に取り入れたものとして高く評価されている。自閉症を発達障害ととらえ,病因として器質的要因を重視する考え方が,次第に定着しつつある現在,自閉症の臨床は新しい出発点に立つこととなった。そこで,最近の自閉症研究の成果から,石井氏が論じた3点について再検討し,主として生物学的研究の視点からあらたな問題を提起したい。
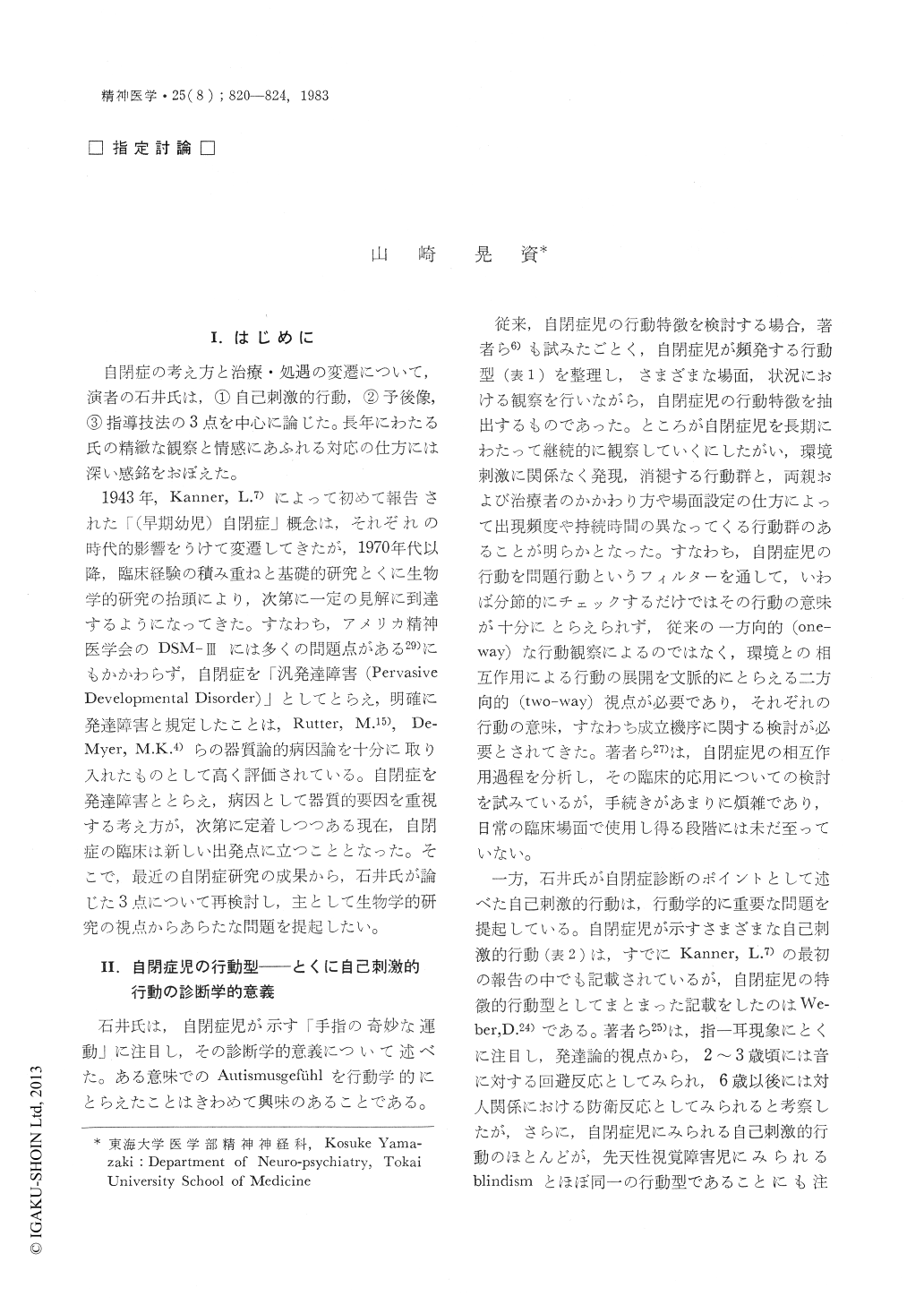
Copyright © 1983, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.


