Japanese
English
特集 呼吸・循環器治療薬の狙いと効果の現実
硝酸薬と心筋梗塞—ISIS−4を踏まえて
The Role of Nitrates in Myocardial Infarction
深見 健一
1
Kenichi Fukami
1
1岩手医科大学第二内科
1Department of Internal Medicine II, Iwate Medical University School of Medicine
pp.795-800
発行日 1996年8月15日
Published Date 1996/8/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1404900004
- 有料閲覧
- Abstract 文献概要
- 1ページ目 Look Inside
1879年にニトログリセリンが初めて臨床応用されて1)100余年,硝酸薬はいくつかの変遷と発展を遂げながら,虚血性心疾患治療に大きな役割を果たしてきた.狭心症の発作寛解薬や治療薬としての効果は既に確立されたものであり,今日においても狭心症治療の第一選択薬としての地位は変わっていない.一方,はじめは禁忌とされていた急性心筋梗塞症への治療にも応用され普及しだしたのは,1974年にJ.N.Cohn2)が心不全治療法としての血管拡張療法理論を支持して以来のことである.この20年間に心筋梗塞症の急性期ポンプ失調への治療効果をはじめとして,梗塞巣の縮小効果,左室心筋リモデリング防止効果,死亡率減少効果などに関する知見が集積し,心筋梗塞症での硝酸薬の効用に期待がもたれた.しかし,1994年のGISSI−3,1995年のISIS−4と,大規模臨床試験において相次いでその有用性が否定されたことは周知の事実である.急性期のポンプ失調や梗塞後狭心症での有用性を示す報告は枚挙に暇がなく,AHA/ACC task force3)においても標準的治療法としての地位が定まっているので,本稿では,梗塞巣の大きさや合併症発生率,生命予後に及ぼす影響を検討した報告を整理し,心筋梗塞症での硝酸薬の意義と今後の方向性について考察する.
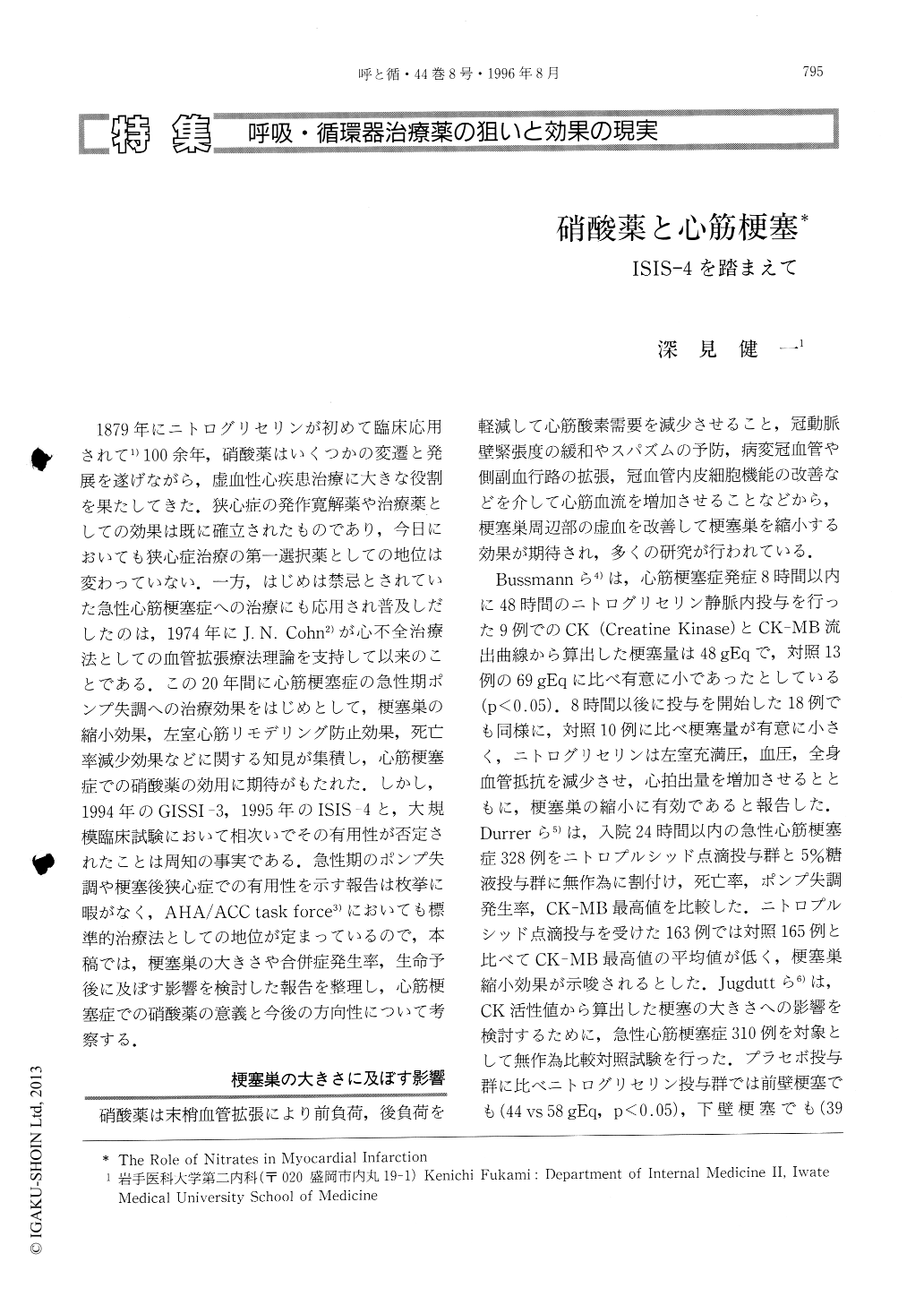
Copyright © 1996, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.


