--------------------
編集後記
八尾 隆史
pp.1740
発行日 2003年11月25日
Published Date 2003/11/25
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1403104243
- フリーアクセス
- 文献概要
- 1ページ目
切除材料の実体顕微鏡像が内視鏡像と組織像の仲介役となり大腸の内視鏡診断が進歩してきたが,胃病変の実体顕微鏡観察は大腸ほど盛んには行われていなかった.その理由の1つとして,上部消化管では表面構造以上に微細な血管構築パターンが重要であるが,これは切除材料では観察できないので,実体顕微鏡像のみでは内視鏡像との仲介役としては不十分であったためだと思われる.しかし,この数年で上部消化管の拡大観察の有用性の報告が相次ぎ,その基礎から応用と現状を把握しておく必要性が生じたため本号が企画された.
上部消化管では拡大内視鏡の応用は多岐にわたっていることが本号で示された.すなわち,良悪性の鑑別診断を含む病変の性状診断・範囲診断に加え,潰瘍治癒過程における再生上皮の評価,Barrett食道粘膜の性状診断(胃型・腸型の鑑別),胃でのHelicobacter pylori感染と粘膜変化の関係,十二指腸非腫瘍性病変の鑑別診断など,炎症から腫瘍まで広範囲に及んでいる.さらには,レーザー共焦点顕微鏡を用いた超拡大観察による生体内での細胞の観察も試みられている.このように,生検組織診断なしでも病変の診断がかなりできるようになり,このままでは病理医は失業しかねないと思わせるほどである.今後,さらに症例を蓄積し,表面の観察である拡大内視鏡像と断面の観察である病理組織像との対比による病変の構築の解析を臨床と病理で協力して行うことにより,臨床画像診断と病理診断の両者がさらに進歩していくと思われる.
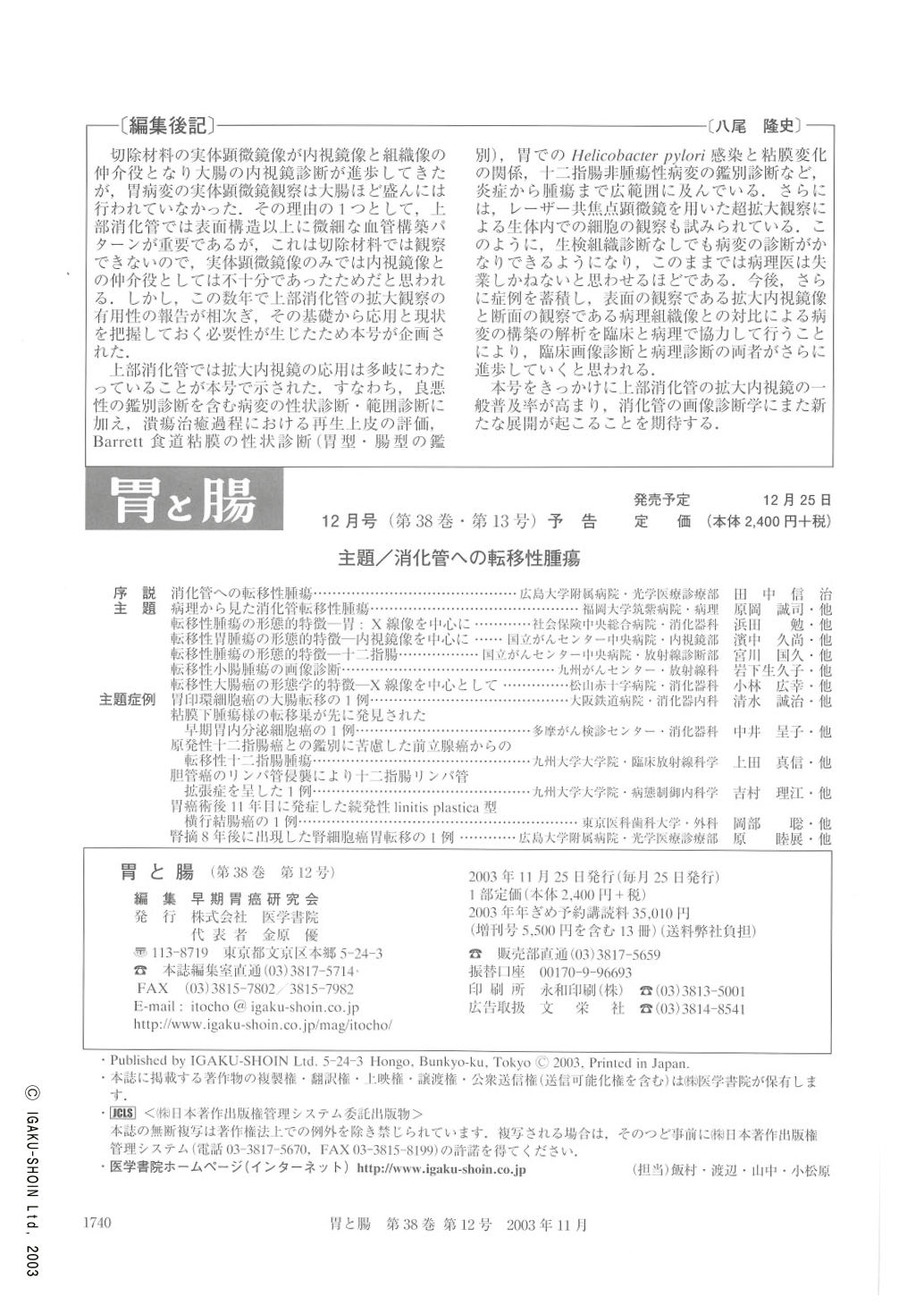
Copyright © 2003, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.


