- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
- 参考文献
はじめに
1)重症心身障害児とは
重症心身障害児(以下,重症児)とは,身体的・精神的障害が重複し,かつ,それぞれの障害が重度である児童と定義される1).知能指数は35以下で身体障害の程度が1級もしくは2級で,大島分類1〜4に相当する.「児童福祉法」のみに規定されている概念のため,発生時期は18歳未満である2).また,超重症心身障害児(以下,超重症児)は重症児と比較して呼吸管理を中心とした継続的濃厚医療・ケアを必要とする児のことである.超重症児の判定基準は,各項目のスコアの合計が25点以上で6カ月以上続く場合とされている3).運動機能に関しては,成長とともに歩行可能例が存在するが,医療の現場では超重症児として判定されていた.重症児・者は,推定で7万9,000人程度とされ,そのうち在宅生活をしている方が5万7,000人程度である4).
2)医療的ケア児とは
2021年(令和3年)6月に「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(医療的ケア児支援法)」が施行された.同法によれば医療的ケア児(以下,医ケア児)とは,日常生活および社会生活を営むために恒常的に医療的ケア(人工呼吸器による呼吸管理,喀痰吸引その他の医療行為)を受けることが不可欠である児童(18歳以上の高校生等を含む)と定義される.それまで重症児に含まれていた医ケア児だが,定義がされたことにより,医療的ケアを必要とする重症児だけでなく,重度の医療的ケアを必要としながらも歩ける・会話できる児も医ケア児と呼ばれるようになった5)(図 16)).
全国の医ケア児(在宅)は,推計で2万382人程度7)といわれており,年々増加している.また,「令和5年度学校における医療的ケアに関する実態調査結果」8)によると,特別支援学校に在籍する医ケア児の数は8,565人(前年8,361人)であり,うち通学が6,674人,訪問教育が1,891人である.また,幼稚園,小・中・高等学校に在籍する医ケア児は2,199人(前年2,130人)である(図 2).そのため,今後も就学する医ケア児は増加することが見込まれる.
3)当院について
当院は,千葉県北西部を中心に,小児から成人まで訪問診療を行っている無床診療所である.小児の対象疾患は,脳性麻痺,染色体異常,神経筋疾患等,多岐にわたり,医療的ケアが必要な方への訪問診療が多い.本稿では,当院で行っている重症児や医ケア児に対しての就学前の訪問リハビリテーション(以下,訪問リハ)でのかかわりに関して示していく.
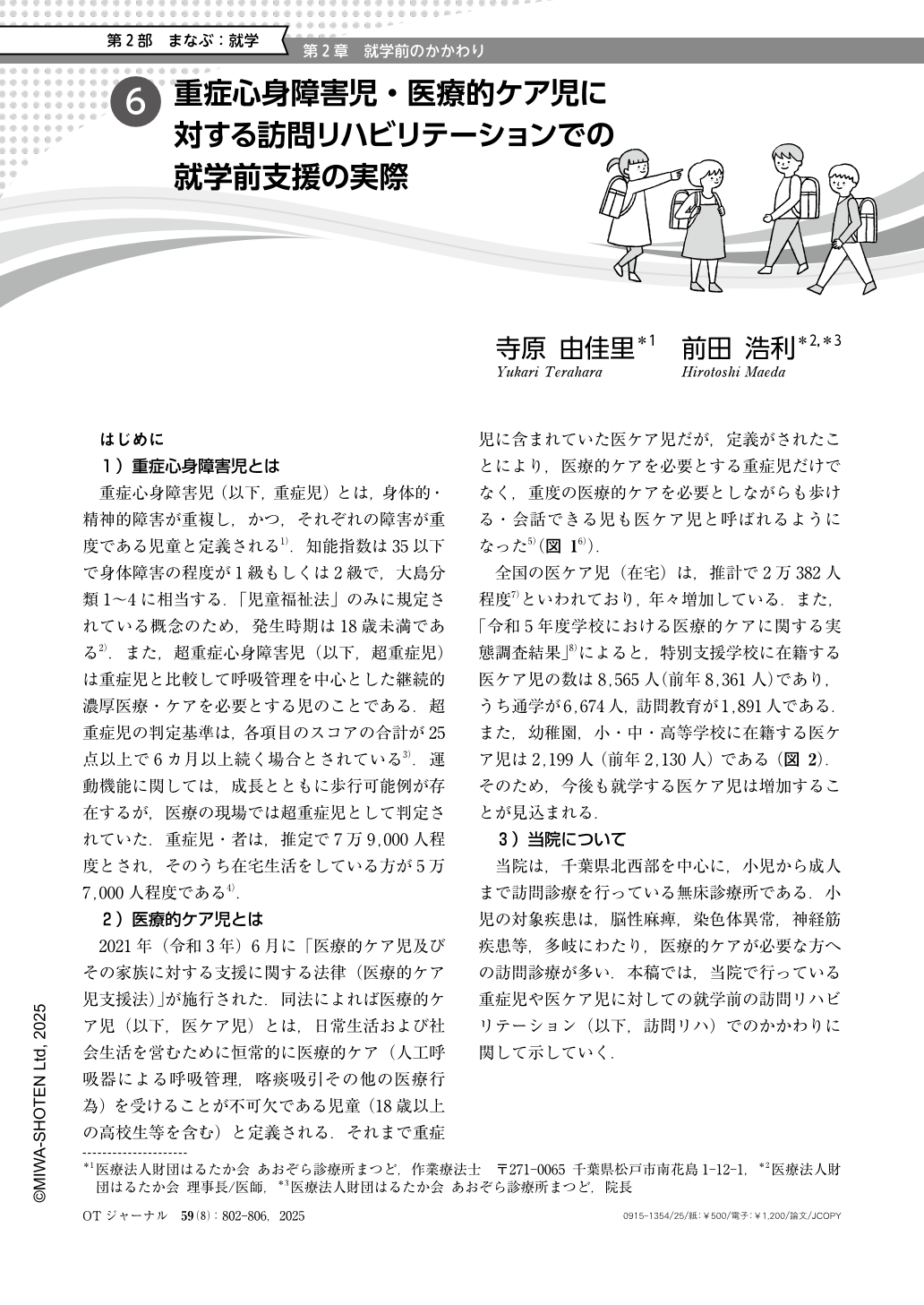
Copyright © 2025, MIWA-SHOTEN Ltd., All rights reserved.


