連載 “出かけたい!”をかなえる—その人・その地域に合った移動を支える・第1回【新連載】
総論:自動車運転支援と地域移動支援のつながりを考える
那須 識徳
1
Satonori Nasu
1
1農協共済中伊豆リハビリテーションセンター
pp.397-401
発行日 2025年4月15日
Published Date 2025/4/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.091513540590040397
- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
- 参考文献
はじめに
近年,国内のリハビリテーション分野では,脳卒中等の傷病後の自動車運転評価への関心が高まり,さまざまな研究が進められてきた.背景には,高齢化率の上昇に伴う高齢者や障害のある運転者の増加,それに伴う法改正への対応が影響していると考えられる.さらに,人口減少や公共交通機関の利用者減少,ドライバー不足により,自家用車に依存せざるを得ない地域の存在も要因の一つとされる.国内で身体障害者に対する欠格事由の基準が設けられたのは1960年(昭和35年)12月に施行された「道路交通法」においてであり,1960年代には国立身体障害者更生指導所(現・国立障害者リハビリテーションセンター)が医療機関での運転評価を他に先駆けて実施した1).その後,1975年(昭和50年)に警察庁が「身体障害者に対する適性試験実施要領」を制定し,全国的に統一基準が整備された.
2011年(平成23年)以降,てんかん発作等による重大事故が多発した影響で,2014年(平成26年)の法改正では運転免許取得および更新時の虚偽申告に対し,1年以下の懲役または30万円以下の罰則が設けられた.これにより,身体障害を生じる疾患の多くが「自動車の安全な運転に支障のあるもの」と見なされ,医師診断書の提出が求められるようになった.
この改正以降,医療機関では「一定の病気等に係る運転者」への対応として,疾患と運転特性の関連,神経心理学的検査やドライビングシミュレーター評価を用いた運転可否の予測研究等を行うようになり,傷病後の自動車運転に関する書籍や論文が数多く出版されている.
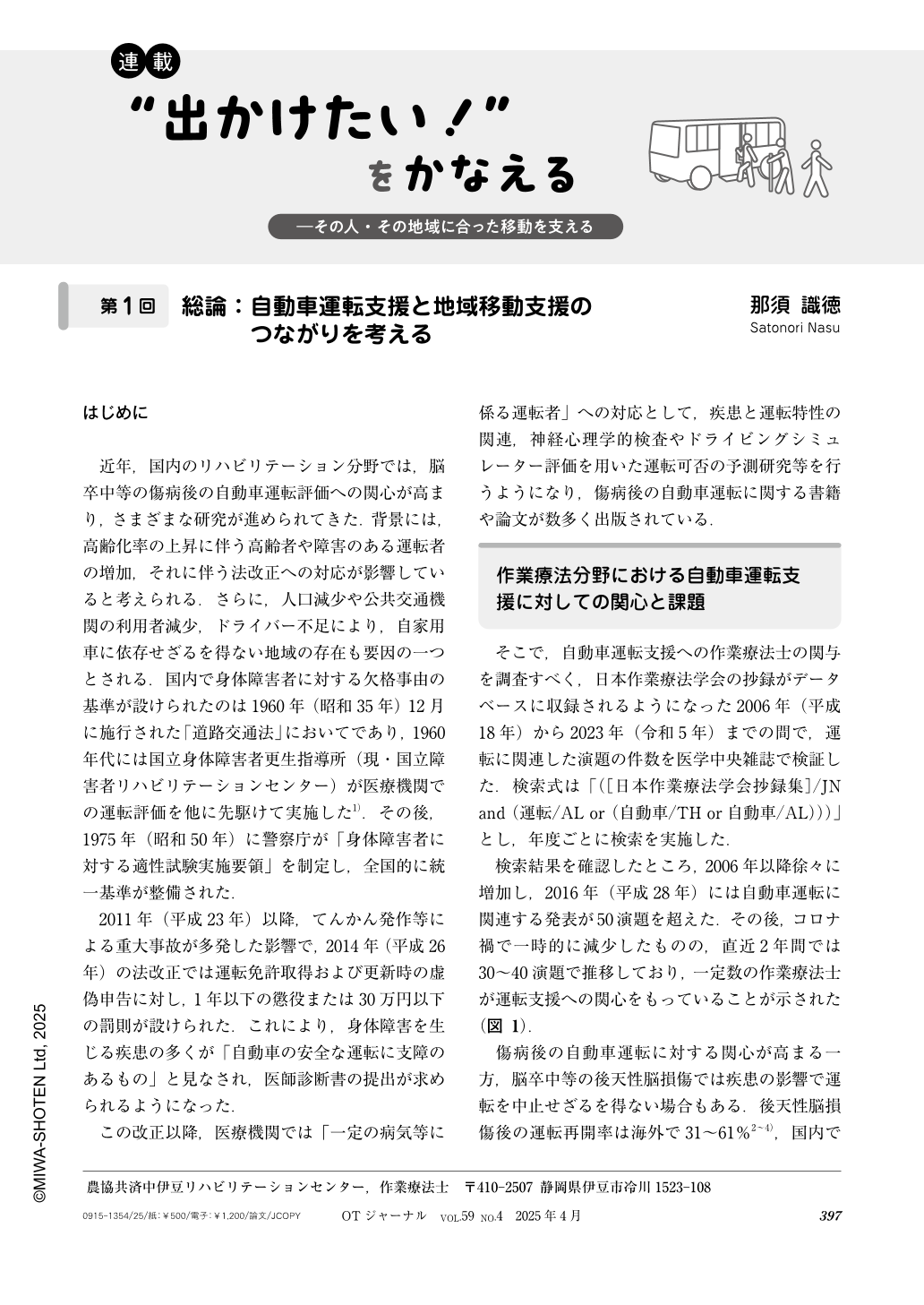
Copyright © 2025, MIWA-SHOTEN Ltd., All rights reserved.


