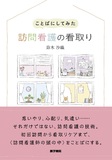書籍を検索します。雑誌文献を検索する際には「雑誌文献検索」を選択してください。
-
基礎医学系
-
臨床医学・内科系
-
臨床医学・外科系
-
臨床医学(領域別)
-
臨床医学(テーマ別)
-
社会医学系・医学一般など
-
基礎看護
-
臨床看護(診療科・技術)
-
臨床看護(専門別)
-
保健・助産
-
看護教員・学生
-
各種医療職
-
東洋医学
-
栄養学
-
薬学
-
歯科学
-
保健・体育
-
雑誌
ことばにしてみた 訪問看護の看取り
医学書院
電子版ISBN 978-4-260-65772-3
電子版発売日 2025年3月17日
ページ数 136
判型 A5
印刷版ISBN 978-4-260-05772-1
印刷版発行年月 2025年2月
書籍・雑誌概要
あの人は、どうしてできるのか。〈訪問看護師の頭の中〉をことばにしてみる。
訪問看護の看取りケアは、特別なものではありません。
対話や日常の看護ケアが重なり、その先にあるのが看取りケアです。
そこには、思いやりや気遣いだけではない、訪問看護の技術があります。
距離感をはかる、一歩踏み込む。応え続ける、安心を置いてくる。
──その一つひとつをことばにしてみました。
ひとつとして同じ場面はない訪問看護の看取りケアを、振り返り、考え、実践するために。
目次
はじめに
Chapter 1 初回訪問と契約の場面で大切にしていること
距離感をはかる
「医療者っぽい脅威」を感じさせない
雑談めいた会話から、今の心情や生活を知る
「わかってもらえている」安心感を持ってもらいたい
情報を全方向からキャッチする
自分を相手の“温度感”に合わせる
もっと知りたい、でも語っていただけそうにない時もある
その人の「一番弱いところ」を探っておく
“困った時に相談できる人”として認識してもらうために
一歩踏み込む
キーパーソンを見極める
「何かがあった時に、お知らせしたい人はいますか?」
そっと手を添えるくらいの距離感を保つ
「疾患とともに生きるあなたの人生に興味がある」
「治療はもうない」と言われても、できることはあることを伝える
思いに触れる
今、療養者さんが人生のどのような状況に置かれているのかを知る
療養者さんが病状をどのように受け止めているのかを知る
会話が一向に深まらない時は、背景にある想いを想像してみる
ご本人が「何をどう聞いているか」に、ただ耳を傾けてみる
“どこで過ごしたいと思っているのか”につながる言葉を捉える
家で過ごすために提供できるサポートについて、しっかり伝える
介入ペースは、ご本人の生活への影響を最優先して提案する
時間の使い方は本人の生活を主体に考える
看護師の介入を受けるか否かの選択権は、療養者さんにある
看護師が相談先となれることを、自信を持ってお伝えする
“意味を伝える言葉”で説明する
契約に至るまでの対話から、ご本人とご家族の思いを推しはかる
契約手続きの中で、ターミナルケア加算、エンゼルケアについて説明する
書面を読み上げるのではなく、“意味を伝える言葉への変換”を心がける
[Case1] 最後まで、自分で選択する
Chapter 2 その時が近づいてくるまでに──じっくりと対話を積む
応え続ける
「あとどれくらいですか?」に含まれる想いを推察する
ご家族にも同様に、必要な情報を重ねてお話しする
目標や計画があれば、時機を逃さず実現に向けて動く
療養中だからこその不安や疑問に応え続ける
確かな多職種連携が療養者さんとご家族の安心につながる
療養者さんの困りごとには、チームで連携、速やかに解決策を探る
今しか聞けないことは、タイミングを逃さず聴く
その先を見据えて関わる
今後の経過の中でご本人やご家族が抱える疑問を想像し、応えていく
想像を巡らす大前提は、相手がどういう人かを知っていること
私たちの目の前の療養者さんの“今”だけでなく、“前後”までを意識する
薬への抵抗感の背後にある誤解を解く
「薬が上手に効いてよかったです!」
安心を置いてくる
医療者がいなくても穏やかに暮らせるよう“安心を置いてくる”
緊急携帯=ナースコールではない
今まで身近でなかったものを、自分自身の一部にしてもらう
病院経由で生じた不安の種には、情報共有と根回しで対処する
看護師の影響力を自覚する
ご家族は「そこに居るだけで意味がある」ことを伝えておく
ご家族の介護力に応じた提案やアドバイスを
ご家族の張り詰める気持ちをゆるめる
サインを見過ごさない
病状が一段進んでいくサインを見過ごさず、客観的に事実を伝える
今後の経過がイメージできるよう説明する
入院や治療などの変化がある時は、特に細やかな連携が不可欠
[Case2] その先を見据えた“安心”を置いていく
Chapter 3 ご様子の変化が見られ始めたら──手際のよいケアと繊細な観察を継続する
安楽なケアを継続する
安楽なケアの基本は、手際のよいケアと繊細な観察
“今までと何か違う”様子が現れてきたタイミングを逃さない
ご家族の“何もしないこと”への不安を拭う
状態が変化する中でも、安楽に過ごせるためのケアをご家族とともに継続する
終末期の変化に対応する
訪問頻度の調整は、圧迫感を感じずご家族が選択できるように
変化に合わせた介入の調整のため、アセスメントを重ねる
不安や心配を前提にしない
“いつものあの人ではない姿”を見るつらさを慮る
これからの変化に備える
少しずつ、想像しやすい言葉で伝えていく
いつでもバックアップがあることを伝えておく
“食べさせることができないこと”に罪悪感を持たせない
具体的な口腔ケアの工夫をお伝えする
ご家族とともに安楽を支えるケアを行う
ご本人の意思を想像しながらケアをする
配慮が見えるケアを、言葉にしながら行う
[Case3] 縁をつなぐ
Chapter 4 看取る──ご家族のご意向に沿ってお見送りをする
連絡を受け、ご自宅に伺う
医師と情報を共有する
死の三徴候の確認は、ゆっくりと丁寧な所作で行う
医師による“最期の診察”を行うことを伝える
静かに待つ、ゆっくり進める
ご家族の頭の中の整理を待つ
最期の診察に向け、現実的な流れに触れていく
最期の診察を行う
その場の雰囲気やご家族の様子は医師にあらかじめ伝えておく
一歩下がってサポートに徹する
ひとつずつシーンを切り替え、エンゼルケアについての意向を確認する
必要な手配について情報提供をしておく
普段からの情報収集が支援につながる
死後の処置を行う
整容ケアは保清と保湿が基本
メイクはご家族のご要望があれば行う
メイクよりも大切なのは、ご逝去直後の保湿
ケアへの参加は強要しない
前向きな印象を残す言葉を心がける
状況によっては“仕上げだけ”をお願いしてみる
“見せないほうがよいケア”の際は、さりげなく席を外してもらう
消毒液の使用や排泄物の処理は特に速やかに行う
医療機器の除去は丁寧に、薬剤の確認・処理も忘れずに行う
不安を残さない
ご利用終了後の流れをお伝えする
退室時の挨拶は、より丁寧に
グリーフケアとしての訪問は、ご家族のご意向があれば行う
[Case4] 家族のペースを守り続ける
Column
処理できない気持ち
Appendix
訪問看護師のバッグの中
おわりに