特集 先生は大変だ―「先生たち」のメンタルヘルスを通して見えるもの
日本語臨床における「先生転移」―治療者が「先生逆転移」を自覚し取り扱うために
加藤 隆弘
1
1九州大学大学院医学研究院精神病態医学
pp.841-844
発行日 2024年12月5日
Published Date 2024/12/5
DOI https://doi.org/10.69291/pt50060845
- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
- 参考文献
はじめに
我が国における精神科臨床場面あるいは心理臨床場面において,私たち治療者は日本語を使用して患者あるいはクライアント(以下総じて「患者」と表記)と日々対峙しているが,お互いをどのように呼び合っているのであろうか。英会話など欧米語での会話と日本語会話の大きな違いは,日本語では主語を割愛できることである。つまり,日本語会話では一人称である自分自身や二人称である目の前の相手をあえて言葉にすることなく会話が成立しうるのである。この日本語での主語なし会話は,日本人のパーソナリティ形成そして日本における精神療法に計り知れない影響を与えているはずであると筆者は考えている。他方,日本語会話において全く主語が必要ないというわけではない。私たちは臨床場面における治療者-患者との会話においてお互いを何らかの呼称で呼び合っており,患者が私たち治療者を呼ぶ際に最も頻用されるのが「先生(せんせい)」という言葉であろう。「先生」という言葉ほど便利なものはない。初診やインテークなど初めて患者と治療者とが出会う場面において,患者は見ず知らずの治療者のことを「先生!」と呼ぶことで会話が成立するのである。本稿では,筆者が20年程前に日本語臨床研究会で発表した臨床場面における「先生転移」「先生逆転移」のコンセプトを紹介し,日本で実践する精神医療や精神療法場面において盲点になりやすい「先生逆転移」とその取り扱いの意義に言及する。
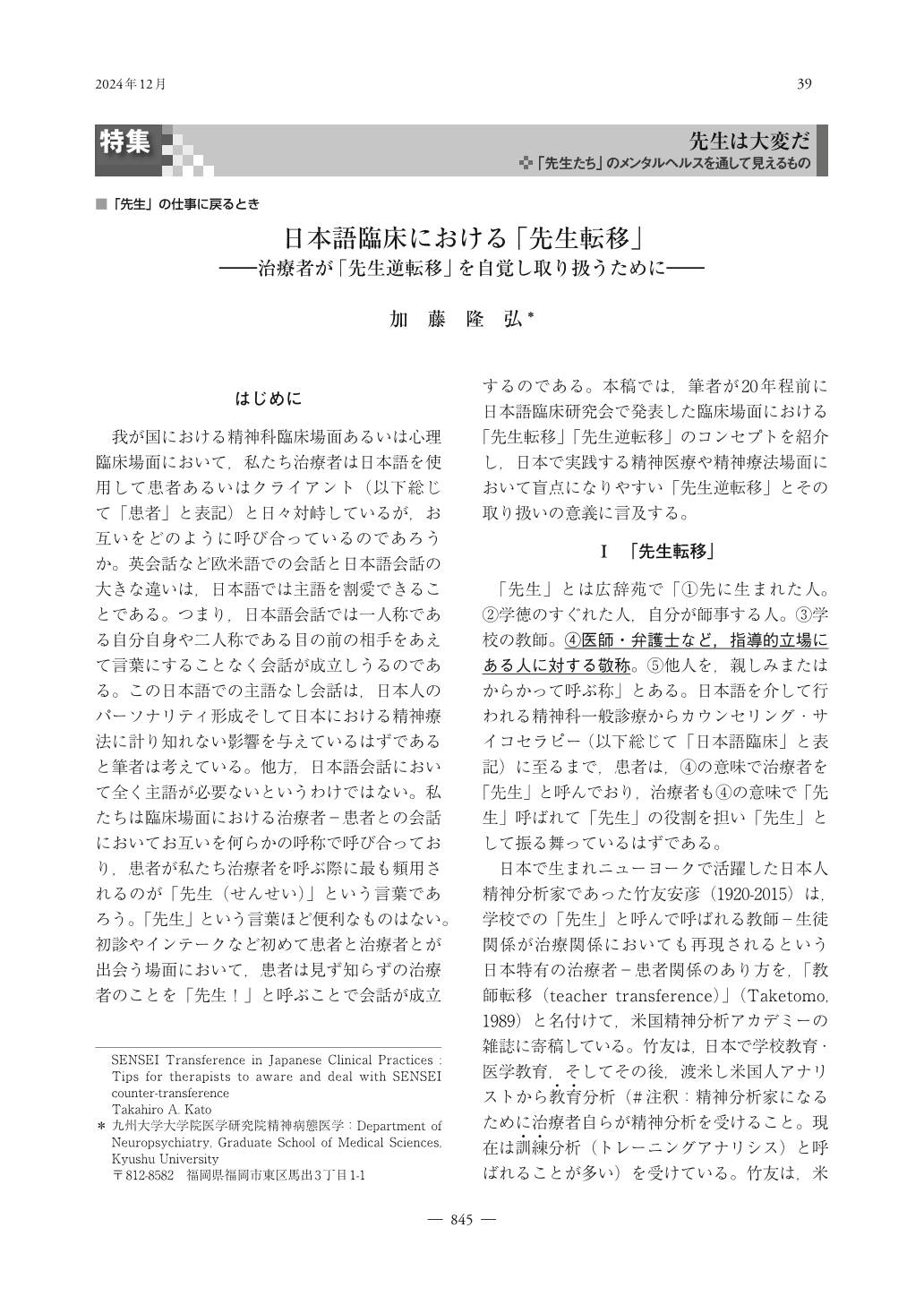
Copyright© 2024 Kongo Shuppan All rights reserved.


